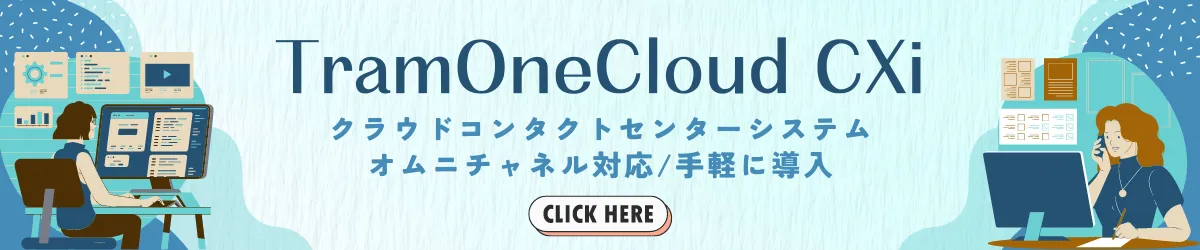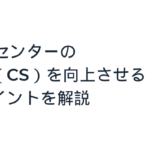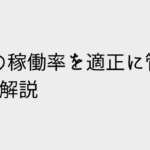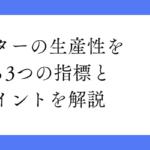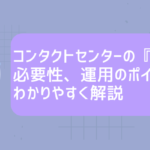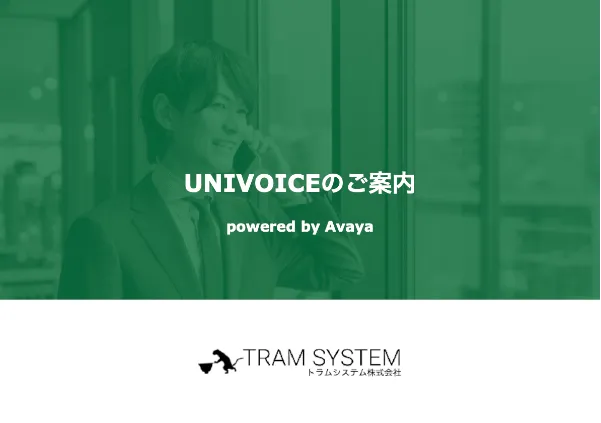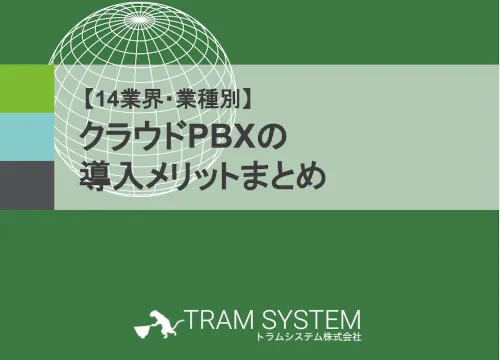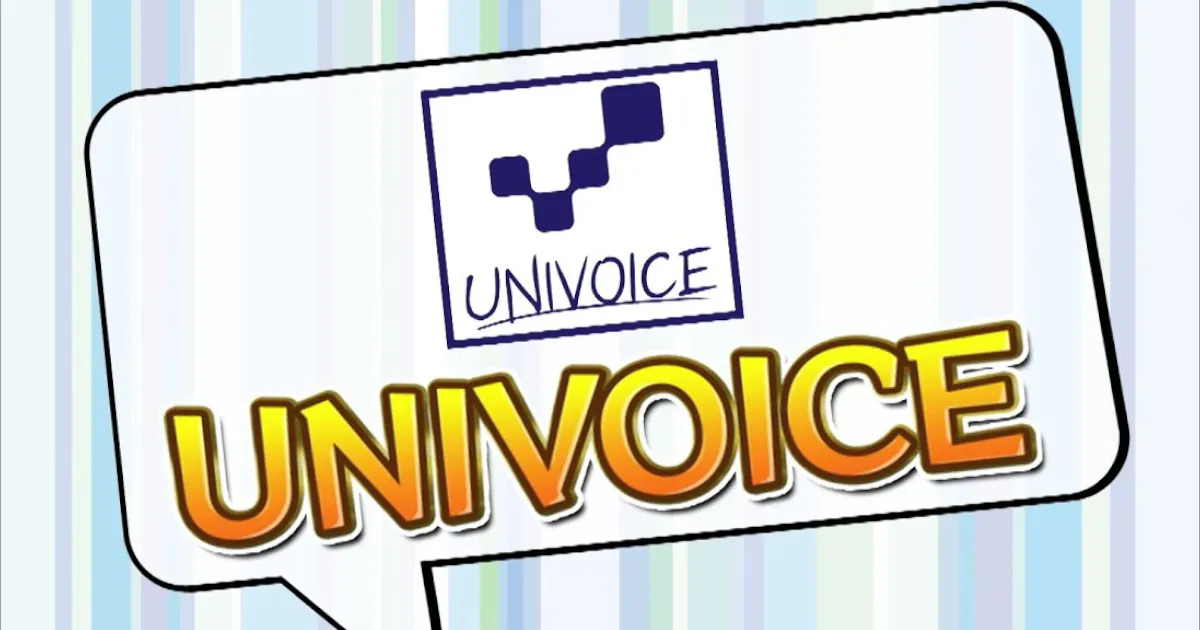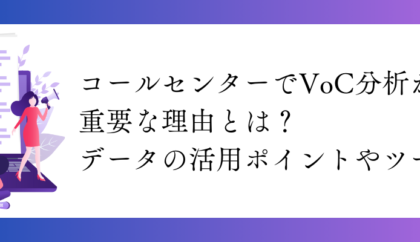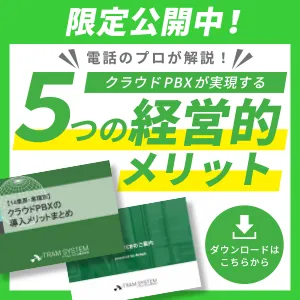コールセンターはどう評価する?指標・基準・ポイントなど解説|トラムシステム
コールセンターやコンタクトセンターは、オペレーターと顧客が電話やチャットなどで直接やり取りする顧客対応の最前線です。よりよいサービス提供、企業やブランドのイメージ向上には、定期的な品質評価や改善が欠かせません。
この記事では、コールセンターを評価する際の手順やポイント、評価指標、基準などについて解説します。

コールセンターを評価する重要性
コールセンターのパフォーマンスを評価することで、企業や現場にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。まずはコールセンター評価の重要性について説明します。
顧客満足度の向上
コールセンターの対応品質の良し悪しは、顧客満足度に直結する重要な要素です。顧客は疑問解消やサポートを求めてコールセンターに連絡をしますが、その際のオペレーターの態度や迅速さ、問題解決能力などが、センターや企業に対する満足度に大きな影響を与えます。
顧客満足度を評価する上で注意したいのが、企業による自己評価と顧客による他社評価の結果は、必ずしも一致しないという点です。企業側が「顧客が満足するレベルのサービスを提供できている」と考えていても、顧客は不満を持っている可能性もあります。
このため、企業は定量的な基準などを用いて、自社センターのパフォーマンスを客観的に評価することが重要です。
競争力の強化
コールセンターの評価は、競争力の強化や事業の成長にも重要な役割を果たします。顧客サービスの品質が向上することで、顧客ロイヤルティの向上やリピーターの増加、口コミによる新規顧客の獲得などにつながります。
国内外に類似するサービスや商品が世の中に溢れている現代において、よりよい顧客体験の提供は他社との差別化にも重要です。コールセンターでの高品質のサービス提供は、商品やサービスに付加価値を与えるのです。
オペレーターのモチベーションアップと育成
コールセンターのオペレーターは日々多くの問い合わせに対応しています。「ありがとう」と感謝の言葉を受け、喜びややりがいを感じることがある一方で、クレーム対応をしたりネガティブな言葉を受けたりと、ストレスを感じることもあるでしょう。
コールセンターを定期的に評価し、結果に応じてオペレーターに適切にフィードバックすることで、オペレーターは自身の良い点を認識し、悪い点を改善できるようになります。自分の仕事により自信を持って望めるようになり、モチベーションアップにもつながるでしょう。
コールセンターの3つの評価ポイント
コールセンターを評価する際には、個別のKPIを闇雲に測定・分析するのではなく、各評価指標をカテゴリに分け、総合的にモニタリングすることが重要です。ここからは、コールセンターを評価する上で意識すべき3つの評価ポイントについて解説します。
パフォーマンス(生産性)
パフォーマンス(生産性)は、コールセンターが与えられたリソースを最大限に活用しているかどうかを示す重要な基準です。
仮にコールセンターの対応品質が非常に優れていて、高い顧客満足度を獲得できていたとしても、それを実現するために多大なコストがかかっていては本末転倒です。
応答率やオペレーターの稼働率、平均処理時間などの指標を用いて、効率的なサービス提供ができているかを評価しましょう。なお、評価に用いる主なKPIは、この後の章で詳しく解説しています。
クオリティ(品質)
クオリティ(品質)は、オペレーターによる対応の正確性やコールセンターの教育体制・業務フローの良し悪しを測定するための基準です。クオリティの向上は、顧客満足度の向上に欠かせません。
一次解決率やミス発生率などによる定量的な対応品質評価に加えて、アンケートなどで顧客の満足度や声を収集します。クオリティに満足していない顧客が多い場合には、オペレーターの教育、業務フローやマニュアルの見直しなどを実施しましょう。
プロフィット(収益性)
プロフィット(収益性)は、コールセンターが企業に収益をもたらす存在であるかを評価する基準です。
一昔前まで、コールセンターは顧客からの問い合わせ対応などの受け身の業務が主であり、コストはかかるが利益は生み出さない「コストセンター」と呼ばれることも多くありました。しかし、最近では顧客ロイヤリティやリピート客の獲得などの利益(プロフィット)につながる使命を持つ「プロフィットセンター」としての位置づけに変化しています。
平均通話コストやクロスセル・アップセル率などを用いて、コストの最小化と利益の最大化を図りましょう。
パフォーマンスに関する評価指標
コールセンターのパフォーマンス(生産性)を評価するためには、以下のKPIがよく用いられます。
応答率
応答率は、お客様からの入電のうちオペレーターが実際に対応できた件数の割合です。一般的には、すべての着信に対する応答率を計算します。応答率が高ければ高いほど、問い合わせや注文に多く応対できており「電話がつながりやすい」状態です。
放棄呼率
放棄呼率は、電話が顧客によってオペレーターにつながる前に切られたり、システムトラブルなどにより電話が切断されたりした割合です。放棄呼は、多くの場合「電話をかけたけどつながらなかった」という状況を示すため、放棄呼率が高い場合はリソースを増やすなどの対応が必要です。
稼働率
稼働率は、オペレーターが業務時間の中で、本来である顧客対応業務全般に割いた時間の割合です。オペレーターの主な業務は問い合わせ対応ですが、それ以外に報告書作成やミーティング、研修などもあります。
稼働率は、それらの非生産的な業務と本来行うべき生産的な業務(顧客対応業務)の割合を示す指標です。高い稼働率は、オペレーターが生産的に働いていることを示し、リソースが最適に活用されている状態を表します。
占有率
占有率は、オペレーターの稼働中に実際に顧客対応に割り当てた時間の割合を示す指標です。具体的には、通話時間、保留時間、後処理時間、待機時間の中で、待機時間を除いた「実対応時間」の割合を算出します。
高い占有率は、それだけオペレーターが連続して顧客対応にあたっている状況です。待機時間が短く抑えられている一方、オペレーターに休む暇を与えず、大きな負担を強いている可能性もあるため、76~87%程度が目安といわれています。
CPH(平均処理件数)
CPH(Calls Per Hour:平均処理件数)は、1時間あたりに処理されるコールの平均数を示す指標です。高いCPHは効率のよいコール処理を示し、コストを削減し収益性を向上させるのに役立ちます。
ASA(平均応答速度)
ASA(Average Speed of Answer:平均応答速度)は、顧客のコールがいかに早く応答されるかを示す指標です。一般的には秒単位で計測し、ASAが小さいほど、顧客は短い待ち時間で対応を受けられていることを意味します。
サービスレベル
サービスレベルは、一定の時間内に対応・処理できた割合を示す指標です。例えば「80%のコールに20秒以内に応答する」といった具体的な目標が設定されます。応対開始するまでに制限があるかどうかが、サービスレベルと応答率の違いです。
ATT(平均通話時間)
ATT(Average Talk Time:平均通話時間)は、オペレーターと顧客による通話時間の平均です。顧客履歴の入力など通話後の後処理時間は含まず、純粋な通話時間を計測します。
ATTの高さは、それだけ1件の問い合わせに多くの時間をかけていることになります。顧客の話が長い、オペレーターの対応が不十分で問題解決に手間取っているなどの原因が考えられるため、原因にあわせた対策が必要です。
AHT(平均処理時間)
AHT(Average Handling Time:平均処理時間)は、オペレーターが1件の問い合わせを完了するのにかかる平均時間を示します。ATT(平均通話時間)と異なり、AHTには通話時間に加えて対話内容の記録などの後処理時間も含まれます。
AHTは事務処理の時間にあたるため、AHTを改善することで生産性の向上に寄与します。一方で、無理にAHTの短縮を強いることで、後処理作業の品質が低下する可能性がある点には注意が必要です。
クオリティに関する評価指標
コールセンターのクオリティ(品質)を評価するためには、以下のKPIがよく用いられます。
モニタリングスコア
モニタリングスコアは、オペレーターがどれだけ優れたパフォーマンスを発揮しているかを評価する指標です。トレーナーや上司がオペレーターと顧客のやり取りを聞き、コミュニケーション能力、問題解決能力、商品知識などの点で特定の基準にもとづいてスコアをつけます。
それぞれのオペレーターの強みや改善点を特定し、サービス品質を向上させることが目的です。オペレーターにとっても、自分の仕事ぶりが定量的に表されることで、モチベーションアップや自己研鑽につなげられます。
一次解決率
一次解決率とは、顧客の問題や要望が初回の問い合わせで解決された割合を示します。問い合わせに対して電話を折り返して回答した場合や、二次対応者や別部署の担当者に転送した場合は、一次解決にはなりません。
高い一次解決率は、効率的な顧客サポートを示し、顧客の不満を軽減します。一次解決率が低い場合には、オペレーターの教育やサポート体制の強化、マニュアル整備などの対応が必要になります。
CS(顧客満足度)
CS(Customer Satisfaction:顧客満足度)は、顧客が提供されたサービスにどれだけ満足しているかを評価する指標です。通常、顧客にアンケートの回答を依頼し、その内容にもとづいてスコアを算出します。
「疑問が解消した」「丁寧なサポートを受けられた」といったポジティブな体験は、顧客満足度の向上や顧客ロイヤリティの獲得につながります。反対に「オペレーターにつながらない」「要望を聞き入れてもらえなかった」といったネガティブな体験は、顧客満足度の低下や企業イメージの悪化といったデメリットにつながるでしょう。
ミス発生率
ミス発生率は、オペレーターが問い合わせ対応において顧客に誤った情報を提供した割合を示します。誤った情報は顧客の不満を引き起こし、信頼性を損なう可能性があるため、ミス発生率はできるだけ低い数値に抑えることも求められます。
ミス発生率を低減するためには、オペレーターのトレーニングやマニュアル整備、ベテランオペレーターやSVなどによるサポート体制の強化などが必要です。
プロフィットに関する評価指標
コールセンターのプロフィット(収益性)を評価し、改善するためには、以下のKPIがよく用いられます。
CPC(平均通話コスト)
CPC(Cost Per Call:平均通話コスト)は、1件の問い合わせ処理にかかる平均コストを示す指標です。これにはオペレーターなどの人件費、設備や施設の維持費、通信コスト、コールセンターシステムなどのコストなどが含まれます。コールセンター運営にかかる全てのコストを計算に含めて算出するのが理想です。
CPCの低さは、コスト管理が効率的に行われており、収益性が高い状態を意味します。一方で、CPCの適正値は各企業やコールセンターの現状、業務内容、運営方法などによって異なるため、それらをふまえて個別に目標値を計算・設定する必要があります。
クロスセル率・アップセル率
クロスセル率は、顧客が元々購入しようとしていなかった追加の商品やサービスを購入する割合を示します。アップセル率は、顧客が元々購入しようとしていた商品やサービスを高額なものに変更する割合です。
クロスセル率とアップセル率は、コールセンターが既存の売上に加えてどれだけの追加売上を出せたかどうかを表します。コールセンターをコストではなく利益(プロフィット)を生み出す組織にするための重要な指標といえます。
NPS(顧客推奨度)
NPS(Net Promoter Score:顧客推奨度)は、顧客が企業やブランドをどれだけ積極的に他者に推奨したいかを示す指標です。NPSは「この商品・サービスを友人や同僚にどの程度勧めたいですか?」というアンケートに回答してもらって算出します。
最近は、ネットの口コミや友人などからのアドバイスを元に商品やサービスの選択をする人が増えてきています。よりよい商品・サービスや顧客体験の提供によってNPSを向上させることで、顧客の忠誠心と口コミを増加させ、新規顧客獲得につながるでしょう。
離職率
離職率は、雇用したオペレーターの退職率を示す指標です。高い離職率はトレーニングと新人教育にかかる追加コストを引き起こし、品質と収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
オペレーターが離職する原因には、給与や待遇への不満、業務によるストレス、業務で必要な知識やサービスのレベルの高さなどが挙げられます。コールセンターの運営者・管理者は、適切な人材採用や十分な研修・サポート体制の提供、評価制度の整備によって、オペレーターの定着率の向上を図りましょう。
コールセンターを評価する方法・手順
コールセンターのパフォーマンス評価は、評価する目的や項目、手段、頻度を検討した上で実施することが重要です。ここからは、コールセンターを評価する際の手順を解説します。
1.評価項目を決める
まずはどのような評価項目を用いて、コールセンターを評価するのかを決定します。用いる指標はセンターの目的や業務内容、課題によって異なります。この記事の前半で紹介した以下の3つの視点で考えてみましょう。
・パフォーマンス
・クオリティ
・プロフィット
評価指標が決まったら、各指標の現在の数値や目標値を設定します。しかし、評価指標はあくまで数字であり、コールセンターの実情と完全に一致するわけではありません。評価を実施することでどのようなコールセンターを実現したいかを意識することが重要です。
2.調査方法を決める
ステップ1で決定した評価項目や評価指標について、具体的な調査方法を決定します。具体的には、KPIの測定、モニタリング、ミステリーコール、顧客アンケート、従業員へのヒアリングなどがあります。
応答率や平均通話時間といった数値で表される指標は、どのように算出に必要なデータを収集するかについても検討しましょう。
3.定期的に評価を実施する
コールセンターの評価は一度だけでなく、定期的な実施が重要です。定期的な評価はコールセンターの改善と持続的な品質管理を可能にします。適切な評価の実施頻度は、評価指標、業務内容、目標によって異なります。
例えば、定量的に表される指標は、コールセンターシステムのレポート機能などを活用して毎月評価することが可能です。アンケートやヒアリング、モニタリングなどを通じて定性的に評価する指標は、数ヶ月に一度行うのが一般的です。
まとめ
コールセンターの評価は、サービス品質の向上、生産性の最大化、収益性の向上に寄与します。コールセンターの目標やあるべき姿などを明確にした上で、適切な評価指標を設定、さらに効率的・継続的な評価プロセスを確立し、コールセンターの成功につなげましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。