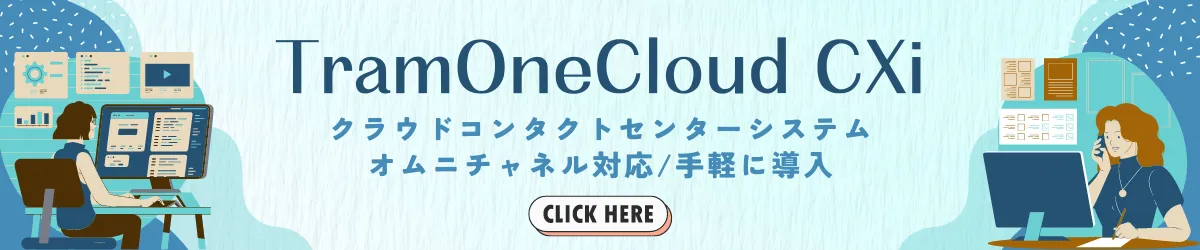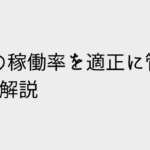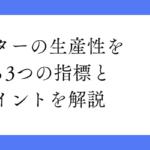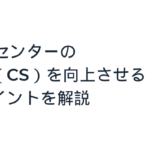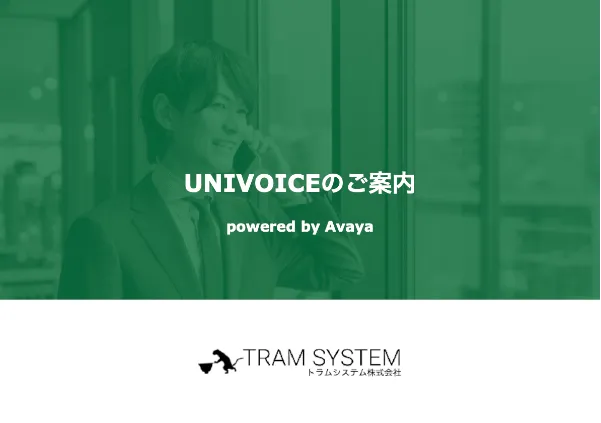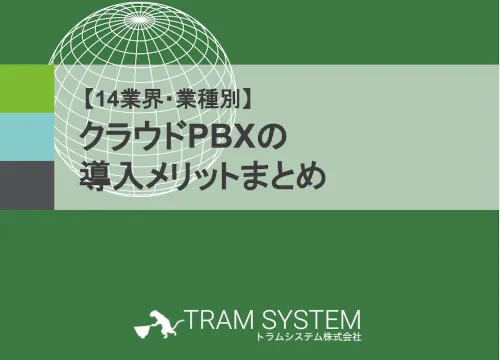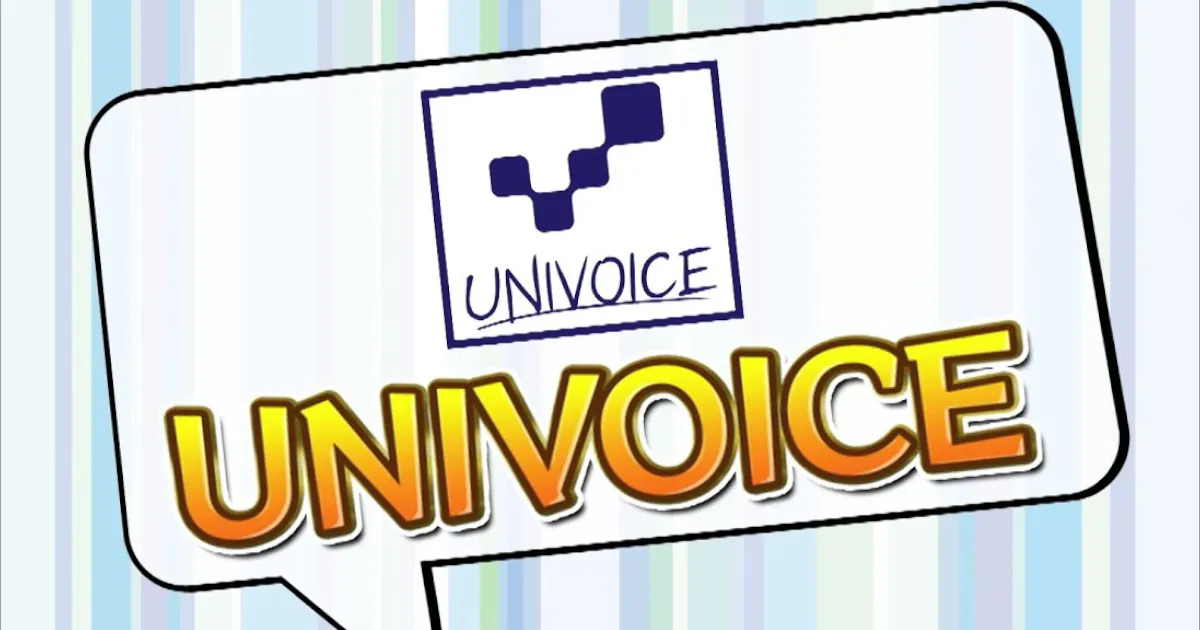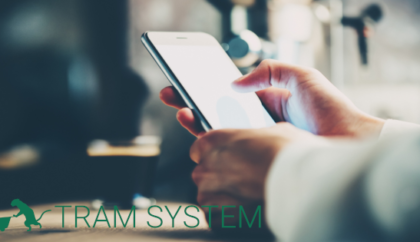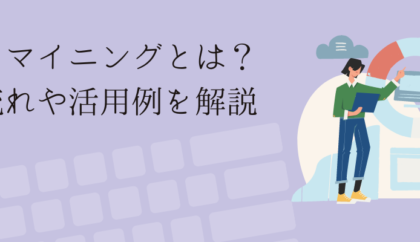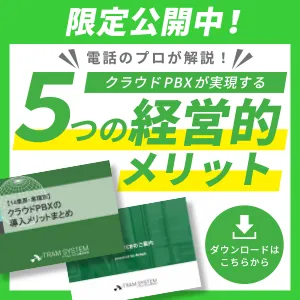コールセンターの評価基準「ASA」とは丨悪化する原因と対策を解説|トラムシステム
コールセンターやコンタクトセンターの業務効率改善に欠かせない品質指標である「ASA」(平均応答速度)。KPI指標として目標値を設定しているところも多く、ASAを適切に管理・分析することで応対品質向上に繋がります。
この記事ではASAの基本的な説明や、ASAが悪化してしまう原因と対策を詳しく解説します。

目次
ASA(Average Speed of Answer)とは
ASA(Average Speed of Answer)とは日本語で「平均応答速度」と訳します。お客様からの電話をかけてからオペレーターが応対するまでの平均時間です。応答までにかかった時間の合計を入電総数で割って算出します。
平均応答速度が短ければ短いほど、お客様をお待たせすることなく電話応対ができている状態です。一般的に20秒程度にKPIを設定することが多いですが、自社センターの状況に合わせて目標設定をしましょう。
最終的にオペレーターに繋がってお客様の課題が解決できたとしても、「繋がるまでに待たされた」という事実は顧客満足度を想像以上に低下させます。応対品質というと業務効率や問題解決率などに注目しがちですが、顧客満足度に繋がる指標としてASAを適切に管理することが大切です。
SL(サービスレベル)との違い
ASAと似たような品質指標にSL(サービスレベル)があります。SLは、事前に設定した時間内にオペレーターが応対・処理できた割合を示す品質指標です。
ASAと同じように「繋がりやすさ」を示す重要な指標ですが、ASAでは応対までの平均時間、SLでは設定時間内に応対できた達成率、と表す状態に差異があります。
例えば「20秒以内の着信率(SL)を80%以上、ASA は20秒以内」と設定したセンターの場合で、以下のように応対速度にバラつきがあるケースを考えてみましょう。
12秒 15秒 18秒 16秒 40秒
5件中4件は指定時間内に応対できているのでSLは達成、ASAは20.2秒のため未達となります。どちらか一方では重大な課題点を見逃してしまう可能性があるため、組み合わせて分析することでセンターの応対状況を正確に把握することが大切です。
ASAが悪化する要因
ASAを活用するためには算出した後に分析・改善活動を続けることが重要です。ここからはセンター管理者が知っておきたい「なぜASAが悪化するのか?」を4つ解説します。
オペレーターの人手・スキル不足
オペレーター数を大幅に上回る入電が合った場合はASAが悪化します。また、オペレーターのスキル不足により各応対時間や後処理時間が長くなってしまうと、新たな入電を受けられません。そのため、新人オペレーターが多いセンターではオペレーターのスキル不足によりASAが悪化する傾向があります。
入電数の急増
新商品が発表・発売された後や、テレビ・SNSなどで取り上げられた後は自社で扱う商品・サービスへの問い合わせが急増します。一時的な悪化であり、次第に落ち着いていくことが多いです。
なお、入電数の急増が予測できる場合は、オペレーターのシフト組み換えることでASAの悪化を予防できます。落ち着いて入電ピークを迎えられるように、普段から営業・開発・マーケティングなどの関連部署と情報連携を密にするようにしましょう。
問い合わせ以外の電話が多い
コールセンターへ問い合わせ以外の入電が多い場合は関連部署への転送などの対応が必要です。本来の業務ではない処理に時間が取られてしまうため、ASAが悪化します。
対策としては「どのような入電理由・傾向があるのか」を明確にし、オペレーターが業務に集中できるようにIVRの導入やFAQの整備などで入電を制御しましょう。
AHT(平均処理時間)の増加
AHT(平均処理時間)とは電話を受けてから応対が終了するまでにどれくらいの時間がかかるかを表す品質指標です。実際に応対していた時間と、電話応対後の結果入力や後処理にかかる時間の合計時間を表します。
問い合わせの回答を探すのに時間がかかる、要点を絞って端的に説明できない、応対結果の入力が遅く次の入電を受けるまでに時間がかかるなど原因はさまざまです。原因に合わせた対策を検討しましょう。
ASA改善のポイント
ASAが悪化した場合は要因を特定し、適切に改善策を実行することが重要です。ここからは具体的な改善ポイントとして、要因ごとにどのような対処が有効なのかを解説します。
代表的な例を4つ紹介しますので、参考にしてください。
適切なWFM(Workforce Management)
単純にオペレーター数を増員すればASAは改善します。しかしコールセンターにおけるコストの大半を占める人件費が増大するため、センター運営を圧迫することは避けられません。
センター管理者はコールセンターの業務量に応じて過不足なくオペレーターを配置することが求められています。
WFM(Workforce Management)は、特定の業務量をこなすために必要な要員数を算出・調整するためのマネジメント手法です。過去の入電・応対実績をもとに将来の入電数・必要要員数を算出します。WFMを適切に実施することで必要最低限のオペレーターで業務運営ができるため、余計なコストをかけずともASAの改善が可能です。
規模の小さいセンターであれば手動でWFMを実施できますが、現在は多くのWFMツール(システム)が発売されています。特にクラウド型ツールは手軽に利用が開始できるので前向きに導入を検討してみましょう。
FAQ・チャットサービスの導入
お客様向けFAQ(よくある質問と回答集)やチャットサービスを導入することで、入電数自体を減らす対策も有効です。同じオペレーター数であっても入電数が減少すれば、多くの入電に応対できます。
FAQやチャットサービスでは、電話よりも気軽に問い合わせできる、画像や動画を使ったスムーズな回答が受けられるなどお客様へのメリットも大きいです。
電話だけを対応していたコールセンターもFAQやチャットサービス、メール、SNSなどを顧客接点を細分化・拡大することで、業務効率化や応対品質向上、顧客満足度向上に繋げることができます。
オペレーター教育
AHTやACW(平均後処理時間)を短縮することで業務効率が向上し、結果的にASAの改善に繋がります。AHTやACWの短縮にはオペレーターの教育が欠かせません。センター管理者は以下のようなポイントを押さえて教育・研修カリキュラムを組むことが重要です。
・応答速度向上
・応対スキルの向上
・クレーム対応スキルの習得
・ストレス対策
以下記事ではオペレーター教育のポイントをより具体的に解説しています。ぜひ参考にしてください。
オペレーションの見直し
応対業務に付随する受発信画面の操作や、応対履歴検索・入力といった業務オペレーションを見直すことも重要です。古いマニュアルを使い続けていたり、非効率な業務を実施していたりと、オペレーション方法に問題があることもあります。
具体的には業務マニュアルや実際の応対業務を確認し、以下の様な観点をチェックしましょう。
・調べ方が分からない、調べているものの回答が見つからない状況はないか
・要点を絞ってうまく伝えられているか
・問い合わせ内容を正確にヒアリングできているか
・後処理に時間がかかる、処理待ち時間が発生していないか
・オペレーターが迷ってしまうような曖昧な業務や、入力項目がないか
オペレーションがムダなく整理できれば業務効率は向上し、オペレーターはより多くの入電に応対ができるためASAが向上します。
ASAを改善させるために重要なこと
センター管理者として改善策を検討・実行する場合、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。ここからはASA改善のために重要なポイントを3つ解説します。
悪化の原因を突き止める
ただ闇雲に改善策を実行しても、改善までに時間がかかったり、応対品質が低下したりと十分な成果を挙げられない可能性があります。まずはどのような原因でASAが悪化しているのかを特定し、ピンポイントで改善策を検討・実行することが重要です。
原因の特定にはSLや応答率、AHT・ACWなどさまざまなKPI指標を組み合わせて分析し、正しくセンターの現状を把握できるようにしましょう。
オペレーターに無理なノルマを押し付けない
ASAを改善したいばかりにオペレーターへ改善策を強要するのは禁物です。
根本的な対策をおざなりにオペレーターへ改善の責任を押し付けてしまっては、オペレーターのストレス増加・やる気の低下に繋がります。またATT(平均通話時間)を短縮するために早口になったり、説明を省略してしまうこともあります。
オペレーターに何か作業や改善策を依頼するのであれば、丁寧に背景や対策内容を説明し協力を得ることが重要です。センター管理者はオペレーターが心身共に健康で、モチベーション高く業務にあたれるよう十分な配慮が求められています。
CS(顧客満足度)とのバランスを考える
ASAを改善できれば電話は繋がりやすくCS(顧客満足度)は向上します。しかし、繋がりやすさばかりを重視して顧客応対が疎かになってしまえば、逆にCSが下がってしまうこともあるでしょう。
改善策の検討する際は、ASAとCSが両立できるように双方をバランスよく考えることが大切です。
まとめ
コールセンターの品質管理に不可欠な指標である「ASA」を解説しました。コールセンター管理者は各種KPI指標を用いて生産性・品質を適切に管理することが求められています。
ただし、ASAなどの数字だけを追いかけて顧客満足度やオペレーターへの業務負荷を蔑ろにするのは本末転倒です。自社センターに足りないものは何か、どうすれば改善できるのかを正しく押さえ、改善策を検討するようにしましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。