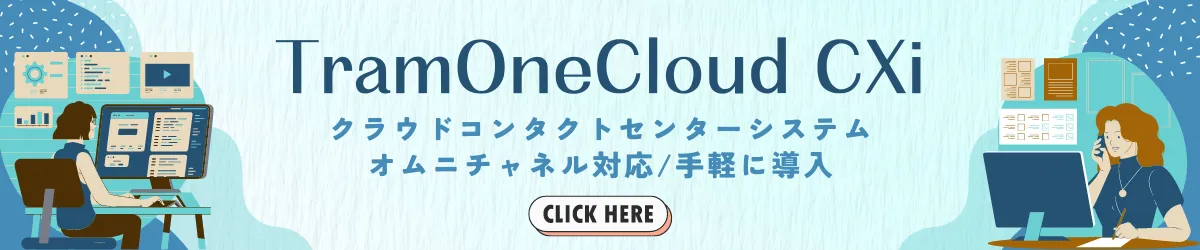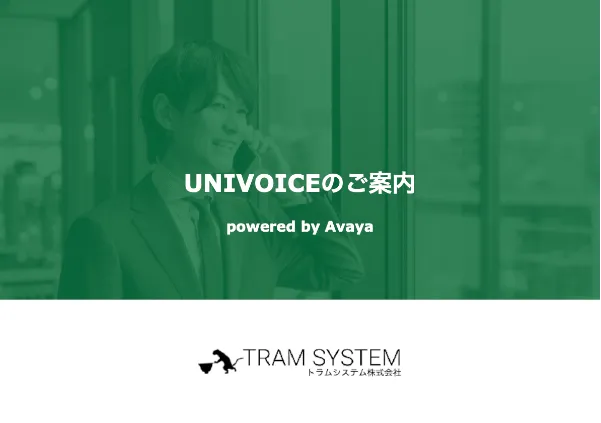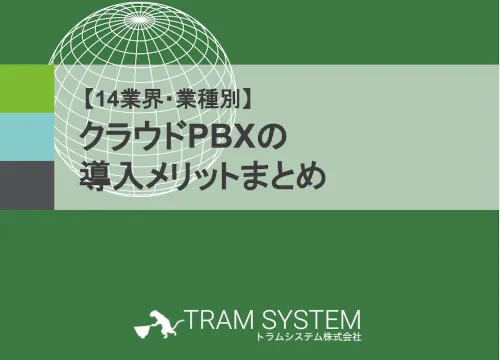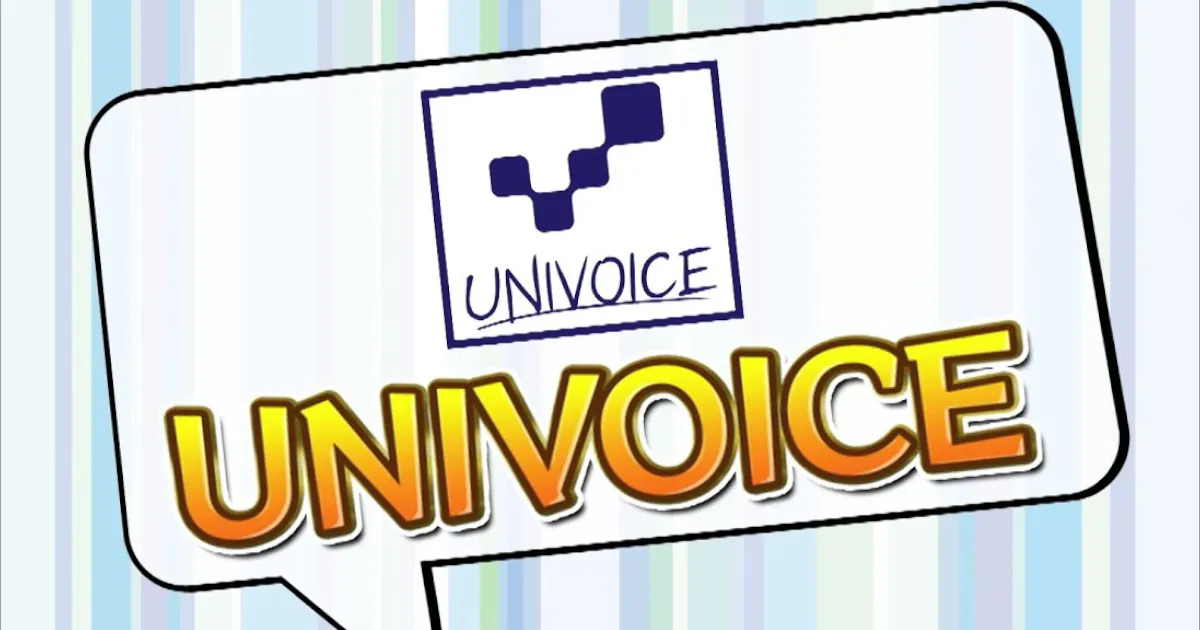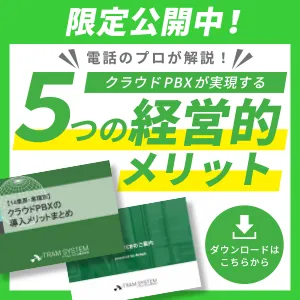コールセンターの評価基準「NPS」とは丨重要性・分析手法を解説|トラムシステム
自社製品やサービスをお客様が満足して利用してくれているのかを評価する指標が「NPS」です。
従来の顧客満足度に代わる評価基準として近年注目を集めています。顧客対応窓口の一つであるコールセンターやコンタクトセンターにおいても、NPSを活用した応対品質の評価・改善は有効です。
この記事では、センター管理者が知っておきたいNPSの基礎知識・活用方法を詳しく解説します。

目次
NPSとは
NPSとはNet Promoter Score(ネットプロモータースコア)の略で、顧客ロイヤリティを測るための指標です。顧客ロイヤリティは自社の商品サービスにどれくらい愛着・信頼感を持っているかを示し、顧客ロイヤリティの高い顧客は以下のような特徴があります。
・商品を再び購入してくれる
・長期間にわたって利用してくれる
・好意的な口コミを広げ、間接的に新規顧客を獲得してくれる
・単なるクレームではなく建設的なフィードバックをしてくれる
NPSは「この商品・サービスを友人や同僚にどの程度勧めたいですか?」というアンケートに回答してもらうだけで顧客ロイヤリティを可視化できます。シンプルさや簡単さがNPSの特徴です。
また、米国のコンサルティング企業であるベイン・アンド・カンパニーは、NPSの高い企業は競合他社の2倍以上の成長率を上げている、という調査結果を報告しています。NPSと事業業績・成長率の間に高い相関関係がある点も、NPSが注目を集める特徴の1つです。
顧客満足度(C-SAT)との違い
顧客満足度は、従来お客様が自社商品サービスに満足しているかどうかを知るために利用する指標です。コールセンターの満足度を調査する場合は、応対終了後にメールやSMSなどで「応対内容は満足出来たか?」といったアンケートを送付して測定します。
NPSと顧客満足度の大きな違いは、以下のような調査ポイントの違いです。
・顧客満足度:直接的な満足度を調査
・NPS:推奨度を聞き、潜在的な満足度を調査
様々な調査結果から「満足度」が高くても、商品のリピート購入や高価格帯商品の購入などには繋がらず、満足度と売上の相関は低いことが分かってきています。そのため、近年はより事業成長や業績と関係の深い「NPS」が顧客満足度に代わって用いられています。
NPS(顧客ロイヤリティ)を高めるメリット
新規顧客獲得には既存顧客維持の4~10倍以上ものコストがかかるため、企業にとっては既存顧客を大切にするマーケティング戦略は欠かせません。そして、既存顧客は顧客ロイヤリティが高いほど売上アップに繋がります。
ここからはNPSや顧客ロイヤリティを高めることで、どのようなメリットがあるのかを具体的に解説します。
口コミによるサービス・商品の拡散
良い商品やサービスを使った後は、周りの友人や家族に話してみたくなることはありませんか?同じようにSNSや口コミサイトで商品サービスのレビューやコメントを投稿することで自然に商品・サービスの良さを拡散させることが可能です。
口コミは「第三者からの評価」として、心理学的にも商品サービスに対する信頼性・信憑性が増す効果があります。顧客ロイヤリティの高い人ほど、好意的なレビューをする傾向にあり、企業にとってはお金を掛けずに新規顧客獲得に繋げられる点がメリットです。
顧客単価の上昇
顧客ロイヤリティが高いほど顧客単価が上昇する傾向があります。具体的に顧客単価が上昇するのは以下の2パターンです。
・より高価な上位商品を購入してくれる(アップセル)
・購入商品と関連性の高い商品とセットで購入してくれる(クロスセル)
企業への信頼や愛着があると、キャンペーンなどをきっかけに「いつもと違う商品を使ってみようかな」という気持ちが働きます。ついで買いや高価格ラインへの誘導で1回の支払額が増え、結果として顧客単価も高くなるという仕組みです。
解約率の低下
商品サービスの「ファン」となってくれれば、解約率や他社への乗り換えのリスクが低下します。例え他社が魅力的な商品サービスを発売したり、お得なキャンペーンを打ったとしても簡単に他社に切り替えることはないでしょう。
解約率低下のメリットは定額サービスや月額会員などの「サブスクリプション型サービス」で有効です。解約せずにユーザであり続ける限り、安定した収益が得られます。
リピーターの獲得
解約率低下と同じ理由で、自社サービスに信頼感や愛着を感じている顧客は継続的な利用や、リピート購入が増える傾向があります。市場が成熟し各企業の製品機能や品質が似通っている場合には特に効果的です。
差別化が困難な商品サービスにおいて、顧客はちょっとした変化やきっかけで乗り換えてしまう可能性があります。このような市場でリピート購入・継続利用を引き出しユーザを繋ぎとめられるのも、顧客ロイヤリティのメリットです。
NPSの分析方法
実際にNPSを算出した後、どのように活用すれば良いのでしょうか?ここからはNPSを定性的・定量的の2観点から分析する方法を紹介します。
NPSは測定して終わりではなく改善に繋げてこそ意味のある指標なので、ぜひ参考にしてください。
定性的分析
定性的分析とは数字で表せない事柄や、内面的、抽象的な性質特徴を把握するための分析方法です。NPSでは調査の際にフリーコメントを一緒に収集することで、顧客が評価に至った理由や思いを汲み取ります。
ただし、定量的分析と比較すると曖昧さが残る分析方法であり、人によって受け取り方にブレがある点に注意しましょう。なお、定性的分析はテキストマイニングツールなどを利用して分析すると効率的に分析を進められます。
定量的分析
定量的分析とは状況、状態を数字で表す分析方法です。定量化・数値化することで客観的に分かりやすく、結果は誰が見ても同じように認識できるというメリットがあります。
NPS分析で定量的分析の手法を適用するのであれば、「友人・同僚に商品をおすすめしたいか」という質問の他に、様々な切り口で満足度を聞きましょう。具体的には調査票に以下のような切り口で満足度調査を実施します。
・ブランドイメージが良い
・商品・サービスが魅力的な機能を備えている
・コストパフォーマンスが良い
・自分に合った商品を提案してくれる
・商品申込・購入までの手続きが簡単
・アフターフォローが充実している
・コールセンターなどカスタマーサポートが充実している
NPSと各要素の相関関係を分析することで、どの要素を重視すれば顧客満足に繋がるのかを知ることができます。
日本のNPSはマイナス平均になりやすい
日本においてもNPSを利活用する企業は年々増加していますが、実際にNPSを測定してみると実感よりも低めに結果が出ることがあります。
これは、日本人の気質に起因するものです。実際にNPS関連のソフトウェアを販売するサイメトリックス社によって「日本は他国に比べて満足度やロイヤルティの点数を低く付ける傾向がある」と報告されています。
ここからはNPS活用する企業や担当者が知っておきたい日本人ならではの特徴や、国民性を踏まえた活用方法を解説します。
原因は日本人特有の文化?
日本でNPSがマイナス平均になりやすいのは、「回答中心化傾向」が根底にあるといわれています。
回答中心化傾向とは心理的偏向の一つで、各種評価やアンケートなどにおいて評価結果が中央付近に集中することです。NPSの場合は11段階で推奨度を調査しますが、中央値である「6」を付けることが多くなります。
日本人は古くから周りと足並みを揃えること、波風を立てないことを良しとしてきました。
周囲との協調を重んじる文化を背景に、日本人は諸外国と比較すると極端な回答を避け、当たり障りのない評価を付ける傾向があるようです。
NPSは推移で見る
NPSの数値が良くなかったからといって安易に落胆する必要はなく「日本人の気質によるもの」と受け止めることが大切です。NPSは結果の絶対値を判断するのではなく、定期的にNPS調査を実施し過去の評価結果との変化を分析するのが良いでしょう。
分析した結果を元に改善策を実行し、顧客ロイヤリティがどう変化するのかを繰り返し測定することがNPS活用の鍵です。
また、競合他社との比較に利用することで、相対的に自社商品サービスの状態を把握することもできます。
まとめ
顧客ロイヤリティを測定する指標であるNPSは、上手く分析・活用することで業績アップや事業成長に繋がる重要なマーケティング指標です。NPSを継続的に測定・分析することで得られた結果を元に、コールセンターの業務改善に繋げていきましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。