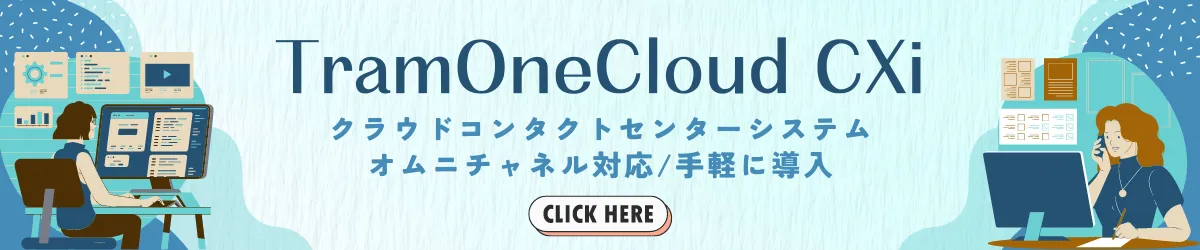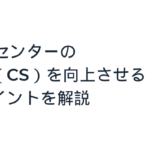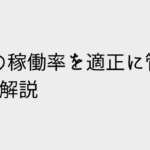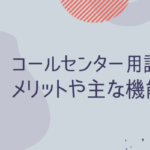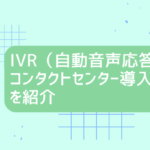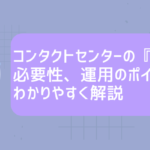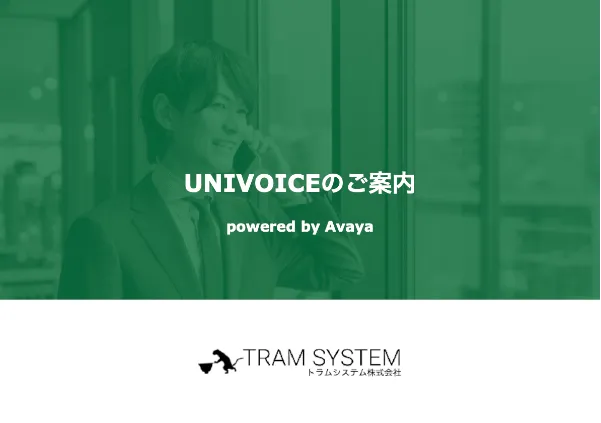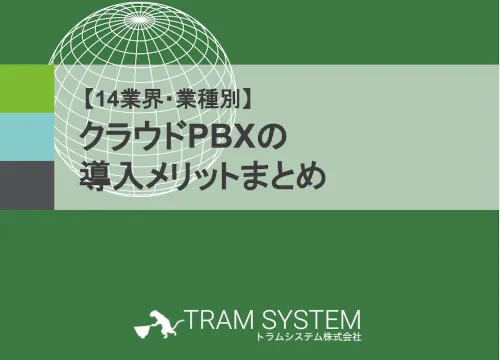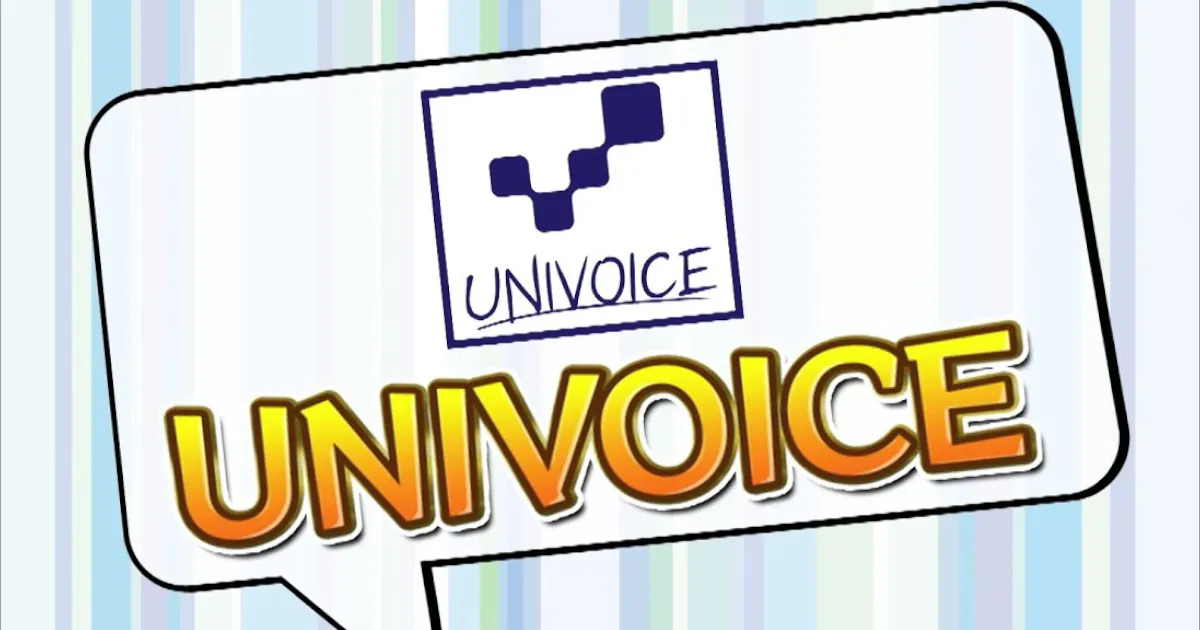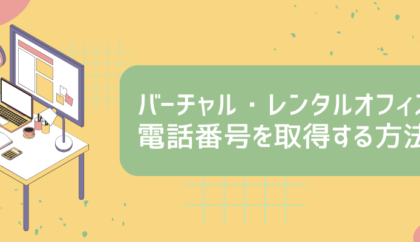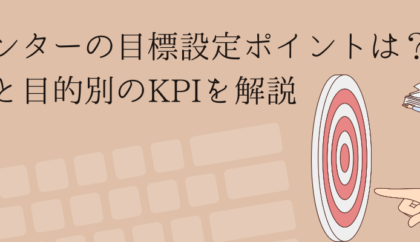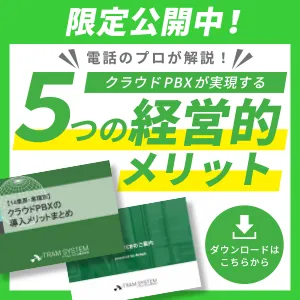コールセンターマネジメントとは?SVの重要性と管理ポイントを解説|トラムシステム
コンタクトセンター・コールセンターの運用に関し、センターの応対品質向上やオペレーターの勤務管理、業務効率化などの悩みを抱えているマネージャーは多いでしょう。この記事では、コールセンター・コンタクトセンターの安定稼働と業務改善をテーマに、マネジメントのポイントとSV(スーパーバイザー)の重要性について解説します。
コンタクトセンター・コールセンターの適正な運用にお役立てください。
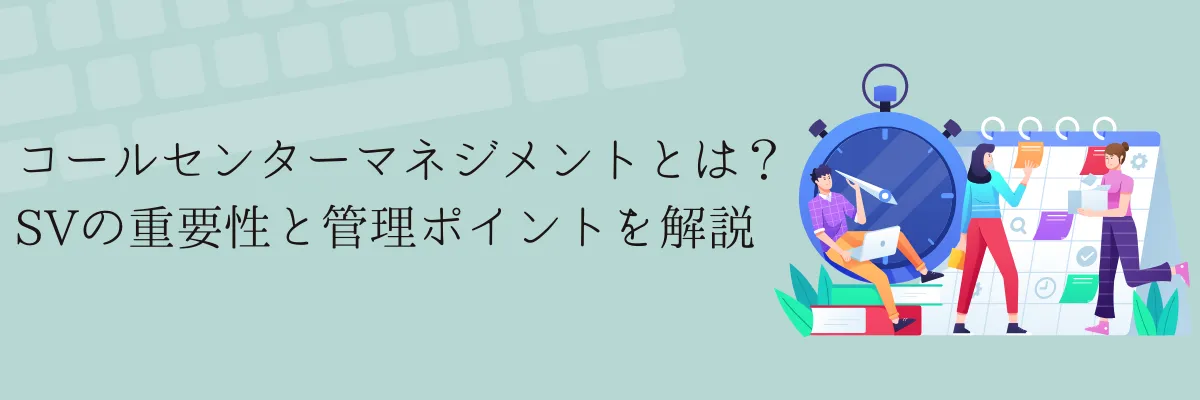
目次
コールセンターマネジメントとは?
コールセンターマネジメントとは、センターの稼働率や応答率、満足度などの現状や将来の目標をふまえ、より効率的・効果的なセンター運営のための環境を整備することを指します。
センターの業務効率を最大化するためには、ヒト(オペレーター)、モノ(設備・システムツール)、カネ(予算・費用)の適切な管理が欠かせません。悪質なマネジメントは顧客応対品質や満足度の低下、クレームの増加に直結する大きな課題です。
マネジメントをするにあたり、重要な存在がSV(スーパーバイザー)です。
SV(スーパーバイザー)の存在がマネジメントの要
コールセンターマネジメントには、SV(スーパーバイザー:Supervisor)とよばれる業務管理監督者の働きが肝心です。SVの業務内容は多岐に渡り、主に以下のような業務を担当します。
・オペレーターの育成、管理
・モニタリング、指導
・二次対応(クレーム処理など)や特別対応(難易度の高い業務やVIP対応など)
・業務改善の取り組み
オペレーターに一番近い管理者として現場をまとめ、課題解決を推進することが求められるため、コールセンターの中で最もハードな職業といわれることもあります。多くのオペレーターを束ねるリーダーシップや、コミュニケーション能力はもちろん、分析力や判断力など総合的な能力が必要です。
センター運営の要となるSVは簡単に調達できる人員ではありません。マネージャーは、SVのスキルアップや支援を惜しまず、中長期的に育成していく意識が大切です。
SVの業務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
コールセンターマネジメントのポイント
コンタクトセンター・コールセンターのマネジメントは、以下4点がポイントです。どれも当たり前の事柄ですが、改めて見返してみると意外に出来ていないことも多く存在します。1つずつ順に解説しますので、センター運営のどこに改善点があるのかを確認してみましょう。
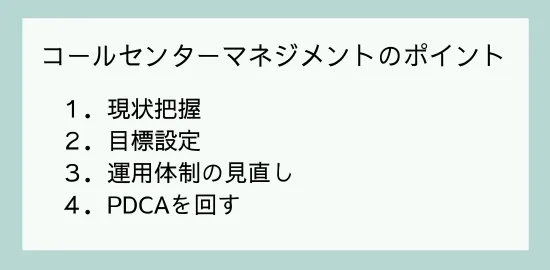
1.現状把握
現状把握とは、センター内の現状を正確に押さえることです。具体的には以下のような情報を収集し分析します。
・稼働率
・占有率
・応答率
・処理時間
・一次回答率
さまざまな標準指標を用いてコールセンターのパフォーマンスを正確に計測し、現状の問題・課題を把握することが重要です。
2.目標設定
現状把握で使用したKPI指標は、正しく分析・評価してこそ価値のあるデータです。過去のトレンドを考慮して各KPIの目標値を設定し、定期的に計測値と目標値との乖離状況を確認しましょう。目標と大きく乖離している場合は、何が課題なのか、何がボトルネックなのかを分析し改善策を策定します。
目標は一度設定して「おしまい」にするのではなく、センターの現状に合わせて都度見直しをすることが大切です。業務改善やコスト削減、顧客満足度向上などのゴールを設定することで、センター内モチベーションの維持・向上につながります。
なお、目標値・ゴールは具体的な数値で明確に示すことが重要です。例えば占有率であれば「日次の平均占有率が○○%~××%で合格ライン」といった具合に、誰が見ても目標の達成状況が分かるようにすることを意識しましょう。
3.運用体制の見直し
マネージャーの最大のミッションは、センターのパフォーマンスを最大化することにあります。そのためには現状把握・目標設定で使用した各種KPI指標を分析し、常にセンター運用体制に問題点がないかどうか目を光らせることが重要です。
例えば稼働率が目標値を外れてしまった場合、以下のような対策が考えられます。
・オペレーターの増減員
・研修制度やフォロー体制の充実
・各種システム、ツールの導入
マネージャーは稼働率だけに注目するのでなく、応答率や占有率など関連指標を組み合わせて問題点を分析し、最適な対策案を確実に実行しましょう。
4.PDCAを回す
センターを取り巻く状況は逐次変化するものであり、運営方法に「絶対解」はありません。どのような時も慌てず臨機応変にセンター運営を行うためには、日ごろから継続的に改善に取り組む姿勢が大切です。そのためにはPDCAの考え方を意識しましょう。
PDCAとは、以下4つの要素の頭文字をとったビジネス用語です。
・Plan(計画)
・Do(実行)
・Check(評価)
・Action(改善)
課題に対する解決策を計画実行し、効果を測定分析し改善策につなげる一連のサイクルを継続に回すことで、組織内の業務改善やコスト削減を実現します。
センター運営で発生するさまざまな課題に対して、それぞれにPDCAサイクルを継続的に実施しましょう。そうすることで、最終的にはセンター全体の業務改善や品質向上などの大きな目標を達成することが可能です。
コンタクトセンター・コールセンター運用に重要な4つのKPI(指標)
現状把握のところでも少し紹介しましたが、コールセンター運用で役立つ4つの指標を具体的に解説します。どれもセンター運営に欠かせないKPI指標です。適切に収集・分析できるように、指標値の意味や見方を再確認しましょう。
応答率
応答率とは、「電話のつながりやすさ」を表す指標です。入電した件数のうち、オペレーターが実際に何件対応出来たのかを計測します。応答率が高い場合は、オペレーターの顧客対応件数が多く電話がつながりやすい、と判断できます。逆に応答率が低い場合は、電話がつながりにくく、顧客が途中で諦めて電話を切っているため、顧客満足度は低い状態といえるでしょう。
応答率は盗難・事故受け付けなど緊急性の高い業務の場合は97%以上、それ以外の場合は90%以上が一般的な指標値です。サービスレベル(基準内応答率、あらかじめ定義した応答時間内に応答できた件数の割合)と組み合わせて応答率を分析し、応答率が指標値を下回る場合はオペレーターの増員やシフトの組み換えを検討しましょう。
平均処理時間
平均処理時間(AHT)とは、1通話あたりの平均対応時間を指します。計算方法は、以下のいずれかで算出します。
・(総通話時間+総保留時間)÷総対応件数
・平均通話時間+平均保留時間
コールセンターの対応業務や、扱っているサービス・商品特性、オペレーターのスキルなどによって平均処理時間は変化するため、統一基準はありません。より短い時間で対応できていれば、その分多くの件数に対応できるので、センター全体として良い状態だと判断できます。自センター内の過去実績などを参考に目標値を設定しましょう。
ただし、平均処理時間だけを重視して目標値を設定してしまうと、オペレーターが早口で対応をしたり、説明を省略したりと、顧客対応品質に影響が出る可能性もあります。定期的な通話モニタリングやアンケート調査といった顧客満足度(CS)を維持・チェックする対策と組み合わせることが重要です。
一次解決率
一次解決率とは、最初の入電で顧客対応が完結した件数の割合です。コールバックや専門部署への転送などの二次対応が必要になる場合は一次解決とはなりません。
一次解決率の低さは、質問に対して明確な解答が得られない、違う担当者に何度も同じことを説明しなければならないなど、顧客満足度を著しく低下させる原因の一つです。解決率を高めるためには、想定質問に対するトークスクリプトを充実させる、研修やトレーニングにてオペレーターのスキルアップさせるなどの方法があります。
なお、一次解決率はシステム的に集計することが難しい指標です。何件かサンプルでピックアップし一次解決率を集計するのが一般的で、顧客対応の経緯を追いながら件数を算出します。
稼働率
稼働率は、勤務時間の中で顧客対応にかけられた時間の割合です。以下の計算式で算出します。
稼働率=顧客対応時間÷勤務時間
顧客対応時間とは、次のような顧客応対に直接関連する時間を合計した時間を指します。
・顧客との通話、メール、チャット応対時間
・保留時間
・後処理時間
・待機時間
日本のコールセンターにおける一般的な稼働率目標は80~85%とされていることが多く、目標値と比較し高すぎても、低すぎても何らかの課題があると判断します。
・高すぎる場合:業務量に対してオペレーター人数が不足している状態
・低すぎる場合:オペレーターが多すぎるか正しく勤怠管理ができていない状態
稼働率はオペレーターのスキルはもちろん、季節、月末月初・曜日などのトレンドによって稼働率は変化します。管理ツールやシステムを使って稼働率を定期的にチェックし、大きく目標値から外れるようであれば何らかの対策を検討することが大切です。
ケース別おすすめシステム機能
顧客対応の効率化や顧客データの活用分析といったセンター運営を強力にサポートするITツールが年々登場しています。センター管理者は積極的にこれらのITツールを導入し、センター運営を効果的に活用することが肝心です。
ここからは、コンタクトセンター・コールセンターのマネジメントを最適化するためのおすすめITツールを紹介します。目的に応じた必要機能を紹介するので、センター運営に悩むマネージャーの方は、ぜひ参考にしてみてください。
業務を効率化したいなら「ACD」「IVR」
最低限のオペレーター数で多くの顧客対応を行うためのシステムとしては、ACD(Automatic Call Distribution:着信呼均等分配)や、IVR(Interactive Voice Response:自動音声応答)があげられます。
ACDは、顧客からの入電をオペレーターの負荷状況やスキルをみながら振り分けるシステムのことです。稼働率や処理時間の改善はもちろん、一次解決率の向上も期待出来ます。
IVRは、自動音声により顧客の問い合わせ事由を元に入電を振り分けるための仕組みです。IVRでコールリーズンを明確化するだけでなく、IVRにて顧客情報の収集・本人確認などもできるので、ACDと同じく各KPI指標値の改善に大きく貢献します。
顧客情報の有効活用なら 「CRM」
顧客管理システム(CRM)とコールセンターのシステムを結合することで、顧客情報の有効活用が可能です。例えば、入電時の情報を元に過去の購入履歴や問い合わせ履歴を参照できれば、スムーズな顧客対応が可能です。通話音声を音声データやテキスト情報として残すことで、後から対応履歴をモニタリングすることもできます。
顧客からの問い合わせ内容やご意見を営業企画部門や経営層へ適切にフィードバックすることで、商品・サービスの改善に役立てることもできるでしょう。
応対品質を向上させるなら「モニタリング」
応対品質を向上させるためには「通話モニタリング」機能を活用します。応対品質とは各オペレーターの電話応対レベルのことで、具体的には以下のようなポイントで評価します。
・顧客のニーズに応えられているか
・丁寧な言葉遣いで対応出来ているか
・正確な情報を提供できているかどうか
・顧客の課題に共感出来ているかどうか
・顧客満足度はどうだったか
複合的な要素を含む指標なので、応答品質を機械的に算出することはできません。定期的に通話モニタリングを実施しながら応対品質を確認し、評価結果は各オペレーターにフィードバックすることで応対品質のさらなる改善を目指しましょう。
コールセンターシステムでは、発信数・成約数・通話時間などのコール情報が蓄積されています。具体的な数値データを使って集計分析することで、効率的に課題を洗い出すことができます。
まとめ
コンタクトセンター・コールセンターのマネジメトントは一度実施して終わりではなく、継続的に実施していくことが重要です。この記事内で取り上げた「稼働率」や「応答率」などのKPI指標を組み合わせつつ、センターの現状を正しく把握し最適な改善策を立案・遂行することが、マネージャーに求められています。
また、システムやSVの力をうまく活用することは、センター全体の生産性向上に有効な対策です。ぜひ積極的に実践してみてください。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。