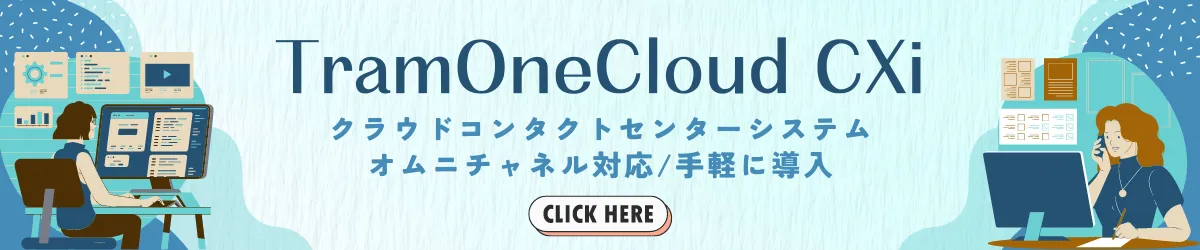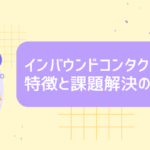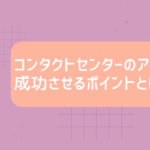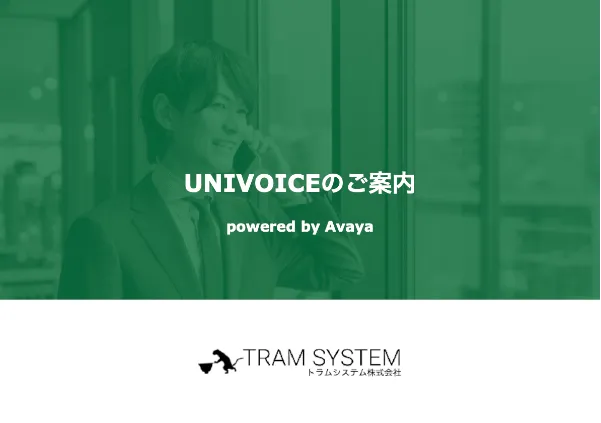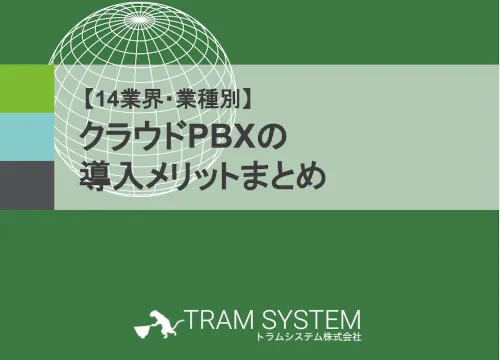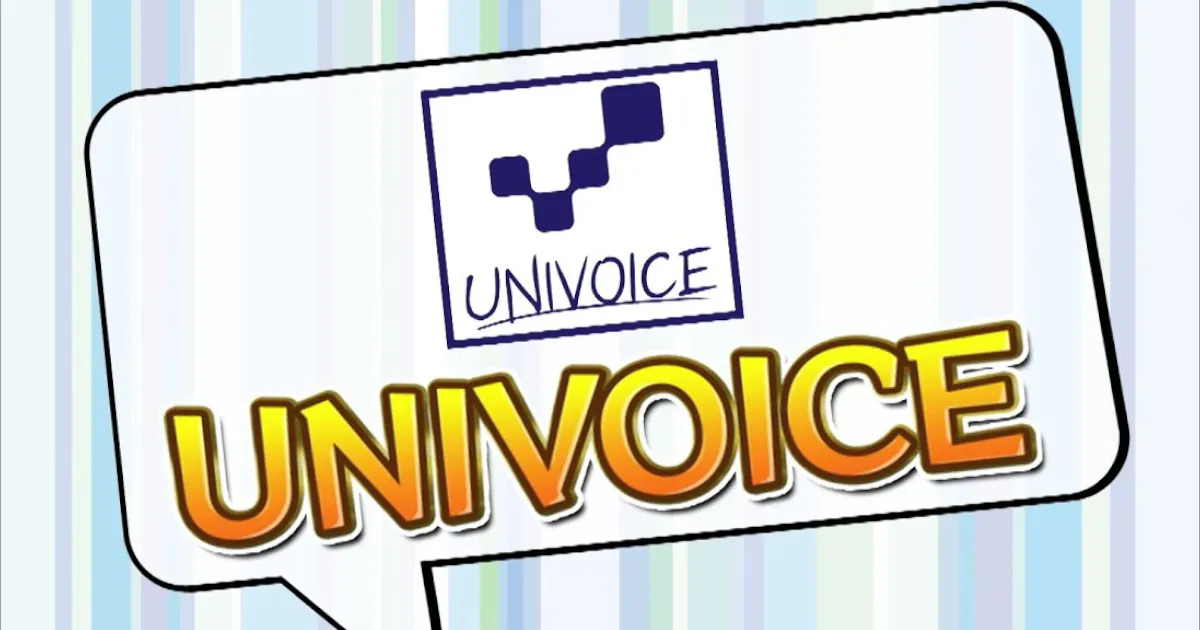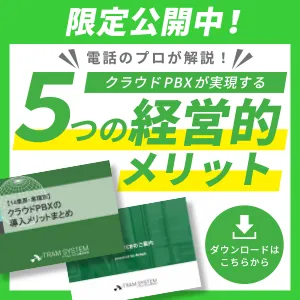BPOコールセンターで生産性向上!委託できる業務やメリット・デメリットを解説|トラムシステム
顧客と企業を繋ぐチャネルとして重要なコールセンター・コンタクトセンター。しかし、慢性的な人員不足や、オペレーター育成ができない等、なかなか理想的な体制を実現できないコールセンターも多いのではないでしょうか。そのようなお悩みを抱えた企業にご紹介したいのが、BPOコールセンターです。BPOコールセンターを活用することで、課題解決の近道になるかもしれません。
そこで本記事では、BPOコールセンターのメリット・デメリットや、委託できる業務について解説していきます。
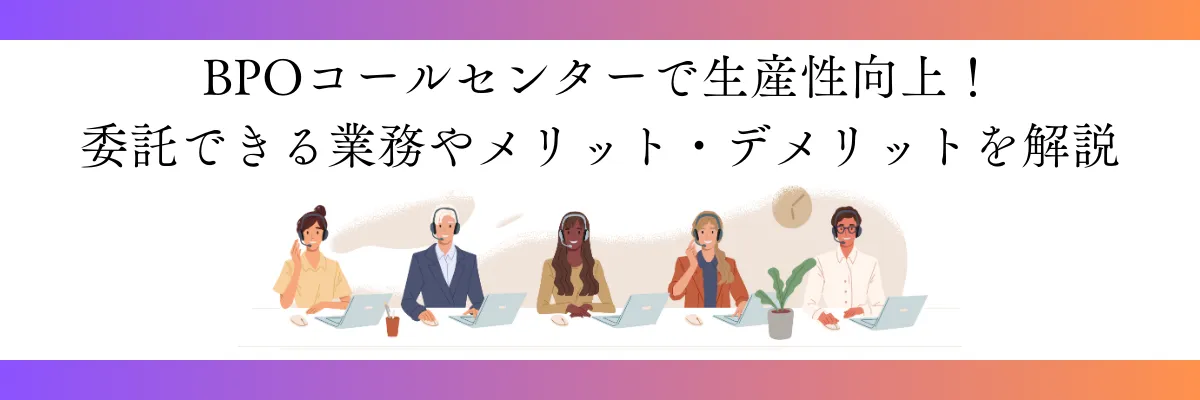
目次
BPOコールセンターとは
BPO(Business Process Outsourcing)、特定の業務を外部に委託することを意味します。BPOコールセンターは、電話応対にかかわる業務プロセスを丸ごと外部委託することを指します
似たような言葉としてアウトソーシングが存在します。一部業務のみを委託するアウトソーシングとは違い、一連の業務プロセスを一括して委託するのがBPOであるという解釈が行われています。
BPOコールセンターで対応できる業務
BPOコールセンターに委託できる業務は、電話応対だけではありません。コールセンター業務における下記のような業務を委託することができます。
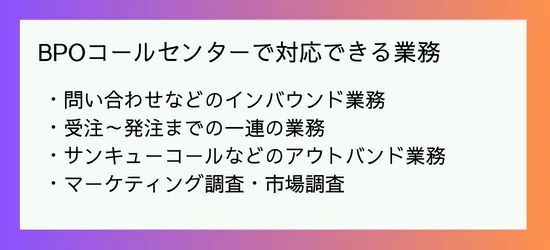
問い合わせなどのインバウンド業務
電話やメール、チャットを含めた、顧客からの問い合わせ対応などのインバウンド業務です。
問い合わせ内容がある程度絞られる場合は、マニュアルやFAQをあらかじめ準備しておくことで、スムーズに対応を移行することができます。
受注~発注までの一連の業務
受注から発注までの業務を委託することができます。
電話で注文を受ける場合は、受注のみならず発注までオペレーターが行います。1件ごとに処理をしないといけないため、手間と時間がかかります。この一連業務をBPOコールセンターに委託することで、社員の業務負担を軽減でき、生産性の向上が実現できます。
サンキューコールなどのアウトバンド業務
商品購入後のサンキューコールや、新規顧客獲得のテレアポのアウトバンド業務です。特にテレアポは人員と時間を必要とする業務です。BPOコールセンターでは、その点を穴埋めしてくれるので、営業機会を逃しません。
マーケティング調査・市場調査
マーケティング調査や市場調査は、集客や新規事業において重要な業務ですが、知識やスキルが必要です。BPOコールセンターにはスキルのある専門のスタッフが在籍しているので、自社にノウハウがなくてもマーケティング調査や市場調査を行うことができます。
BPOコールセンターのメリット
BPOコールセンターを取り入れることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットを3つご紹介します。
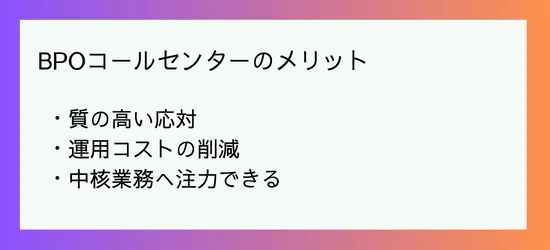
質の高い応対
自社のコールセンターでは、オペレーターの育成に時間がかかります。BPOコールセンターでは経験とスキルのあるオペレーターが応対にあたるため、質の高い顧客応対を提供できます。
また、休日や時間外にも応対ができるため、顧客満足度向上に繋がります。
運用コストの削減
コールセンターの運用には、人件費やコールセンターシステムの構築など、費用や時間がかかります。BPOコールセンターに委託することで、費用や準備期間を抑えることができます。
繁忙期のみ委託することもできるので、自社のコールセンターの規模はそのままで、一時的に応対量を増やすこともできます。
中核業務へ注力できる
電話に係わる一連の業務を委託することで、社員に専念させたい中核業務に注力させることができ、生産性向上が見込めます。
BPOコールセンターへテレアポを委託し、社員はアポの対応や受注業務に専念したり、マーケティング調査を委託し、上がってきた調査結果を纏めて商品開発に活かしたり、企業戦略や事業展開など、専門的な業務にリソースを割けるようになります。
BPOコールセンターのデメリット
企業にとってメリットの多いBPOコールセンターですが、注意すべき点もあります。
情報漏洩のリスク
社外のスタッフが顧客情報や企業の機密情報に触れることになるため、セキュリティ対策をしっかり講じているか慎重に見極める必要があります。情報漏洩は企業の信用を大きく損ないます。もし、万が一情報が流出してしまった時の対応も事前に検討しておきましょう。
ノウハウが蓄積できない
業務を一括して委託してしまうため、自社にノウハウや経験が蓄積されません。
BPOコールセンターから内製コールセンターへ移行をする場合は、人材育成を1から進めなければならず、時間とコストがかかります。その際は、BPOコールセンターからのレポートを通じて応対内容を把握し、マニュアルを整備してオペレーターの教育をしていきましょう。
委託先の比較ポイントとは
BPOコールセンターのを依頼する委託先の比較ポイントを解説します。数ある企業、サービスの中から自社に最適なものを選定し、成功に導きましょう。
コスト
料金が安い委託先を選択しがちですが、コストが低い代わりにサービスの質が不十分なケースもあるので注意しましょう。複数の委託先から見積もりを取り、自社で求められる要件とコストのバランスを意識する必要があります。
セキュリティ体制
不正アクセスやサイバー攻撃で機密情報、個人情報が漏洩すると、企業の社会的信用が失墜してしまいます。そのような事態を防ぐため、委託先のセキュリティ体制はきちんと確認することはもちろん、担当するオペレーターのセキュリティ意識もチェックしましょう。
対応品質
オペレーターの対応品質は、委託先を選ぶうえで重要なポイントです。顧客満足度に関わってくるのはもちろん、アウトバンド業務では販売ルートや業績の向上につながります。対応品質を観察し、業務を任せる実力があるかチェックしましょう。
突発的な要件への対応速度・柔軟性
表向きは優れていても、突発的な要件への対応速度、柔軟性が不足していると、コールセンターの運用に支障が出ます。繁忙期にはオペレーターの人数を増やす、キャンペーン期間中は対応する曜日や時間帯を増やす、などの対応が可能かどうか確認しておきましょう。
多様なチャネルでの対応
近年のコールセンターは、電話、メール、チャット、SNSといった様々なチャネルでユーザーとやり取りしています。電話だけでなく、様々なチャネルに対応したセンターは、顧客との総合的な接点(コンタクト)を担う部署としてコンタクトセンターと呼ばれています。
コンタクトセンターにおいては、様々なチャネルから来た情報に対応できる仕組みが必須です。情報を円滑に共有できるシステムを備えているかどうか確認してみましょう。
導入実績
導入実績も欠かさず確認しておきましょう。自社と規模や業種が共通している企業での実績が豊富なら、安心して任せられます。取引がある企業のインタビュー記事をホームページに実績として掲載している場合もあるので、それらの情報を見てみるのもよいでしょう。
まとめ
今回は、コールセンター業界で近年広がっているBPOについて解説しました。BPOの最大の目的は、組織のスリム化と生産性の向上です。そのためにはまず、現状の課題を発見することが重要となります。定型的な業務はBPO化し業務を削減することで、社員をより専門性の高い業務に注力できる体制を目指しましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。