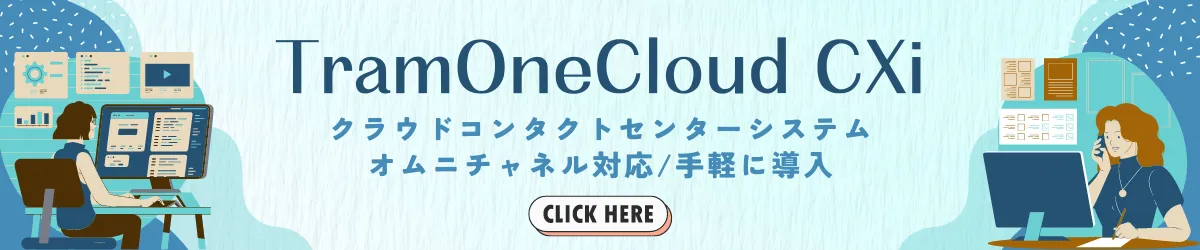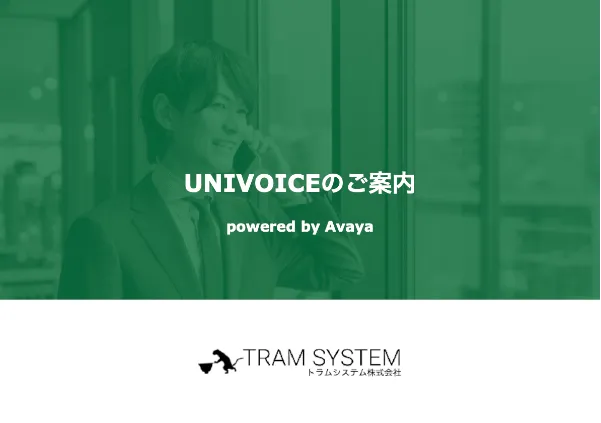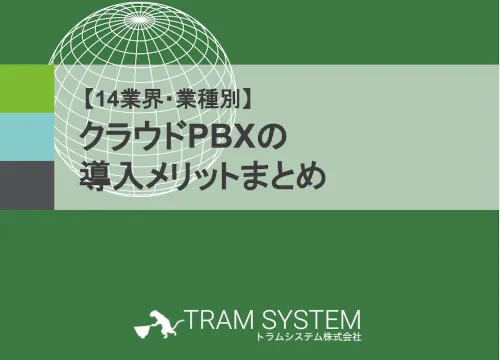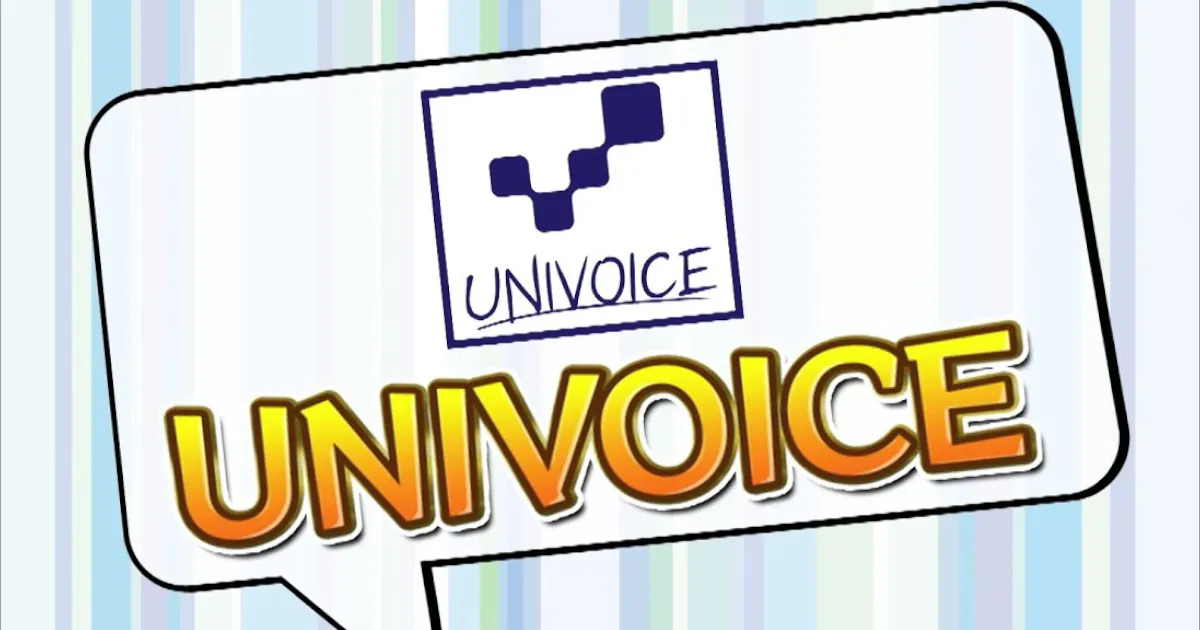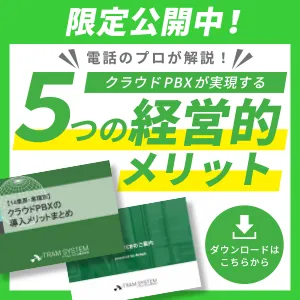コールセンターの外注のメリット・デメリット丨費用や注意点も解説|トラムシステム
業務の効率化やよりよいサービスの提供などを目的として、コールセンターやコンタクトセンターの業務を外注する企業が増えています。外注サービス事業者は、スキルや経験を持つオペレーターを確保し、問い合わせ対応や注文受付、営業活動や市場調査などの幅広いサービスを提供し、企業のニーズに答えています。
しかし、外注の検討にあたって、具体的にどのような業務を外注できるのか、メリット・デメリットは何かなど、気になる担当者の方もいるでしょう。この記事では、コールセンターの外注について、メリットやデメリット、かかる費用、委託時に気をつけるべき点などを解説します。

目次
コールセンターの外注とは
コールセンター(コンタクトセンター)の外注とは、コールセンター業務の全体または一部を、顧客とのコミュニケーションを専門的に行う業者などに委託することです。外注先は、電話やメール、チャットなどの媒体を通じて、顧客からの問い合わせや要望に対応したり、営業活動やアフターサービスを行ったりします。
外注によって、企業はコールセンター業務の品質向上や効率化、コスト削減などを目指すことができます。
外注できる業務
コールセンターの業務は、顧客からの問い合わせや要求に対応するインバウンド業務と、顧客に対して電話をかけ、営業活動や市場調査などを行うアウトバウンド業務があります。
それぞれどのような業務を外注できるのかを解説します。
インバウンド業務
インバウンド業務については、以下のような業務を外注することが可能です。
・問い合わせ対応:顧客からの製品やサービスに関する問い合わせや照会に対応する
・注文対応:顧客からの注文や購入手続きに関するサポートを提供する
・アフターサービス:購入した製品やサービスの保証や修理、返品・交換に関する問い合わせに対応する
アウトバウンド業務
アウトバウンド業務については、以下のような業務を外注することが可能です。
・マーケティング活動:新製品やキャンペーンの告知、アンケート調査など、マーケティング活動に関連する連絡を行う
・営業/販売促進活動:製品やサービスに興味を持ってもらい、最終的に購入してもらうことを目的として連絡を行う
・フォローアップ:顧客へのお礼の連絡など、継続的な関係構築を目的として連絡を行う
コールセンターを外注するメリット
顧客のニーズが多様化・複雑化し、高いレベルでのサービス提供が求められる現代において、よりよい顧客体験の提供を目的にコールセンターを外注する企業が増えています。
コールセンターの外注には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、主な3つのメリットについて解説していきます。
短期間・少ない投資で運用開始できる
通常、コールセンターの立ち上げには、目的の設定から業務フローや組織体系の決定、システムの選定と導入、業務スペースの確保、人材の採用と教育など、様々なプロセスを経る必要があります。
一方、コールセンターサービスを提供する事業者は、これらの業務遂行に必要な設備とノウハウ、人材をすでに備えているため、外注によって短期間かつ少ない投資で運用開始できます。
自社で人材を確保・育成する必要がない
オペレーターの顧客対応スキルは、コールセンター全体の品質に加え、企業やブランドのイメージや信頼にも関わる重要な要素です。
自社でコールセンターを立ち上げる場合、対応マニュアルの整備や人材の確保、教育などが必要ですが、外注であれば高いスキルを持つオペレーターが即時確保できます。
多くのコールセンターのサービス事業者は、様々なスキルや経験を持つスタッフを常時確保しているため、依頼企業の業務形態やサービスにあわせて適切なスタッフをアサインします。
さらに、求人募集や面接、新人教育、スキルアップ研修、面談などの人材管理にかかるコストを削減できる点も、外注のメリットの1つです。
より重要な業務に社内リソースを割り当てられる
コールセンターの外注は、コールセンターの立ち上げや運用にかかる時間や人的リソースの節約にもつながります。これにより、社内のリソースを営業活動や新製品・サービスの開発など、より重要な課題に割り当てることが可能です。
より重要な業務に集中できることは、企業にとってはもちろん、社員にとってもスキルや経験が身につく、仕事への満足度が上がるといったメリットがあります。
コールセンターを外注するデメリット
コールセンターの外注は、コスト削減やリソースの確保につながる一方で、顧客サービスの品質低下などにつながる可能性もあります。ここからは、コールセンターの外注によるデメリットを解説します。
自社にノウハウや経験を蓄積できない
コールセンター業務を社外のリソースで対応するため、社内で経験やノウハウが蓄積されない点は、外注による弊害と言えます。
日々顧客と直接やり取りを行うコールセンターでは、商品やサービス、企業に対する期待や要望、クレームなど様々な「声」が集まります。企業は、それらの声を集約、分析し、よりよい商品やサービス提供に活かすことが求められる一方で、外注ではそれが難しいのが現状です。
また、将来コールセンター業務を自社運用に切り替えたいと考えても、ノウハウや経験がなさが障壁となり、結果として引き続き外注に頼らざるを得なくなる可能性もあります。
情報共有に時間がかかる
社内のコミュニケーションネットワークから外れた外部のサービス事業者が業務を遂行する仕組み上、情報共有などに時間がかかる危険性があります。コールセンターの対応方針の変更や新しい商品やキャンペーンの案内などの業務連絡が遅れることで、状況やニーズの変化にスムーズに対応できないかもしれません。
また、同じようにサービス事業者から依頼元の企業への連絡にもタイムラグの発生が予想され、トラブルやクレームに関する報告をすぐに受け取れない可能性があります。
委託内容によってはコストが高い
コールセンターの外注にかかる費用は、依頼する業務の内容や対応時間、コールの件数、配置するオペレーターの数などによって決定されます。このため、契約内容によってはコストが高額になる点には注意が必要です。
料金形態やサービス内容は事業者によって異なるため、全体のコストが自社のビジネスや予算に見合うかどうかを確認しましょう。
コールセンターの外注にかかる費用
コールセンターの外注費用は、主に月額固定制と従量課金制のいずれかの料金形態で決定されます。ここからは、それぞれの特徴とメリットについて解説します。
月額固定制
月額固定制は、毎月一定の利用料を支払い、あらかじめ定められた範囲内でサービスを利用できる料金形態です。「1ヶ月あたり100件」といった事前に定められた対応件数に基づいて料金が設定されるため、予算の見積もりや経費管理が行いやすい点が特徴です。
一方で、実際の利用量と関係なく一定の金額を支払うため、閑散期などにはコストパフォーマンスが低下する可能性があります。また、予期せぬ出来事(メディアで商品やサービスが取り上げられて注目度が上がる、トラブルや不具合の発覚で問い合わせが増えるなど)の発生時には、追加料金が発生することもあります。
従量課金制
従量課金制は、着信数や発信数、対応時間などの実際の利用量に応じて料金を発生する料金形態です。成約につながった場合のみ料金が発生するケースもあります。
実際に使った分を支払うため、コストに無駄がなく、需要の変動に柔軟に対応できる点が特徴です。一方で、月額固定制よりも基本料金が高めに設定されていることが多い点や、コストの予測や管理が難しい点には注意が必要です。
インバウンドとアウトバウンドの料金の違い
コールセンターの外注にかかる費用は、具体的に依頼する業務内容とオペレーターに求められるスキルの違いから、インバウンド業務よりもアウトバウンド業務のほうが高額になる傾向があります。
インバウンド業務は、基本的に顧客からの問い合わせを待つ「受け身」の対応であるため、対応時間を決めやすく、着信数もある程度の予測が可能です。また、オペレーターには商品・サービスに関する最低限の知識が求められるものの、マニュアルをしっかりと整備すれば、新人オペレーターでも比較的容易に業務に慣れることができます。
一方、主体的に発信を行うアウトバウンド業務では、業務の内容や1日の達成目標などによっては、着信数の増加や時間の延長などが発生しやすいです。加えて、オペレーターには商品・サービスの販売やマーケティングに関する知識やトークスキルなど、インバウンド業務よりも高いスキルが求められます。
このように、アウトバウンド業務ではより多くの時間とコール数が発生することに加え、高度なスキルを持つ人材を確保しなければいけないため、料金が高くなることが多いのです。
コールセンター業務を外注する際のポイント
コールセンターの外注には様々なメリットがある一方で、そのメリットを最大限受けるためには、いくつか注意しておくべきこともあります。ここからは、コールセンター業務の外注する際の検討ポイントを解説しましょう。
業務内容
コールセンターの業務は、顧客の問い合わせ対応、注文受付、技術サポート、アポイントメント設定、調査・リサーチなど幅広くあります。その中のどのような業務を外注するのかを、明確に定めましょう。
ノウハウや顧客の声の収集・蓄積を考えると、自社でコールセンター業務を行ったほうがよいケースもあります。外注の目的から、依頼すべき業務とそうでない業務を見極めることが大切です。
また、外注する事業者には、自社の求めるスキルや経験を持つオペレーターが配置されているかも重要な確認点です。コールセンターは顧客と直接やり取りを行う顧客対応の最前線であるため、安心して業務を任せられる事業者を見つけたいものです。
対応時間・件数
対応時間と対応件数(コール数)は、月々の利用料金に直結する事項です。特に月額固定制の場合は、発生するコール数の正確な予測は無駄なコストの発生を防ぐために重要になります。
1件あたりの料金や対応時間は事業者によって異なりますが、一般的に夜間や土日祝日などの対応には、割増料金が適用されます。複数の外注サービスの事業者を比較し、対応時間、件数、料金などの条件が、自社の要件と一致するかを確認しましょう。
また、一時的に問い合わせの数が急増した際、オペレーターの増員や対応時間の延長ができなければ、「全然つながらない」という顧客の不満につながります。急な需要の増加に柔軟に対応できるかも確認しておきたいポイントです。
コールオーバーの料金
コールオーバーとは、対応件数が契約上限を超えた場合に発生する状況です。
事業者によっては、追加の料金を支払うことでコールオーバーに対応してくれるところもあります。しかし、その際のコールオーバー料金は、通常の利用料金とは別に設定されていることが一般的です。
コールオーバーの料金が割高に設定されている場合、外注費用が予算を大幅に超過するケースもあるため、コールオーバーが発生する可能性やその際の追加料金などは、契約前に試算しておきましょう。
まとめ
コールセンターのアウトソーシングは、コスト削減や設定期間の短さなど、多くのメリットがあります。しかし、自社でノウハウや知識を蓄積できない、コミュニケーションの遅れが生じる可能性があるなどのデメリットもあります。メリットとデメリットを天秤にかけて、コールセンターのアウトソーシングが自社のビジネスに適しているかどうかを判断するようにしましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。