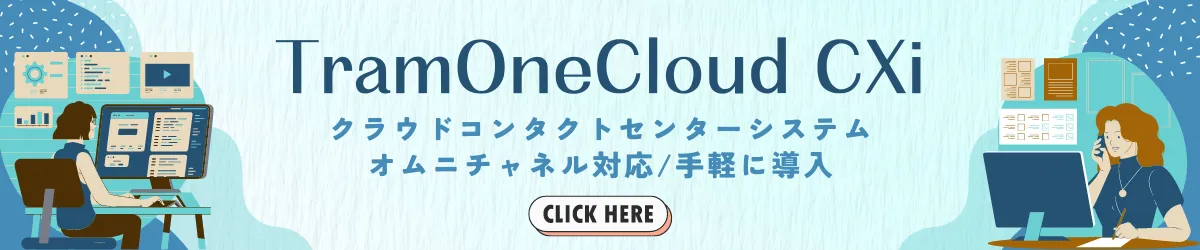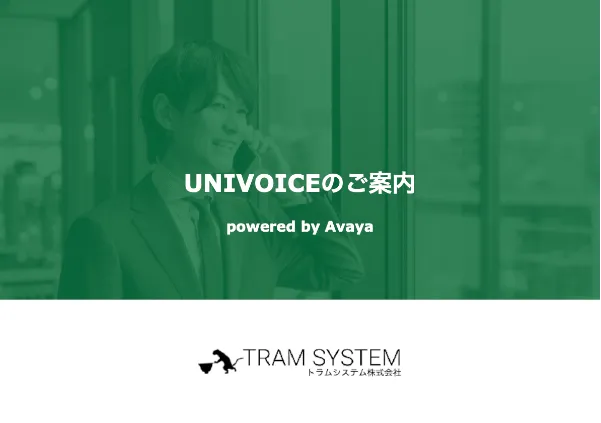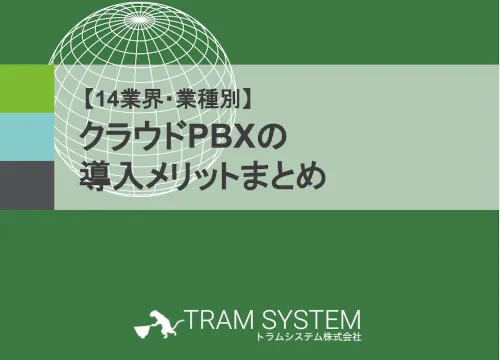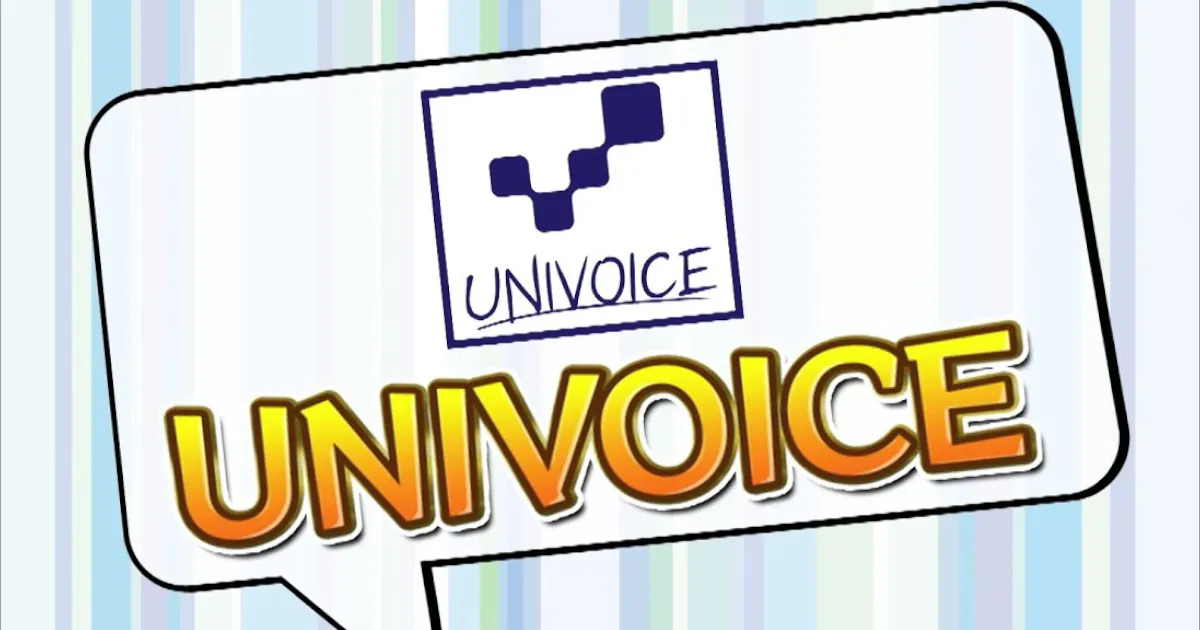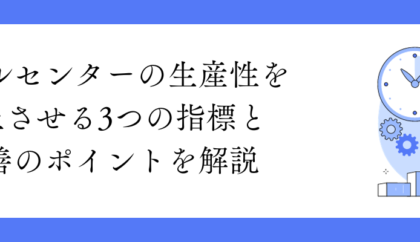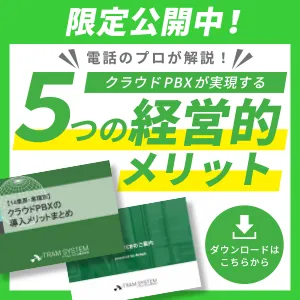テレワークがうまくできないダメ上司とは?部下の管理のポイントを解説|トラムシステム
テレワークを実施している企業では、対面での会話や電話からメールやチャットなどにコミュニケーション方法が変化し、上司が部下へのマネジメントに苦戦することがあります。
コミュニケーションの質や量が落ちないようにと積極的に声かけをしても、なかなか状況が好転せずに悩んでいる管理職も多いようです。
本記事では、テレワークがうまくいかない上司の特徴やテレワークにおける部下との接し方、管理のポイントについて解説します。ぜひ参考にしてください。

目次
テレワークでうまくいかない「残念な上司」とは?
オフィス勤務の際は評判のよかった上司でも、テレワーク導入後に人望を失ったり成績が出なくなったりする場合もあります。テレワークでうまくいかない「残念な上司」には、どのような特徴があるのでしょうか。以下を参考にセルフチェックをしてみましょう。
クイックレスポンスができない
テレワークにおいて素早い返信は業務を円滑にする重要なポイントですが、これがおろそかになっている人は注意が必要です。
オフィスであればメールやチャットの返信が遅くても、上司の様子を見て「すぐに返事をもらうのは難しそうだ」と判断できます。しかし、テレワークでは返信が遅いと「嫌われているのではないか」「部下の仕事に無関心だ」と疑われてしまう可能性があるのです。
特に判断が必要な場合や納期が近い場合、部下に大きなストレスを与える原因になります。テレワークではクイックレスポンスを強く意識するように心がけましょう。
仕事を丸投げする
テレワークに限りませんが、やるべき仕事は同じでも「任された」と「丸投げされた」ではモチベーションに大きな違いが出るので注意してください。
上司は丸投げしたつもりがないとしても、業務の依頼時に説明不足があると部下からは「仕事を丸投げされた」と思われがちです。テレワークでは即時に質問がしにくいため、部下の理解が追いつかないまま仕事が始まらないよう気をつける必要があります。
説明が曖昧でわかりづらい
テレワーク下では、上司の説明が曖昧でわかりづらい場合、部下は業務を円滑に進めることができずストレスになってしまいます。
業務の背景や求められるアウトプットの説明がなかったり、「適当にまとめておいて」のような曖昧な指示になっていたりすると、仕事が非効率になることは避けられません。
仕事を部下に任せられない
仕事の丸投げもよくないですが、過剰な管理も部下のモチベーションを下げる一因です。また、説明が面倒、苦手という理由で仕事を振り切れない人も注意しましょう。
こうした「仕事を部下に任せられない」上司は、部下を育てる、全体の生産性を高める、といった管理職としての意識に問題があると考えられます。
テレワークで様子がわかりにくい分、細かな報連相を求めることはマネジメント上とても大切です。しかし、度が過ぎると部下は「対応のために時間が取られる」「信用されていない」と感じてしまうので注意する必要があります。
頻繁に電話をかけてくる
オフィスではお互いに気軽にコミュニケーションを取ったり、業務を細かく確認したりできますが、テレワーク下ではそれができません。その中で、部下と音声で話せる電話はとても重要なツールです。
しかし、電話は確実に相手の時間を奪ってしまうため、多すぎる電話は部下の業務の妨げになってしまいます。
また、「話をしながらでないと考えがまとまらない」「メールは読むのも書くのも面倒」など、自分本位な理由から電話をしている場合、いつか部下にも悟られ、評判を落としてしまうので注意してください。
部下の仕事ぶりを見ていない
テレワーク中は、部下の仕事ぶりを評価するための情報も少なくなります。表面的な成果ばかりが評価される、担当業務以外の目に見えない貢献が見落とされるなどが、部下のモチベーション低下につながることもありますので注意しましょう。
テレワークでのマネジメントのポイント
テレワークを導入してから社内が活性化する企業もあれば、全体の意欲や生産性が低下してしまう企業もあります。
テレワークの導入後も、高い生産性やモチベーションを保っている企業は、上司がしっかりとテレワークに対応したマネジメントを行っているという共通点があります。
ここからはテレワークにおけるマネジメントのポイントについて見ていきましょう。
業務以外でもコミュニケーションを取る
上司と部下の関係性を良好に保つためにはコミュニケーションの質と量が重要ですが、過剰な干渉はNGです。業務以外にもコミュニケーションの機会を作るのがポイントで、コミュニケーションが改善されてマネジメントが機能するようになります。
たとえば、全社や部署の単位で朝礼を行う、定期的に顔出し必須のミーティングを行うといった方法はコミュニケーションの改善に効果的です。また、会議の前後の時間にメンバー間で雑談や情報共有をする時間を作るのもよいでしょう。
部下を信頼して過剰な管理はしない
テレワークでは、部下が「監視されている」という意識を持ちやすいため、部下を信頼して仕事を任せて過剰な管理を避ける姿勢を持ちましょう。上司からの信頼を感じることで、部下は責任感を持って仕事に取り組んでくれます。
ちゃんと仕事をしているか気になる場合は、定期的な進捗報告の機会を作り、そこでしっかりとコミュニケーションを取るだけでも十分です。個人の能力に比して仕事が進んでいない場合は、しっかりその原因を追及し改善を促すようにしましょう。
部下一人ひとりにあわせて対応する
テレワークではオフィスと比べてどうしても管理が行き届かないところがあり、社員一人ひとりの仕事に対する姿勢や業務上のスキルが求められます。しかし、性格や能力はそれぞれ違うため、同じように要求するのは間違いです。
また、テレワークではワークライフバランスにも配慮する必要があり、子育てや介護などとの両立を目的としている人もいます。こうした場合、上司からの頻繁な連絡がワークライフバランスの実現を妨げることがあるので注意してください。
上司は部下の性格や状況をよく理解し、適切に指示や指導、管理を行っていく必要があります。全体での会議だけでなく個別に話す機会も作って、業務上のレビューや悩みの相談などができるようにしましょう。
部下の成果・評価を意識する
テレワークでは部下の様子がわかりにくいため評価方法も再考が必要になることがあります。評価方法を変える場合は、必ず部下にも共有して意識させるようにしましょう。
たとえば、勤務態度の評価方法は、遅刻の有無や勤務時間の長さなどではなく、業務の進捗報告や納期内のアウトプットを基準にしたほうがテレワークにはふさわしいでしょう。
また、部下が出した成果に対しては適時にフィードバックを行うこともポイントです。
フィードバックを適時に行うと、モチベーションを高めて成長を加速させる効果があります。フィードバックがない場合、部下は仕事の質や評価について不安を抱えてしまうこともあるため、部下の成果については早めのフィードバックを意識しましょう。
テレワークでの上司と部下のコミュニケーションのポイント
テレワークになってから、上司と部下の間でのコミュニケーションが円滑にできなくなるケースは少なくありません。
テレワーク下では相手の様子がわからないため、コミュニケーションにおける意識を切り替えることが大切です。また、ITが苦手な人にも各種のツールを扱うスキルが求められます。
ここからは、テレワークでの上司と部下のコミュニケーションのポイントについて解説します。
電話・チャット・メールを使い分ける
テレワークでは電話・メール・チャットが主なコミュニケーションツールとして使われています。これらを正しく使い分けることで、コミュニケーションを円滑に行えるようになるでしょう。
音声で話せる電話は複雑な内容のやりとりができ、即時の回答ももらえる一方で、相手の時間を奪ってしまうのがデメリットです。メールは、記録が残ることや返信のタイミングを相手の都合で決められるのがメリットですが、急ぎの用件には向きません。
チャットはメールよりもスピーディーなやりとりができるように工夫されたツールです。便利ですが、情報が流れやすい、情報量やトピックが多い場合は不向き、など欠点もあるためうまく使いこなす必要があります。
それぞれのツールのメリットやデメリットを理解し、相手や目的、状況にあわせて適切に使い分けるようにしましょう。
電話・チャット・メールなどのコミュニケーションツールの使い分けについては、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
ツールを活用する
テレワークのマネジメントでは、ツールをうまく活用することがポイントになります。
テレワーク用のツールとしては、チャットツール、ビデオ会議ツール、プロジェクト管理ツールがよく話題に上がりますが、カレンダーやプレゼンス(在席)機能も便利です。
カレンダーは個人のスケジュールだけでなく、部署やチームの業務スケジュールを共有することで互いのスケジュールに配慮した業務が可能になります。プレゼンス機能は、「連絡可能」「会議中」「離席中」「休日」など個人の状態を表す機能で、テレワークで見えにくい互いの現在の状況を可視化するために効果的です。
新たなツールの利用は費用やルール整備、操作方法の習得などの課題もありますが、少しずつ進めていくことで生産性の高いテレワーク環境の構築につながります。
「つながらない時間」を尊重する
コロナ禍によって全国でテレワークの導入が進みましたが、その中で注目されるようになったのが「つながらない権利」です。「つながらない時間」を責めるのではなく、尊重する雰囲気を醸成することがテレワーク下のマネジメントには求められます。
つながらない権利(Right to Disconnect)とは、休日や時間外の電話やメールを拒否できる権利です。2021年に厚生労働省が発表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では、メール送付の抑制などが提言されています。
2022年現在、この権利に関係した罰則などはありませんが、こうした意識を持ってマネジメントすることで、部下たちも安心して働けるようになるでしょう。
つながらない権利については、次の記事でも詳しく解説しています。詳しく知りたいという方はぜひご一読ください。
テレワークのコミュニケーションにはクラウドPBXがおすすめ
クラウドPBXとは、PBX(構内交換機)をクラウド上に設置し、内線、外線、転送などの電話機能を利用するサービスです。従来のPBXとは違って自社内に機器を設置して保守を行う必要がなく、電話回線も不要ですので短期間で容易に導入できます。
テレワークのコミュニケーション問題の解決に効果的な機能が多いため、テレワーク導入の際にはぜひ検討してみるとよいでしょう。
テレワークのコミュニケーションにクラウドPBXがおすすめである理由についてポイントを絞って解説します。
登録端末間の通話は無料
クラウドPBXの大きなメリットのひとつが、登録した端末の間での通話が内線扱いとなり、通話料がかからないことです。
テレワークのためにBYOD(個人の端末を業務で使用すること)で運用している企業では、業務で利用した通話料を会社と社員のどちらで負担するかという問題が生じがちです。
クラウドPBXの導入により、社員間の電話の通話料を気にする必要がなくなれば、コミュニケーションのハードルをひとつ少なくなり、コミュニケーションが取りやすくなるでしょう。
会議通話・ビデオ通話が可能
クラウドPBX製品の中には、複数人での会議通話(グループ通話)に対応したものや、ビデオ通話に対応したものもあります。クラウドPBXはビジネス使用が想定されており、音声品質も高くセキュリティも強固なため、安心してグループ通話やビデオ通話を行えます。
会議通話やビデオ通話の機能を利用してオンライン朝礼やミーティングを実施すれば、質の高いコミュニケーションが可能になるでしょう。
チャット機能やプレゼンス機能も提供
テレワーク向けの機能が充実したクラウドPBX製品なら、チャット機能やプレゼンス機能、カレンダーなどのビジネスツールも提供しているのでおすすめです。
テレワーク用のツールは数多くありますが、個別にツールを導入すると、管理も煩雑で費用も高くなり操作の習得にも時間がかかります。クラウドPBXで複数のツールを代替できるため、テレワーク環境の構築に必要な時間やお金などのコスト削減が可能です。
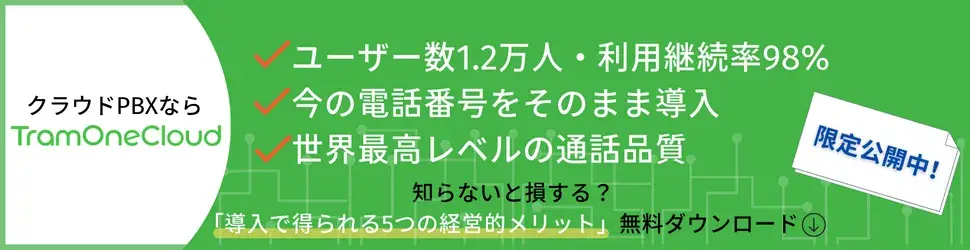
まとめ
テレワーク下のマネジメントやコミュニケーションでは、オフィスで働く場合とは異なるポイントがあります。部下の管理や関係性について、気になる点がある場合は本記事で紹介したポイントをぜひ見直してみてください。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。