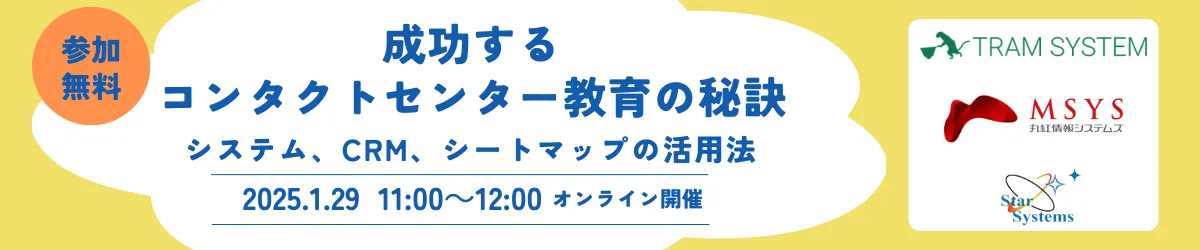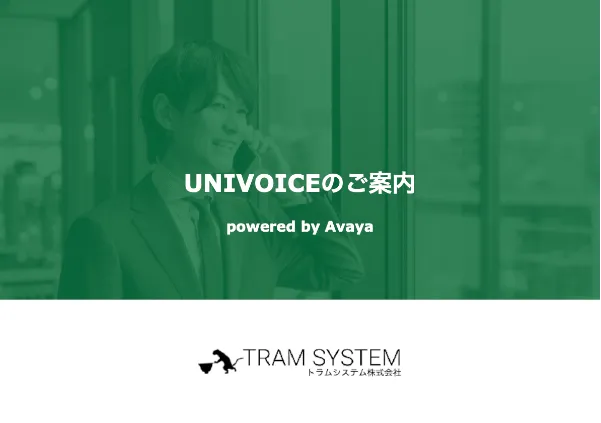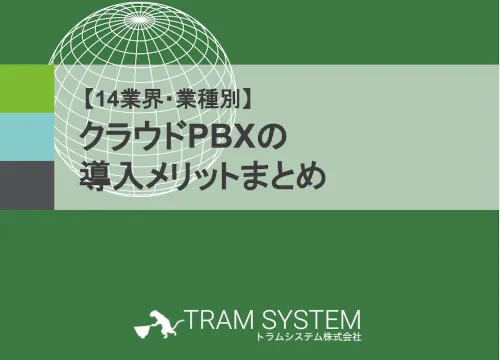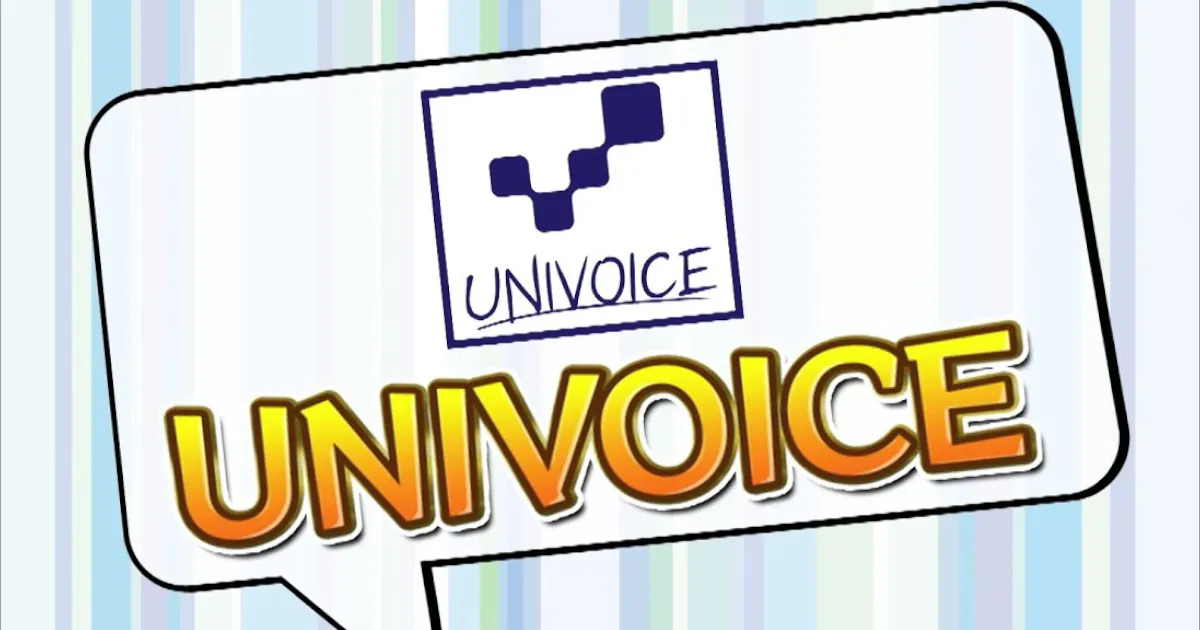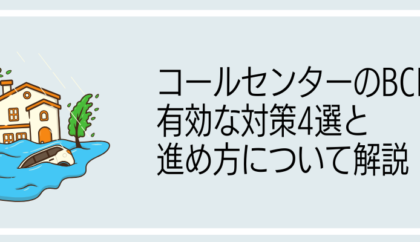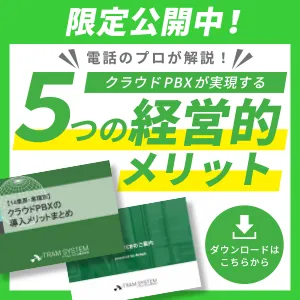テレワークで必要な「つながらない時間」とは?企業や個人の対応を解説|トラムシステム
特定の時間帯に業務に関する電話やメールの対応を拒否する「つながらない権利」が注目されているのをご存じでしょうか。ヨーロッパでは法制度化が進んでおり、日本でも関連するガイドラインを発表・導入する企業も増えています。
本記事では「つながらない権利」の概要、日本とヨーロッパの対応の違い、テレワーク中に「つながらない権利」を守るために必要な行動について解説します。

目次
テレワークで注目される「つながらない権利」とは
つながらない権利(Right to Disconnect)とは、休日や業務時間外に、業務に関わる電話やメールを拒否できる権利です。携帯端末端末の普及やチャットツールの誕生で顕在化した諸問題「仕事と私生活のオンオフが曖昧になる」「業務時間外も連絡への対応を強いられる」を解決するために行使されます。
つながらない権利で論点となるのは、以下のような問題です。
・仕事と私生活のオンオフが曖昧になる
・業務時間外も連絡への対応を強いられる
・モニター越しに業務を監視される
つながらない権利は、2017年1月にフランスで法令化された「従業員の完全ログオフ権」をきっかけに注目を集めました。この法律では、経営者と従業員が勤務時間外のメール等によるコミュニケーションを制限する方法を協議し、方針を定めることが義務付けられています。
その後EU諸国を中心につながらない権利に関する法律を施行する例が増加し、日本でもコロナ禍によるテレワークの流行で注目されるようになりました。2021年に厚生労働省が発表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では、メール送付の抑制などが提言されています。
厚生労働省のガイドラインの内容
厚生労働省が発表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」ではつながらない権利についてこのような形で言及されています。
メール送付の抑制等
テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。
労務管理上の留意点
テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。
長時間労働を行う労働者への注意喚起
テレワークによる長時間労働が生じる恐れがある労働者や、休日、所定外労働が生じた労働者に対して、使用者が注意喚起を行うことが有効である。
海外(ヨーロッパ)と日本の対応の違い
海外(ヨーロッパ)と日本の対応には1つ大きな違いがあります。海外(ヨーロッパ)のつながらない権利の多くが法律で定められた義務なのに対し、日本のつながらない権利は法的拘束力のない努力目標である点です。
法的拘束力がない以上、日本で業務時間外のメールや電話を完全に防ぐことはできません。「仕事であれば時間外でも対応すべきだ」といった意識も根強く、株式会社NTTデータ経営研究所が企業経営者や役員に対し2021年3月に行った調査では以下のような結果となりました。
【就業時間外に業務に関して緊急性のない電話やメール(LINE 等を含む)に対応することへの考え方】
1.連絡があれば対応したいと思う:18.6%
2.できれば対応したくないが、対応するのはやむを得ないと思う:46.7%
参考:株式会社NTTデータ経営研究所「新型コロナウイルス感染症と働き方改革に関する調査」
日本の企業文化は「仕事」と「プライベート」の境目が曖昧になる傾向があり、従業員は上司からの𠮟責や人事考課のマイナスを恐れて、つながらない権利を主張しづらいのが現状です。
テレワーク企業で「つながらない権利」が侵害されるシーン
テレワークを日常的に行っている企業では、自分の行動が相手のつながらない権利を侵害していないか、逆に上司や同僚の行動で自分のつながらない権利が侵害されていないか確認が必要です。
具体的なシーンを紹介しますので、現在の業務スタイルと照らし合わせて問題がないかチェックしてみましょう。
業務時間外にメール・チャットの即時返信を求める
テレワーク業務時間外に「昼間話した件どうなってる?今日中に返信して」とメールやチャットの返信を求めるのはつながらない権利の侵害です。連絡相手が上司や取引先など上位の人物であることが多く、対応を拒絶することが難しい状況が多々あります。
上位の立場にある人間が時間外連絡を行わなければ防止できるため、管理職へつながらない権利に関する研修や教育を行うとよいでしょう。取引先とは「時間外の連絡を行わない」と契約書に明記するなどしてつながらない権利の侵害を防止します。
休憩時間中の電話待機を求める
テレワークでも休憩中に「電話が来たら対応して」と電話待機を求められるケースはいくつか存在します。
会社支給のスマホや電話機で電話待機を強いられ、ストレスや疲労感を感じるテレワーク労働者は少なくありません。休憩時間中の労働は残業代、あるいは別時間の休憩で対応すると法律で定められているにもかかわらず、どちらも付与せず電話待機を命じる企業も存在します。
休憩を2交代制にして休憩時間を確保する、電話代行サービスを利用する、時間外アナウンスを流すなどが対策として考えられます。暗黙のしきたりや強制をやめ、全員がストレスなく働ける環境を構築しましょう。
スマホの電源は常時入れておくように求める
多忙な企業では「テレワーク中でも顧客や上司からの連絡に備えてスマホの電源は常時入れるように」と求められるケースがあります。会社から指示を受ければすぐ労働を開始できる状況は、業務から解放されているとは言えず、労働時間の超過にもなりかねません。
労働時間の長期化は安全配慮義務違反にもつながるため、企業はつながらない権利を尊重する意思を表明し、業務端末のシャットダウンなどを行う必要があります。
「つながらない権利」を作るために社員個人ができること
つながらない権利はテレワーク企業を中心に重要性を増しているものの、実際には日本企業の社員が企業に対してつながらない権利を主張することは困難です。以下の要因が理由として挙げられます。
・日本企業の風土では業務とプライベートの切り分けが困難である
・つながらない権利を保証する法律が現在の日本に存在しない
・経営者側のつながらない権利に対する意識が希薄である
現時点でつながらない権利を確保するには、個人で意識的に公私をわけるように行動することが求められます。現場レベルでできることを解説するので、テレワークの現場で実践してみましょう。
不必要にプライベートの連絡先を教えない
顧客や取引先に利便性を提供するため、自身のつながらない権利を犠牲にしてプライベートの連絡先を教える行為は珍しくありません。しかし、一度前例を作れば今後もプライベートの犠牲が要求されます。後任も「前の担当はやってくれたのに」と言われ苦労することでしょう。
企業全体のことを考えるならば、個人のスタンドプレーでつながらない権利を放棄すべきではありません。「指定された電話番号以外でのやりとりをしない」などのルールを設け、悪しき前例を作らないようにしましょう。
計画的に仕事を進める
時間外の電話やメールは、予期せぬトラブルやミスによって引き起こされるのが基本です。仕事のスケジュールに余裕を設定し、計画的に仕事を進めるよう心がければ、上司や取引先から時間外に緊急連絡が来る可能性を削減できます。
管理職の場合は、突発的な業務やスケジュールに余裕のない案件が発生しないよう調整し、部下のつながらない権利を守ることが求められます。
同僚や上司とコミュニケーションのマナーについて話し合う
顔を合わせる機会が少なくなるテレワークでは、同僚や上司とのコミュニケーションマナーが重要となります。これまで当たり前だった時間外の返答やレスポンスの要求を避け、「金曜日夜の連絡の返事が月曜日になるのはしょうがない」のような寛大な認識を共有しましょう。
業務時間内はクイックレスポンスを心がける
業務時間内はクイックレスポンスを心がけ、共に働く上司や同僚を安心させましょう。レスポンスが日常的に遅れていると、連絡を送る側も不安になり、返事の催促が発生しやすくなります。業務時間内の連絡には即座に対応し、終業後や休日中の「あの件どうなりましたか?」が発生しないようにしましょう。
良かれと思って親切に対応しすぎない
良かれと思って行った親切な対応が、相手や自分自身のつながらない権利の侵害に繋がるケースもあります。上司、顧客、取引先から業務時間を超えたつながりを求められた時「本当に企業のためになるのか?」「他の同僚や部下は迷惑しないのか?」を考え、冷静に返答しましょう。
まとめ
働き方が変化すると共に労働者の考え方も変わり、日本でもつながらない権利をはじめとするフレキシブルな考え方が広がりを見せています。プライベートと業務を個人で意識的に分け、自分だけでなく働く社員全員のつながらない権利を守れるよう心がけましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。