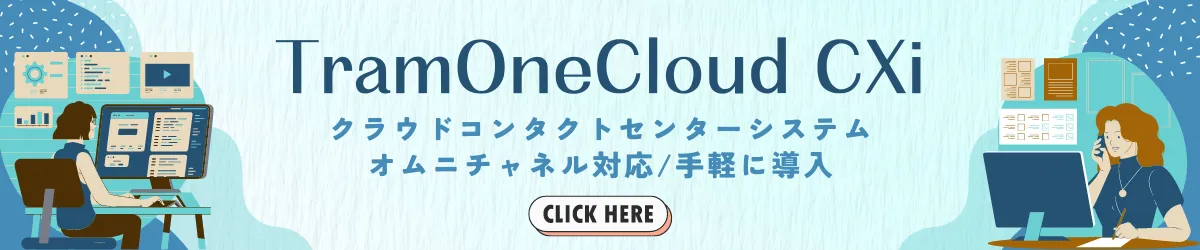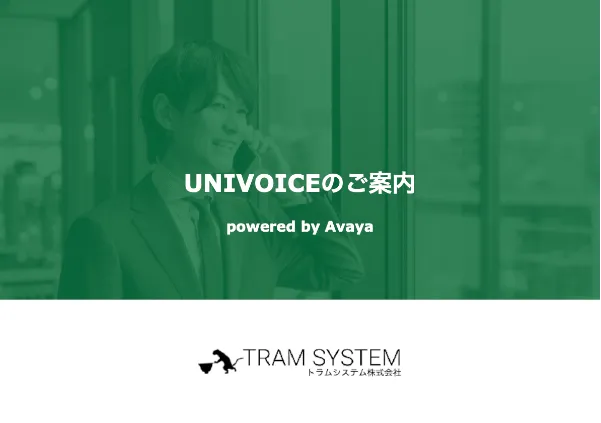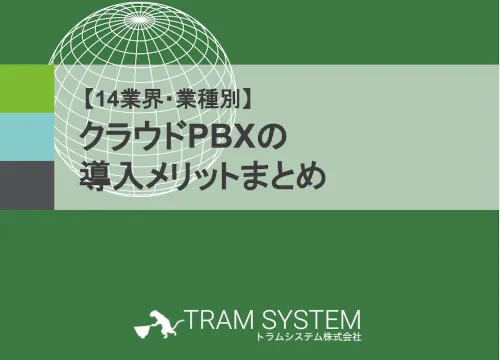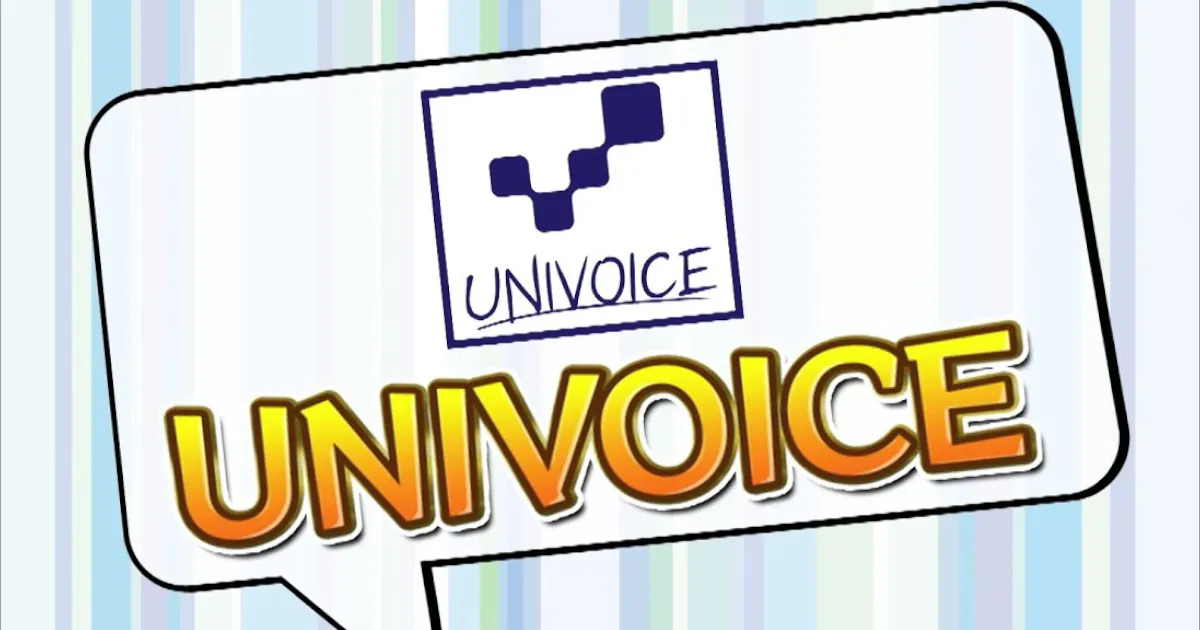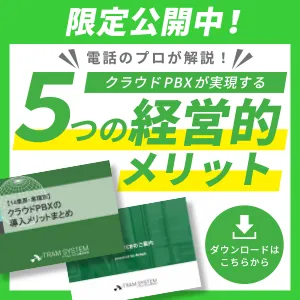MVNOはなぜ安い?丨安さの仕組み・MNOの違いと歴史も解説|トラムシステム
スマホの通信費を見直すため、格安SIMの普及が広がっています。格安SIMの仕組みに欠かせないのがMVNOですが、そもそもMVNOとは何でしょうか?この記事では電話代をおさえてモバイル通信を利用できるMVNOの仕組みや歴史、MNOとの違いなどについて解説します。

MVNOとは
MVNO(エム・ブイ・エヌ・オー)とは、Mobile Virtual Network Operator(仮想移動体通信事業者)を略した言葉です。
大手携帯会社である、ドコモ、au、ソフトバンク(キャリア)から一部の回線を借りて、インターネットサービスを提供しているものをMVNOといいます。
現在、ワイモバイル、UQモバイル、LINEモバイル、楽天モバイル、マイネオなど様々なMVNOのサービスがあります。
MVNOと格安スマホ
スマートフォンを利用するために必要なSIMカードには、いろいろな情報が記録されています。例えば、デバイスはスマホなのかガラケーなのか、どのキャリアから通信回線を借りているのか、電話番号は何かといった個々のIDデータが記録されています。
最近はSIMカードを自由に挿入して利用できるSIMフリー端末が多く普及し、さらにMVNOと契約することでより通信費や電話代の料金を抑えてスマホを利用することができるようになったことで「格安スマートフォン」と呼ばれるようになりました。
MVNOのメリット
1.電話代や通信費を安くできる
やはりMVNOの強みは料金の安さです。キャリアの月額料金と比べると費用をかなり安くすることができます。実店舗では店員から親切にいろいろと教えてもらえますが、そのような人件費や店舗管理費を削減することで安い料金を実現できています。
2.プランの選択肢が多い
MVNOのプランは豊富に用意されています。あまりインターネットを使わない人なら1GB、2GB程度で十分です。よく動画を見たり、アプリでゲームをしたりするなら10GB以上のプランを選ぶなど、使い方に応じて細かい通信料を設定できるのがMVNOのメリットです。
MVNOのデメリット
1.MVNOによっては、通信回線が不安定にあることがある
格安スマホでよく問題視されるのが、通信回線の品質がキャリアよりも劣る点です。
MVNOはキャリアから回線を借りているものなので、利用人数によっては品質の低下の可能性があります。例えば、お昼の休憩時間や夕方以降など、仕事をしている人たちが急にスマホやパソコンなどの回線を一斉に使いだすと通信速度が落ちることがあります。
2.キャリアで使えた機能が使えなくなる
MVNOでは、@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jpといった、ドコモやau、ソフトバンクで何気なく使っていたキャリアメールが使えなくなります。その場合、MVNOで用意されているメールアドレスに変更するか、Gmailなどのフリーメールを利用することで解決できます。
また、キャリア決済も利用できなくなるので設定の変更が必要となります。
3.実店舗が少ない
キャリアに比べて実店舗が少ないのもMVNOのデメリットです。簡単なことならインターネットで調べて解決できる程度の力があればもちろん、電話やメール、チャットでいろいろ教えてくれるMVNO事業者もたくさんあるため、心配する必要もありません。
MVNOの歴史
電話といえば、昔はNTT一択でした。しかし1988年に自動車電話事業が解禁されてから三大キャリアへと発展していく多くの事業主が参入していきました。NTTだけのものであった電話業界により多くの扉が開かれたのです。
これまで穏やかだった電話業界が競争社会となり、2001年にはついにb-mobile(日本通信)が、旧DDIポケットのPHS通信回線を借りる形で事業をスタート。これが日本でのMVNO事業のはじまりです。
大手携帯キャリア会社である、ドコモ、au、ソフトバンクだけでなく多くのインターネットプロバイダが電話業界へと足を踏み入れたことで、モバイル業界の競争が高まり、よりユーザーが自分にあったプランを選択し購入できる時代へと変わっていきました。
今ではNTT、大手キャリアだけでなく多数のプロバイダーたちが様々なサービスを展開することで顧客獲得競争を行っており、ユーザー側からすればより自分にあったサービスを選択できるようになっています。
MVNOとMNOとの違い
MVNOと似た言葉で、MNOというものがあります。MNOとは、Mobile Network Operator(仮想移動体通信事業者)の略で、以下のような意味の違いがあります
・MNO・・・Mobile Network Operator(移動体通信事業者)
・MVNO・・・Mobile Virtual Network Operator(仮想移動体通信事業者)
MVNOにある「仮想」という文字がMNOにはありません。
MNOは国から許可を得て通信回線を一部もらい、ユーザーに提供できる設備を自分たちで用意して持っている会社のことです。実際の設備を持っているので「仮想」ではありません。反対に、MVNOはMNOから一部の回線を借りているだけで、実際に何かを持っているわけではないので「仮想」という言葉がついています。
日本の回線は限られたものなので、総務省の許可がなければ自由に使えず、その許可を取った回線がMNOです。
・MNO・・・ドコモ、au、ソフトバンク
・MVNO・・・ワイモバイル、UQモバイル、LINEモバイル、楽天モバイル、マイネオなど。
MNOが用意するべき設備には、電波を送受信するためのアンテナやネットワークを運用するための整った施設などが必要が、これには多額の費用がかかります。
一方、MVNOではMNOの持っている通信回線を一部分けてもらい、そこから通信サービスを提供します。MVNOは電波を分けてもらっているだけなので、国からの許可はいらず、自分たちで設備を用意する必要もありません。
MVNOはなぜ安いのか
通常、キャリアで契約してかかる月々の費用は7,000円~1万円ほど。それがMVNOなら2,000円~3,000円にまで低価格におさえることができます。(プランによります。)
こうしたMVNOの安さの背景には、MNOつまり大手キャリアのように、国から通信回線の許可をもらったり、大がかりな施設を用意する必要がなく、その分のコストや人件費を抑えられる、といったことがあります。
さらに、大手キャリアとMVNOの料金プランの考え方にも、安さのヒミツが隠されています。
MVNOと大手キャリアの料金プランの違い
大手キャリアは電話サービスを基本料金として料金を定めています。それに対して格安SIMを扱うMVNOではインターネットを利用するデータ通信を軸にプランを考えています。
現在では、「LINE」や「スカイプ」のようにインターネット回線だけで電話が無料でできるようになりました。そのため、電話料金をベースに料金プランを考える大手キャリアより、電話サービスをアプリ通信でまかなうことのできるMVNOの方が安い料金価格を提供できるのです。
まとめ
MVNOは個人だけでなく企業でも大きな需要が伸びてきています。企業のスマホ貸与とクラウドPBXなどのビジネスフォンのスマホ連携などにMVNOは大きく寄与しており、企業単位で、電話も通信費も低価格で利用することが可能な時代となってきています。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。