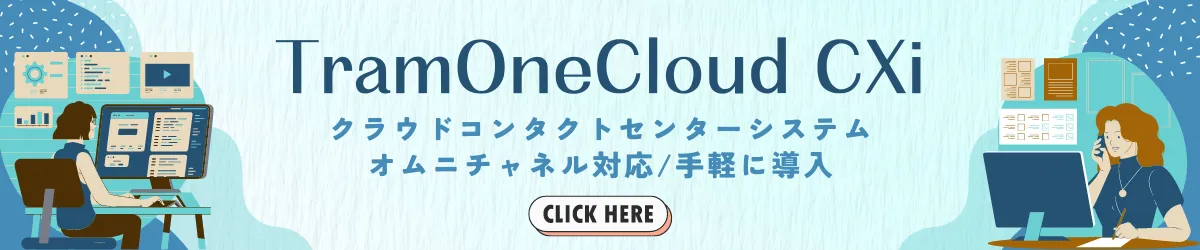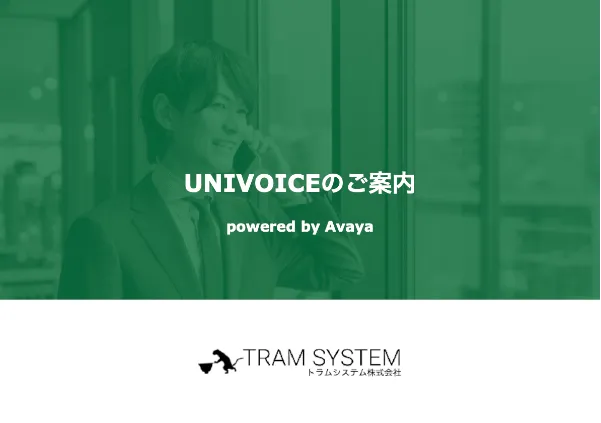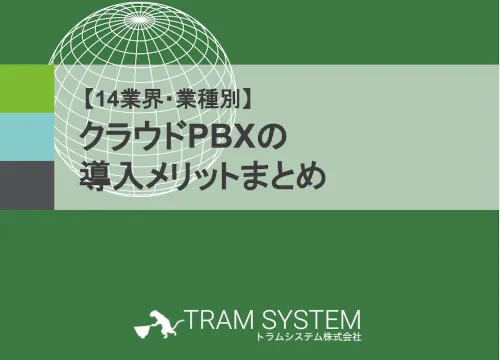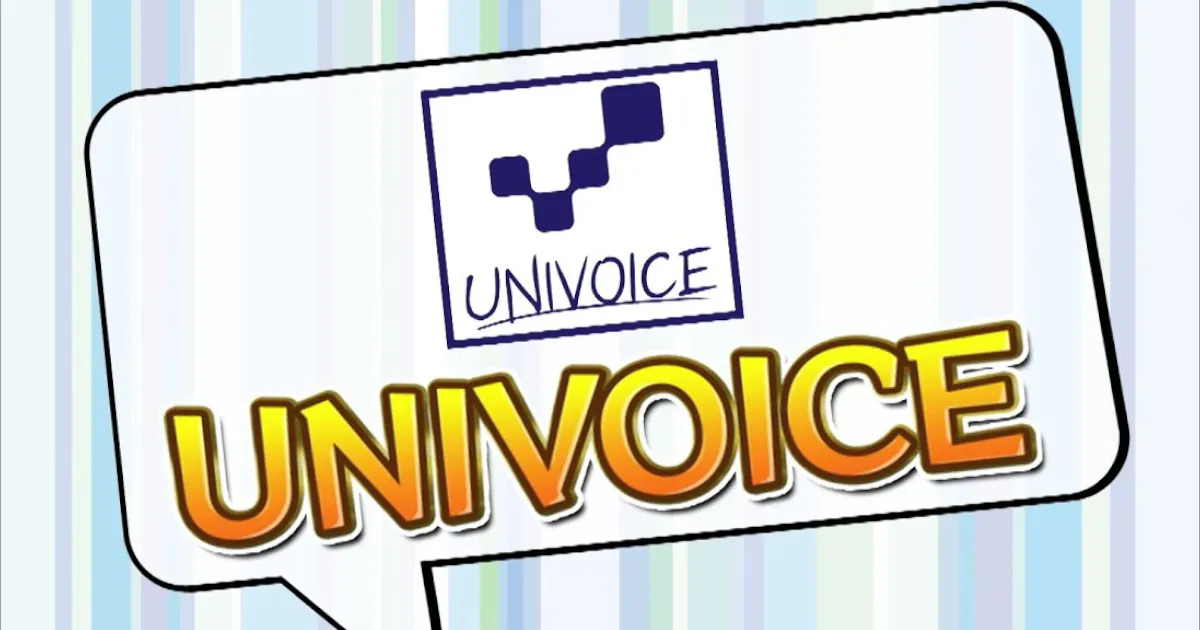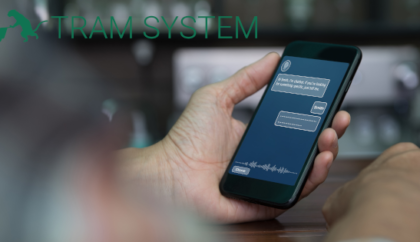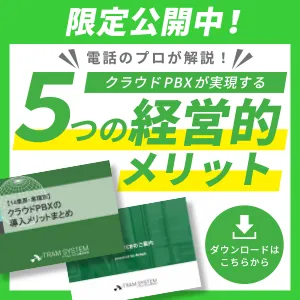ビジネスホンが壊れたその時に|修理方法から寿命まで対応方法を教えます|トラムシステム
日々の業務で利用しているビジネスフォンが故障すると、業務への影響もあり一刻も早く復旧したいと考えると思います。ビジネスフォンが動かなくなった、調子がおかしい、という場合のよくある症例と対応方法を紹介します。

目次
ビジネスフォンの仕組み
まずはビジネスフォンの仕組みについて解説します。ビジネスフォンは家庭用電話機とは異なり、電話回線の引き込み口と本体を接続するだけで動くものではありません。まず、電話回線の引込口と主装置を接続します。(主装置の役割についてはこの後で解説しています)その後主装置とローゼットと呼ばれる小型の機器を接続し、モジュラーケーブルを介して各内線電話機と接続します。ローゼットには主装置からの配線を各内線電話機に分岐する役割があります。
つまり、ビジネスフォンは「電話回線の引込口 → 主装置 → ローゼット → モジュラーケーブル → ビジネスフォン」といくつかの機器やケーブルを通して設置する必要があります。
ビジネスフォンの主装置とは
家庭用電話機の場合、一つの電話回線から接続できる本体は一台のみで、電話番号も一つだけです。一方ビジネスフォンでは、一つの電話回線で複数の電話機本体が利用でき、外線だけでなく、各電話機間で内線をかけることもできます。それを可能にしているのが「主装置」と言われる機器で、主装置は外線と内線、または内線間をつなぐ役割があります。回線を内線電話機で共有する他、電話帳のデータ記憶なども行っています。ビジネスフォンの利用には主装置が必要であり、電話機本体と並んで重要な機器です。
ビジネスフォンの本体・主装置の耐用年数・寿命
ビジネスフォンに限らずほぼ全ての機械・設備には法定耐用年数が設定されています。耐用年数は、法律で定められている「問題なく利用できる期間」であり、この期間を元に減価償却費の算出が行われます。ただし、法定耐用年数はあくまで法定上の使用可能な見積もり期間であり、実際の利用可能期間(寿命)とは異なります。
ビジネスフォンの耐用年数は6年と定められていますが、実際には10年以上利用することができます。主装置についても、6年の耐用年数よりも長い期間利用できるとされていますが、利用頻度、設置環境などによって異なります。
ビジネスフォンの故障の主な原因
10年、15年と長期間に渡って利用できるケースが多いとはいえ、耐用年数(6年)を超えると故障する機器が増えてくることも事実です。特にビジネスフォンは多くの人が一日に何度も利用するものであるため、経年劣化は避けられません。ビジネスフォンの故障で最も多いのは、電話機本体ではなく電話回線を複数の機器に振り分ける主装置です。特に電源ユニットと呼ばれる基盤部分は長年の利用によって壊れやすい部分です。
具体的な故障理由について解説していきます。
ホコリによる故障
気がつくと部屋の片隅や棚の上などに溜まっているホコリ。このホコリが原因で主装置が故障することがあります。特に、主装置などはオフィスの隅など、普段あまり掃除をすることがない場所に置かれることが多いため、知らず知らずのうちにホコリがたまり、故障の原因となり得ることがあります。対策としては定期的に掃除をすることが最も有効でしょう。
CPUユニットの劣化
主装置の中に入っているCPUユニットと呼ばれるパーツの劣化によってビジネスフォンが突然動かなくなることがあります。CPUユニットは電話機や電話回線をどのように動かすかをコントロールするメイン基盤ですが、24時間365日作動し続けるため劣化もしやすいパーツです。CPUユニットに異常がある場合、主装置を再起動することで回復することがあります。ビジネスフォンの調子がおかしい、動かない、といった場合の対応方法についてはこの後に詳しく解説しています。
配線の劣化
CPUユニットと同じく、配線の劣化によって故障することもあります。ビジネスフォン本体や主装置は定期的に入れ替え工事を行うことはありますが、配線はそのまま、という企業も多くありますが、配線も機器と同じく長年の利用によって老朽化していきます。老朽化してしまった配線は工事が必要になるため、タイミングとしてはビジネスフォンの入れ替え工事などに一緒に配線の状態をチェックすることをおすすめします。
そのため、ビジネスフォンの設置や取替工事の際に一緒に配線の状態をチェックし、劣化が見られる場合は補修工事を一緒に提案してくれたり、工事当日に柔軟に配線処理などに対応してくれる業者を選ぶこともポイントです。
ビジネスフォンが動かない時の対応方法
日常的に利用するビジネスフォンが突然動かなくなると、業務に大きな影響がでる可能性がありますが、まずは落ち着くことが重要です。メーカーや修理業者に問い合わせをする前に自分たちで出来ることもあります。ここからは、ビジネスフォンが動かない場合の対応方法について解説します。
一部の電話が使えないのか、全ての電話が使えないのかを確認する
まずは動かない電話機が一部なのか、全てなのかを確認します。一部のみの場合、主装置とその電話機を繋いでいるケーブルが問題なく接続されているか、緩んでいないかどうかを確認します。接続されている場合は電話機から近い順番に配線を抜き差ししてみて、事象が解決するかどうかを見てみましょう。主装置やそれ以外の機器に問題がない場合、配線を繋ぎ直すだけで解決するケースもあります。
電話機の問題か、主装置の問題かを確認する
配線に問題ない場合、次は電話機の問題か、主装置の問題かを確認します。一部の電話機のみが使えない場合、正常に動作している電話機と入れ替えることで本体の故障かどうかを調べます。利用できない電話機が一台だけの場合、主装置の電源を一度オフにした上で5分~10分経った後に再度オンにすることで正常に動くケースもあります。正常に動作している電話機と入れ替えたり、主装置を再起動しても動かない場合は主装置や他の部分の故障の可能性を疑います。
回線の不具合を確認する
問題が電話機本体にないとわかった後は、回線の不具合の有無を確認します。光回線の場合、ONU、ホームゲートウェイ、光電話アダプタなどの機器の電源が入っていること、コンセントやモジュラージャックにケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。ケーブルを一度抜き、再度しっかりと差し込んでみる、という方法で解決するケースもあります。また、自社や特定のエリアに対して通信障害などが発生していないか利用している通信キャリアに問い合わせをしてみましょう。
主装置の不具合を確認する
電話機や回線に問題がない場合は、主装置の故障やケーブルの断線・ショートの可能性も考えられます。主装置などは個人が勝手にいじることで逆に別の故障などに繋がることもあるため、無理に自己解決しようとせずにメーカーや販売業者に相談しましょう。問い合わせ時には、利用しているメーカーや利用期間に合わせて
などを伝えるとスムーズに話を進めることが出来るでしょう。
主装置の電源と再起動の方法
対応方法で解説した通り、主装置を再起動することで問題が解決するケースがあります。主装置の再起動の方法は、機種によって異なり、誤った手順で再起動を行うと主装置が壊れてしまったり電話帳などのデータが破損してしまう可能性があるため、注意が必要です。焦って再起動を行おうとせず、メーカーの取扱説明書などを確認してから行いましょう。
ビジネスフォン故障時の修理について
調査や問い合わせの結果、故障と判明した場合は修理・または買い替えが必要です。主装置のユニットが故障した場合、部品交換によって修理ができることもありますが、購入から長期間過ぎている機種の場合、修理用の取替パーツがメーカーから販売されていないことがあります。ビジネスフォンの販売メーカーが部品を保有する期間は、製造打切り後7年間であるため、それ以降はパーツをメーカーから取り寄せることができません。
世に多く出回っているメジャーなモデルの場合はメーカー以外の修理業者等で対応している場合もありますが、パーツがなくて修理ができない可能性もあるため、まずは販売店やメーカーに問い合わせしましょう。日々の業務で利用する事務機器のため、一日も早く修理を行いたいところですが、修理にかかる時間については目安として
です。
一度修理をしても、定期的に故障するのであれば思い切って新しいビジネスフォンに入れ替える検討をしてみても良いでしょう。新品の購入は初期費用がどうしても高くなってしまいますが、中古ビジネスフォンであれば初期費用を抑えて入れ替えることができます。中古ビジネスフォンであっても発信・着信・転送といった電話としての基本機能は最新機種と変わらずに利用できるため、最低限の機能で良いという場合はおすすめです。
まとめ
ビジネスフォンは24時間365日稼働しており、いきなり故障すると業務に大きな影響がでる可能性があります。急な故障で電話帳などのデータも全て消えてしまった、ということも避けたいものです。大事なときにいきなり使えなくなった、といったことを起きないように耐用年数・利用継続年数を把握し、適切なタイミングで買い換えることが重要です。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。