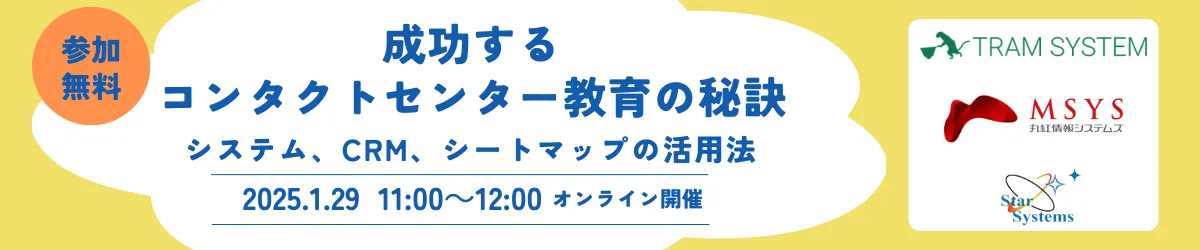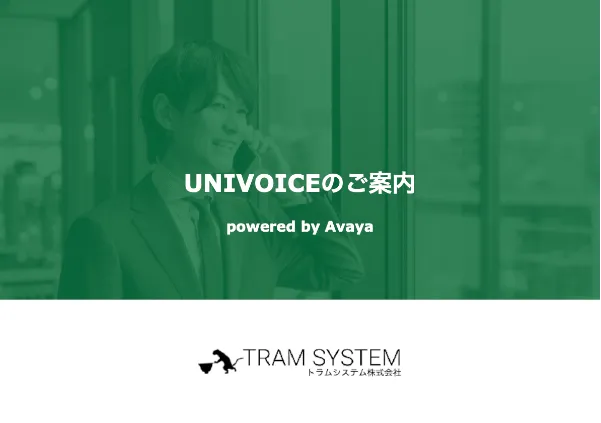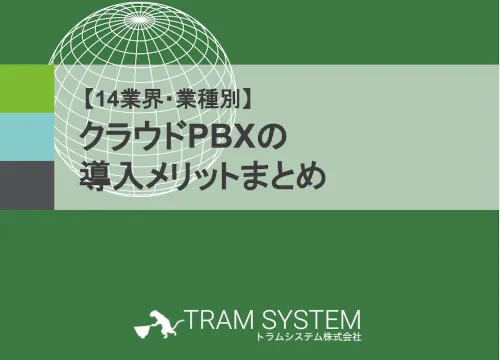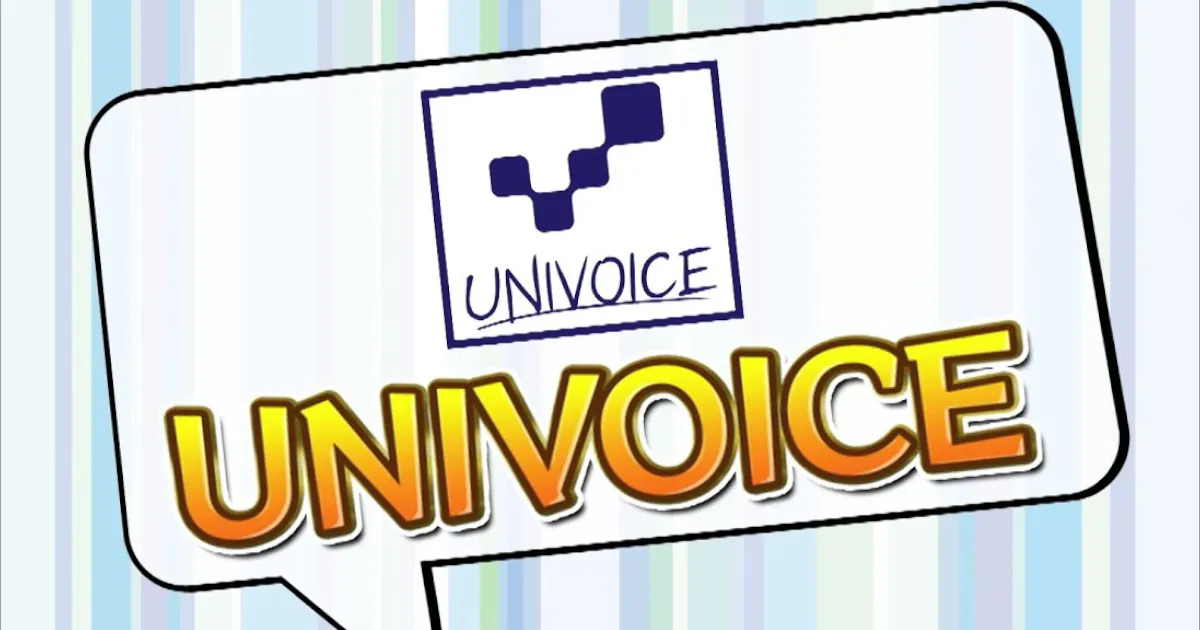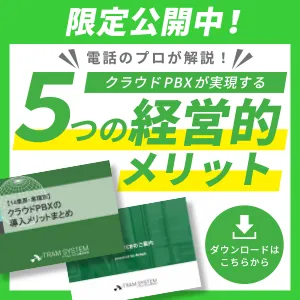管理がしやすい内線電話の採番方法とおすすめルールを紹介|トラムシステム
内線電話設置の際に重要となるのが、各電話機への内線番号の採番です。2~4桁の番号で設定されますが、効率よく行われないと運用に支障をきたします。本記事で内線番号採番のポイントについて解説します。

目次
内線番号の採番ルールのポイント
内線電話の採番は、予めルールを設定して上で行うことが大切です。ルールを設定せずに採番を行なった場合、以下のようなことが起きる可能性があります。
・内線番号が統一されておらず、表にした際見栄えが悪い
・番号が覚えづらく、連絡に支障をきたす
・社員の増減があった場合、設定が面倒
将来の人員増強やオフィス移転なども視野に入れ、内線番号のルールはしっかり定めておきましょう。ただし、何でもありというわけではなく、いくつかの基本ルールが存在します。ルール設定時に気を付けるべきポイントを紹介します。
分かりやすい
内線番号の採番を行う際は、数字をできるだけ揃え、分かりやすく規則性のある番号配置にしましょう。分かりにくい番号配置だと、社員が操作に手間取ってしまい、ミスの原因となります。
・わかりやすい番号配置の例
【番号1】210
【番号1】211
【番号1】212
わかりにくい番号配置の例
【番号1】145
【番号2】582
【番号3】369
社員に周知させるために作成する内線の番号表も、用紙や文字のサイズを適切にする、役職者を上位に持ってくるなどして、見やすさを心がけてください。内線電話を受付としてオフィス入り口に配置するケースも増えているので、来客対応の内線番号は番号表内で太字・赤字にしましょう。顧客対応スピードが向上し、顧客満足につながります。
追加・変更の対応がしやすい
企業では社員の入社・退職が頻繁に行われますので、内線電話の採番も追加・変更がしやすいように設定しておきましょう。部署ごとに番号を採番する場合は、被らないように100単位で設定すると効果的です。10単位で設定すると、すぐに枠が埋まってしまうので注意しましょう。
・追加・変更の対応がしやすい番号配置の例
【営業部の内線番号】210番から
【経理部の内線番号】310番から
【総務部の内線番号】410番から
・追加・変更の対応がしにくい番号配置の例
【営業部の内線番号】210番から
【経理部の内線番号】220番から
【総務部の内線番号】230番から
社員数がストックしている番号以上に増えた場合は、内線番号の桁を4桁5桁と増やすのがおすすめです。
1で始まる番号は使用しない
採番を行うにあたり、100番から数字を使おうとするケースがありますが、要注意です。内線番号では基本1で始まる番号は使用しないのが基本ルールとなっています。1の代わりに、2を最初の数字として設定するようにしましょう。
・おすすめできる番号配置
【番号1】210
【番号1】211
【番号1】212
・おすすめできない番号配置
【番号1】110
【番号2】111
【番号3】112
1がおすすめできないのは、警察の110番や消防の119番など、1から始まる番号緊急短縮ダイヤルが多いからです。もし外線に誤発信した場合に事情を説明する必要が生じ、業務効率の悪化を招きます。
キリのよい番号は取っておく
100,200などキリの良い番号は一旦確保し、一般社員の番号配置ルールから離しておくのがおすすめです。
・おすすめできる一般社員の番号配置
【営業部の内線番号】210番から
【経理部の内線番号】310番から
【総務部の内線番号】410番から
・おすすめできない一般社員の番号配置
【営業部の内線番号】200番から
【経理部の内線番号】300番から
【総務部の内線番号】400番から
理由として、キリのいい番号は社長や役職者の内線番号として利用することが多いことがあります。社長や役職者を電話で呼び出す際は緊急性が高い案件が多く、押しやすい数字を採用するとミスが減ります。部署の共通内線番号として採用するのもおすすめです。大企業では役職者や幹部も増えるので、キリのいい数字は常にストックしておきましょう。
・キリのいい番号 配置例
【社長室の内線番号】200番
【専務の内線番号】300
【営業部の共通内線番号】400番
採番ルールの例
採番ルールは、社員数が多ければ多いほど、採番は慎重に行う必要があります。大企業では1部署に100人を超える社員が在籍している場合も多く、ルールを明確に決定しないまま採番を行うと、後になって使用可能な番号がなくなってしまう可能性があります。主な採番ルールを3つ紹介します。
オフィスの階や部署で分ける
オフィスの階や部署に応じた採番は、番号ごとに特徴を付けられ覚えやすいというメリットがあります。階と部署両方を組み合わせて採番すると、さらに細かく分類できます。ただし、1から始まる番号は避ける、キリのいい数字を役職者用にするなどの基本ルールは遵守しましょう。
オフィスのレイアウト変更のたびに内線番号を変更しなければならない、番号の枠が大量に必要というデメリットもあります。中小企業よりも、複数の階にまたがるオフィスを持つ大企業でおすすめの方式です。
・階に応じた番号配置
【1階の内線番号】210番から
【2階の内線番号】310番から
【3階の内線番号】410番から
・部署に応じた番号配置
【営業部の内線番号】210番から
【経理部の内線番号】310番から
【総務部の内線番号】410番から
・階と部署に応じた番号配置
【1階営業部の内線番号】220番から
【2階総務部の内線番号】330番から
【3階経理部の内線番号】440番から
社員番号=内線番号とする
シンプルに、社員番号を内線番号として採用する方法です。社員番号と同一なので、採番や管理がしやすいというメリットがあります。その反面、階や部署ごとの特徴を出しにくい、社員が増減するたびに新たに設定しないといけないのがデメリットです。フリーアドレスオフィス(社員の固定席がないオフィス)のような社員の待機場所が一定ではない会社、社員数が少なめの中小企業で採用しましょう。
ルールを設定せずに連番で振り分ける
始まりとなる内線番号(10や100など)から、連番で内線番号を設定していく方法です。
・連番での番号配置
【社長】210番
【専務】211番
【本部長】212番
とにかく簡単に採番できるので、社員の少ない企業でおすすめの方式です。ただし、当然ながら階や部署による特徴は出せず、人員増加後の調整も難しいので注意しましょう。家族経営など人員の増減が行われにくい企業の場合は、採用しても問題なく扱えます。
内線電話機の台数の目安は?
内線電話機の最適な数は、「社員数+会議室」を合わせた数です。社員数が10人、会議室が5人の場合は、15台の内線電話が必要となります。
「社員数+会議室」の数分用意することで、社員個人に掛かってきた内線電話、会議室にいる社員に掛かってきた内線電話に対応可能です。ただし、内線を使っていない社員、まったく使われていない会議室がいる場合は、削減しても構いません。使用状況を分析し、柔軟に対応しましょう。
まとめ
オフィスの通信設備として、重要な役割を果たすのが内線電話です。内線電話を効率よく運営するためにも、番号の採番は計画的に行いましょう。オフィスの拡張や移転、社員数の増減などを見据えた採番ルールを設定し、通信設備をスムーズに利用できるようにしましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。