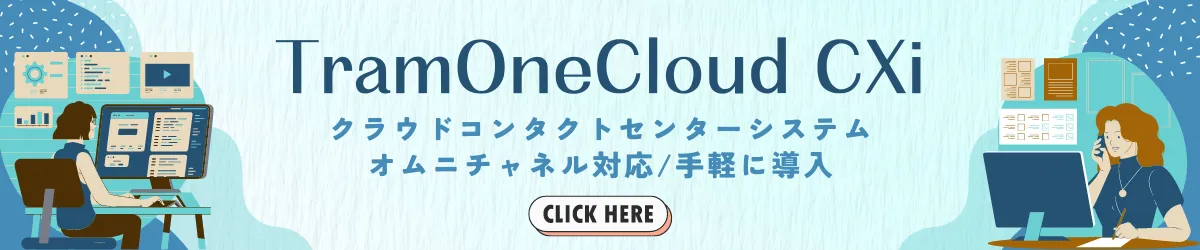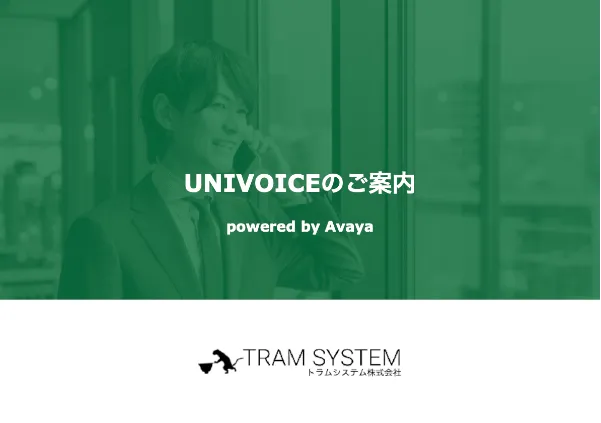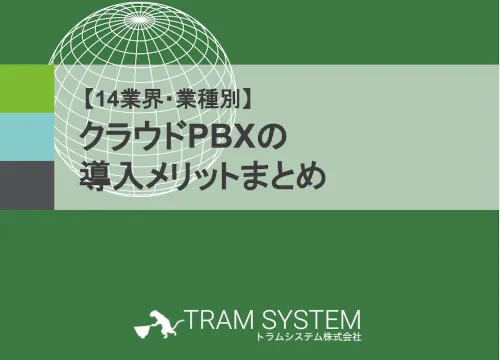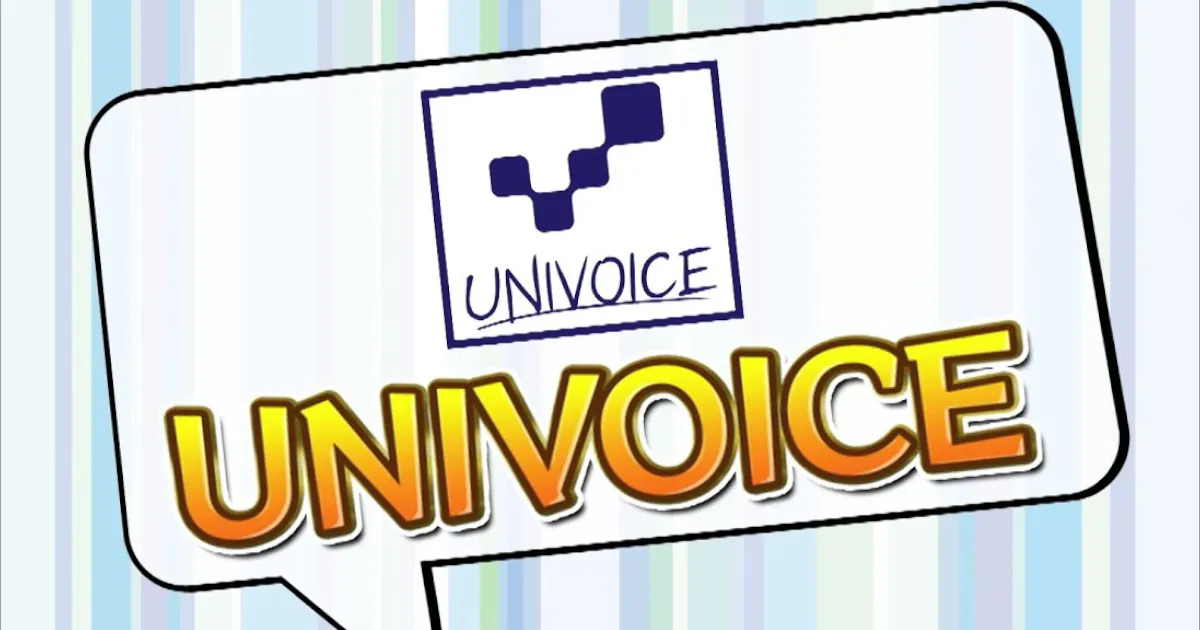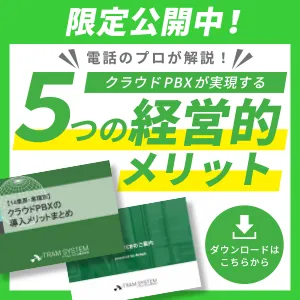Windows Azureが選ばれる理由を解説します|トラムシステム

目次
クラウドサービスとは
クラウドサービスのクラウドは、クラウドコンピューティングを省略した言葉です。現在クラウドサービスは数多くリリースされており、今後クラウドサービスにほとんどのサービスが置き換わる可能性があります。
クラウドサービスについての理解は今後のビジネスの流れを把握するためには絶対に必要なことです。クラウドサービスの仕組みや使われ方について説明します。
クラウドサービスの仕組み
クラウドコンピューティングとはOSやサーバーなど、本来であれば物理的な機器が必要なコンピューターを、ネットワークを介してユーザーがサービスのみを利用できる仕組みを指します。
一例としてWeb会議のクラウド版をサービスとして利用するとします。Web会議システムは本来テレビなどの設備の導入を行わなければ利用できません。しかしクラウドでサービスを利用すると、サービスを提供している企業のホームページにアクセスし、契約を決めたなら必要なパッケージをユーザーのコンピューターにダウンロードするだけで利用することができます。
このように実物の機器を必要としないため、サービスをすぐに始めることができます。サービスのみを提供するため企業はコストを最小限に抑えられ、またユーザーは低価格でサービスを利用することが可能です。
仕組みとして、サービスのみを扱っていることやクラウドサービスの形態上パッケージ販売のような形式をとることができないため、月額いくらのサブスクリプション方式で、ユーザーは毎月定められた料金を支払います。サービスによっては使用した分だけ料金を支払う従量課金制のサービスもあります。
クラウドサービスの使われ方
多くの企業でGoogleドライブやOffice365のような社員で書類などのデータを共有・編集、メールやメッセージでのやり取りができるアプリケーションが使用されていますが、あれらは典型的なクラウドサービスであり、知らない内にクラウド上のサービスを利用しているといったケースが珍しくなくなってきました。
他にも先に説明したWeb会議サービス、顧客管理や防災管理など、Web上で手軽にデータを扱えるので、幅広く利用されています。
また、後に詳しく説明するAzureのようなクラウドプラットフォームサービスも主にエンジニアなどの開発者の間で支持を集めています。
Windows Azureが選ばれる理由
Windows Azureは現在ではMicrosoft Azureと名称を変更していますが、Windows Azureという名称になじみのある方も多いかもと思い、今回はWindows Azureの名称を使用しています。
市場のシェア
Azureはパブリッククラウド市場の中でもAmazonのAWSと1、2を争うシェアを誇っています。AWSの方がずっとシェア率で先行していたのですが、AzureがじわじわとAWSに迫り、2018年のシェア率ではAWSを僅かながら追い抜いているというデータもあります。
Azure、AWSに続くのがGoogleのGoogle Cloud PlatformやIBM、Oracleです。また中国のAlibabaも僅かながらシェアを獲得しており、今後アジア圏を中心にシェアを伸ばすのでは、と思われます。
いずれにせよAzureは今のところクラウドプラットフォームサービスではトップレベルのシェア率を獲得しており、安心できるサービスであることが分かります。
Windows Azureのサービスカテゴリーの概要
Azureのソリューションを確認すると、モノのインターネット (IoT)、人工知能、SAP on Azure、ブロックチェーン、ハイブリッド クラウド アプリケーション、分散型 ID、DevOps、モバイルなど一通りのサービスは揃っています。
それだけではなく、eコマース、Azureのガバナンス、Confidential Computing、SharePoint on Azure、Dynamics on Azure、Red Hat on Azure、LOB アプリケーション、開発とテスト、監視、ビジネスインテリジェンスなど、本当に数多くのカテゴリーが充実しています。
また製品の部分を見ると、AI+機械学習、データベース、ネットワーク、メディア、DevOps、ID、モノのインターネット(IoT)、Microsoft Azure Stack、モバイル、Strageなどのカテゴリーに分かれています。
ここで紹介したカテゴリーはあくまでも大ざっぱなもので、それぞれ更に細分化されています。全て含めると400を超えるサービスがあるので、ユーザーはあらかじめAzureをどのように使うのか決めておかないと迷ってしまうかもしれません。
料金体系
Azureの料金体系は基本的に従量課金制で、かつ最初は無料で始めることができます。どれくらいかかるのかというのは利用の仕方でかなり料金が変わってくるので、一概に述べることはできません。
Azureのホームページから料金を計算することができるので、利用したいサービスがあればおおよその料金を試算することができます。
Windows Azureのメリットとデメリット
Azureのメリットとデメリットについて説明します。クラウドプラットフォームサービスをお探しの場合、Azureは魅力的なサービスではありますが、良い面ばかりではありません。
メリットとデメリットを把握し、最適なサービスかどうか確認してください。
コストがオンプレミスに比べ安い、初期費用は不要
オンプレミスの場合、どうしても初期費用がかかります。開発のための環境を整えようとすると、オンプレミスだとライセンスを取得するだけでも何百万円もかかることがあり、初期費用がかなり高額になります。
比較すると同じ程度の環境を自社で構えることを目的とすれば、クラウドサービスの方がはるかに導入がしやすく、費用もかからないことが分かります。
設定や運用が不要で開発に集中できる
オンプレミスで設備を導入すると初期設定などが必要になりますし、運用の際も滞りなく動かすために点検を行う必要があるなど、どうしても様々なことに気をとられてしまいます。
しかしクラウドサービスならばサービスがパッケージ化されているので、開発環境が簡単にデバイス上に作り出せます。点検などの作業をサービス側が行っているため、開発のみに集中できるのです。
選べるサービスが多い
いくらクラウドサービスの利便性が高くても、選べるサービスが少ないと利用できるユーザーは限られてしまいます。しかしAzureをはじめとして現在のクラウドプラットフォームサービスはサービスの種類が豊富で、開発環境を求めている方のほとんどの要望を満たすほどに充実しています。
利用した分しか料金がかからない
オンプレミスならば仮に設備導入後まるで使わなかったとしても導入分の費用はかかります。月額いくらと決まっているサービスの場合、使わなくても決まった額が必要になります。
しかしAzureのように従量課金制だと、利用した分しか費用がかかりません。なのでほとんど利用しない場合、格安でAzureを利用することができ、費用的にかなりお得になります。
オンプレミスに比べてカスタマイズ性に乏しい
オンプレミスに比べてカスタマイズ性に乏しいのが難点です。というのも、クラウドサービスの場合サービスが既にパッケージ化されている状態で利用しますので、オプションサービスの追加くらいしかできることがないからです。
とはいえ以前に比べるとパッケージの種類も増えてきましたので、カスタマイズのためにオンプレミスの設備が必要になるユーザーはとても少ないのではと予想されます。
長期的に運用する場合オンプレミスよりも高くなる場合も
オンプレミスの場合、初期費用はかかるものの、運用年数が長くなるとクラウドサービスのように使った分だけ費用が発生してしまうといったことはないため、何年も使うのであればオンプレミスの方が費用的に安く抑えられることがあります。
ただアップデートなど運用のためのコストは絶対にかかりますし、クラウドサービスのように開発以外のコストをサービス提供側がやってくれるということはありません。オンプレミスかクラウドかという選択は一長一短であるため、自社でどのようにシステムを利用するかよく熟考する必要があります。
保守運用ができる技術者が育たなくなるかも
開発のみに集中できる環境であるということは、開発以外のことに対する技術力がまるで育たなくなるということでもあります。オンプレミスでシステムを運用することで技術者は自然と運用のための知識などを習得していきますが、そういった過程を社員の誰もが踏めません。
クラウドサービスがどんどんと増えてきている昨今なので、開発者さえいれば業務は十分にまわるでしょう。しかしいざ保守や運用に詳しい技術者の力が欲しいと思ったときに、新たに誰かを雇うか、外部の詳しい人間に相談するかくらいしか手がなくなり、自社ではどうにもできなくなります。
Windows Azureが選ばれる理由
Windows AzureはMicrosoftのサービスであるという点で信頼性が高く、企業で利用されているほとんどのOSはWindowsであることなどから利用するユーザーが多いです。無料で始められるという意味で資金のない企業でも導入がしやすく、とりあえず使ってみてから本格的な導入を検討するという企業もたくさんあります。気軽に利用できる点が魅力のWindows Azure、一度利用してみてはいかがでしょうか。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。