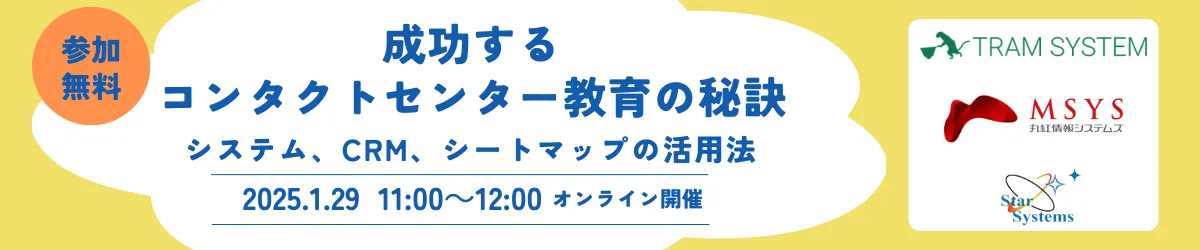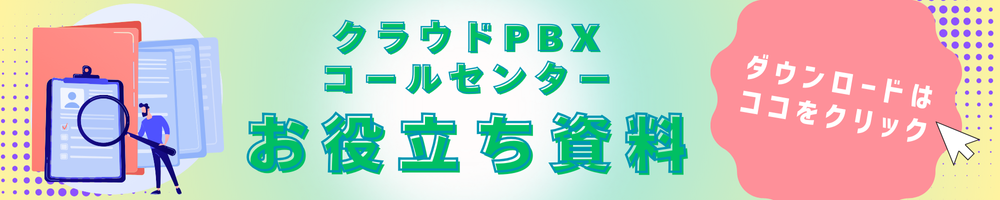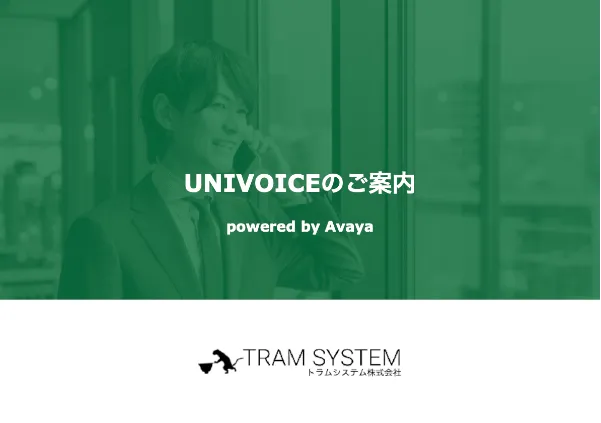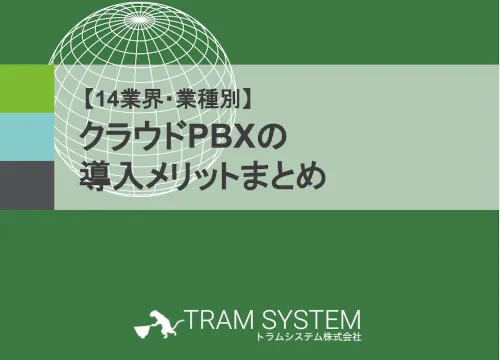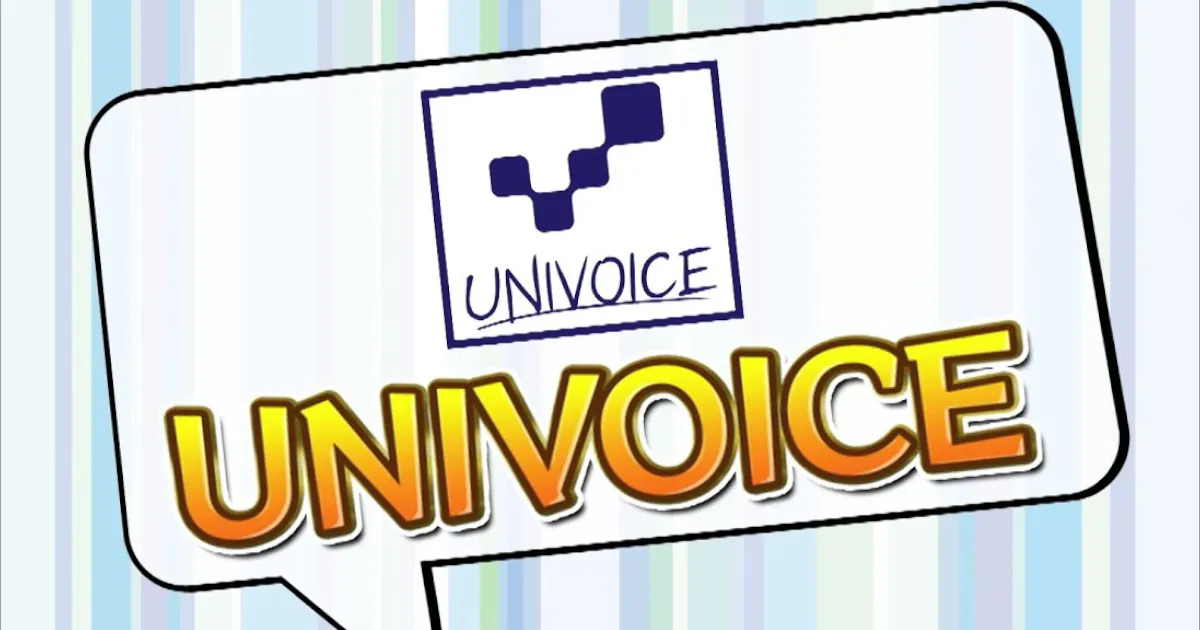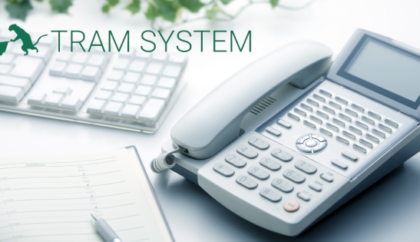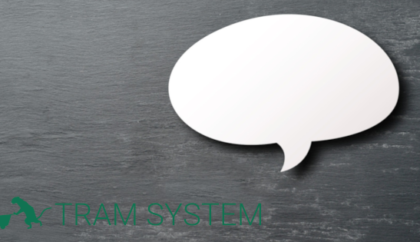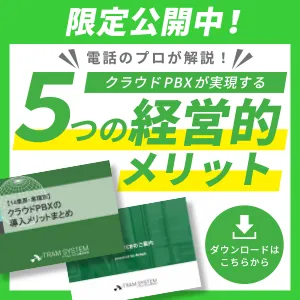社用携帯の私的利用はバレる?企業が監視できる内容・必要なルールを解説|トラムシステム
会社から貸与される社用携帯(スマートフォン)は、業務目的にのみ利用するのが原則です。しかし「少しだけなら」と、家族や友人への連絡や私的なネット検索など、業務外の目的で利用したことがある方もいるかもしれません。
実際、社用端末を私的利用してしまうと、企業にバレるのでしょうか?また、企業は従業員による社用携帯の私的利用を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか?
この記事では、社用携帯の私的利用にあたる行為や、企業が社用携帯の利用を監視する方法などを解説します。

目次
社用携帯(スマホ)の私的利用とは
会社から従業員に配布される社用携帯(スマホ)は、原則業務にのみ利用するものです。このため、業務以外の目的での利用は、全て私的利用になります。
具体的にどのような行為が当てはまるのかを詳しく見ていきましょう。
プライベートに関する通話・メール
同僚や友人と飲み会などのプライベートな用事について電話をしたり、仕事終わりに会社の携帯で家族に帰宅時間の連絡を入れたりする行為は、私的利用にあたります。
社用携帯は、仕事中は肌見放さず持ち歩くため、つい私物のような感覚を持ってしまいがちです。しかし、社用携帯はあくまで業務上の連絡に用いるものであるため、プライベートの用件は個人のスマートフォンなどから連絡するようにしましょう。
業務に関係のないWebサイトの閲覧
業務に関係のないWebサイトの閲覧やプライベートな内容をネット検索、プライベートのSNSの閲覧なども、私的利用に該当します。
一方、取引先に訪問するために、会社の住所や行き方を調べたり、資料作成のためにネットで情報を収集したりする行為は、社用携帯の利用範囲内です。
業務に関係のないアプリのダウンロード
社用端末は従業員が勝手にアプリをダウンロードできないように制御されているケースが多いですが、その制御がない場合でも、私的なアプリのダウンロードは行うべきではありません。
アプリの中には、悪意を持った者が情報収集や端末の遠隔操作などを目的にウィルスなどを仕込んでいるケースがあるためです。万が一そのようなアプリが原因で情報漏洩などのセキュリティ事故が起こらないよう、個人の判断でアプリをダウンロードするのはやめましょう。
社用携帯の私的利用は会社にバレる?
結論から言うと、社用携帯の私的利用は、企業にバレる可能性が高いです。
社用携帯を従業員が頻繁に私的利用することで、企業側は業務外の目的で使った通話やネット検索についても料金を支払うことになります。1ヶ月ごとや1人あたりの金額は少額であっても、それが長期間、従業員数の多い会社で続くとかなりの金額になるでしょう。
このため、企業は配布した社用端末が適切に使われているかを、利用明細やツールなどでチェックするのです。
私的利用が会社にバレると、私的利用分にあたる通話料やデータ通信料を会社から請求される可能性もあります。このようなトラブルが起こらないよう、会社は社用携帯の利用ルールを明確に定め、従業員はそのルールをしっかり守ることが重要です。
社用携帯(法人携帯)で監視できる内容
具体的に、企業は社用携帯のどのような内容をどこまで監視できるのでしょうか?企業が従業員による社用携帯の利用履歴を確認する主な方法は、①毎月の利用明細などの情報と②MDM(モバイルデバイス管理)ツールの2つです。
毎月の利用明細
通信会社から毎月送られてくる利用明細からは、対象月の通話時間やデータ通信量を見ることができます。ある社員の通話時間や通信量が他の社員よりも極端に多い場合には、業務以外で利用している可能性が疑われます。
MDM(モバイルデバイス管理)ツール
MDM(モバイルデバイス管理)ツールとは、スマートフォンやタブレットの一括操作や一括設定、遠隔操作、セキュリティ対策を目的としたツールです。
MDMツールを利用することで、企業は通話時間やデータ通信量などに加えて、インストールされているアプリやアプリの利用状況などを見ることができます。
例えば、業務時間外にブラウザアプリを多く利用していたり、企業で許可していないアプリをインストール・閲覧していたりすると、私的利用の可能性があると判断できます。
【企業向け】社用携帯の私的利用を放置するリスク
MDMツールなどで従業員の社用携帯の利用状況の確認などが行えるとはいえ、社用携帯を保持している全ての社員について都度確認するのは非常に手間のかかることです。
しかし、たとえコストがかかったとしても、社用携帯が適切に使用されているかをチェックすることは重要です。
ここからは、社用携帯の私的利用を企業が放置するリスクを紹介します。
通信コストの増大
数分間の通話や2,3ページのWebブラウザの閲覧であっても、社用携帯を利用するとその都度通話料やデータ通信料が発生します。1回ごとに発生する金額が小さなものであっても、それが企業規模・年単位となれば金額は見過ごせないものになるでしょう。
さらに、企業側が指摘や監視を行わないことで、「私的利用してもバレない」と従業員が考えてしまい、さらに私的利用が広がる可能性もあります。
無駄な通信コストによって事業に影響が出ないよう、企業はコストをかけても対策する必要があります。
セキュリティリスク
社用携帯には、同僚や取引先の連絡、業務に関するメールやチャットの履歴、ファイル共有サービスへのアクセスなど、様々な機密情報が保存されています。
しかし、社用携帯の私的利用として本来は許可されていないアプリのインストールやブラウザの検索が行われることで、以下のようなセキュリティリスクが高まります。
・マルウェア感染リスク
・不正利用リスク
・情報漏洩リスク
この他にも、セキュリティ意識が低いまま社用携帯を利用・持ち歩きすることで、盗難や紛失のリスクも高まります。
情報漏洩などのセキュリティリスクは企業の信用にも関わる問題であるため、しっかりと対策をしておくことが重要です。
【企業向け】適切な社用携帯運用のためのルール作りのポイント
社用携帯の利用に関するトラブルを避けるためには、あらかじめ利用ルールを定めておく必要があります。ここからは、具体的なルール作りのポイントを紹介します。
私的利用の禁止・発覚時の罰則
私的利用を禁止することを、具体的な禁止事項をともに周知しましょう。
「業務外の内容について電話をする」「友人や家族にメールを送る」など、例をあげて説明することで、社員は具体的にどのような行為が私的利用にあたるのかが理解できます。緊急時を除き、社用端末の利用を業務時間内に限定することも効果的でしょう。
加えて、「明らかな私的利用が発覚した際には、私的利用該当分の通話料・データ通信料を利用者から徴収する」といった私的利用が発覚した際の罰則について定めるのも方法の1つです。
利用状況の把握
MDM(モバイルデバイス管理)ツールなどを導入し、企業側で社用携帯の利用状況の把握や制御・一括操作ができるようにします。その上、従業員には必要に応じて利用状況や履歴を確認する可能性があることを周知しましょう。
「私的利用が疑われる際には、通話やメールの履歴、アプリの利用状況などを確認する」としておくことで、私的利用を抑制する効果も期待できます。
セキュリティ対策
MDM(モバイルデバイス管理)ツールやセキュリティソフトなどによる基本的なセキュリティ対策に加えて、従業員自身が高いセキュリティ意識を持って社用携帯を扱えるようにする取り組みも重要です。
安全な社用端末の運用には、その端末を利用する社員個人の協力が欠かせません。例えば、セキュリティ教育などを通して以下のようなルールを徹底させましょう。
・OSやアプリは常に最新バージョンにする
・公共のWi-Fiは利用しない
・送信元が不明確なメールは開封しない
まとめ
社内外の仕事の関係者との日々のコミュニケーションに欠かせない社用携帯は、スムーズな業務遂行に欠かせない一方、従業員による私的な用途にも利用されやすい一面があります。
企業側はMDMツールの活用や運用ルールの設定など、私的利用を防ぐ取り組みをしましょう。また、従業員は「社用携帯は業務目的にのみ利用する」という意識を持ち、適切なシーンでのみ利用するようにしましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。