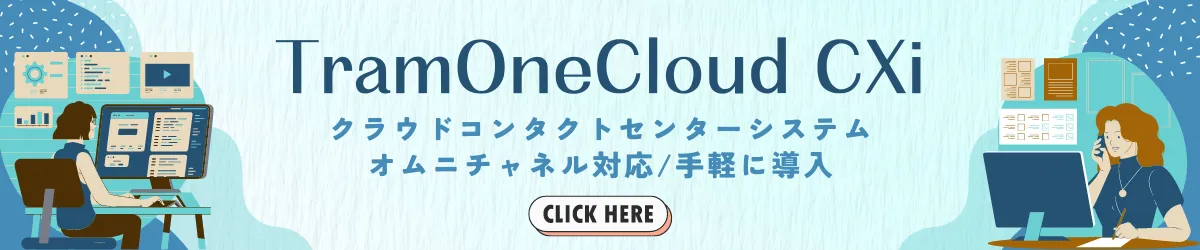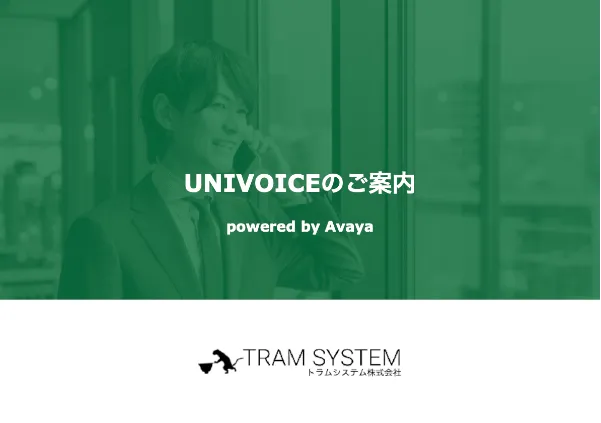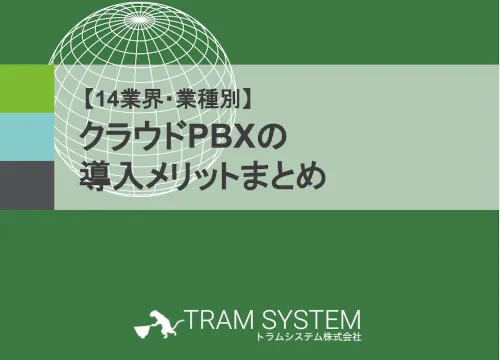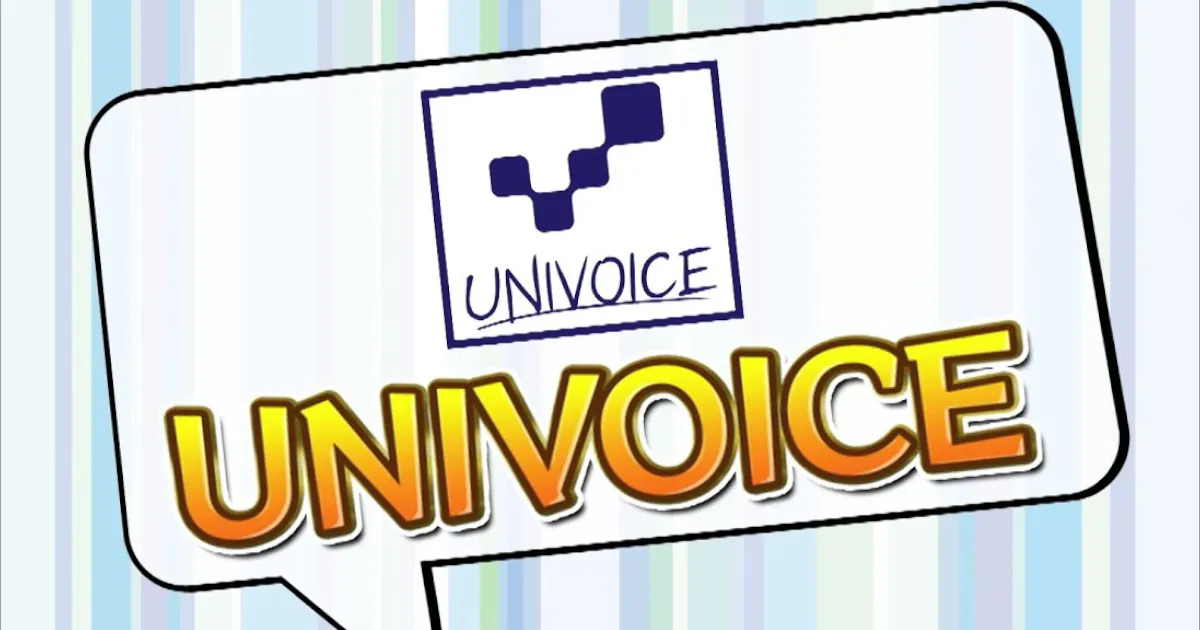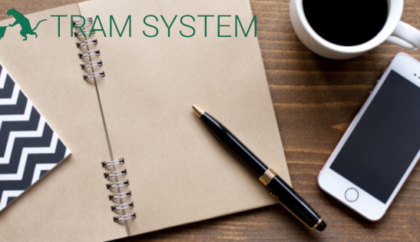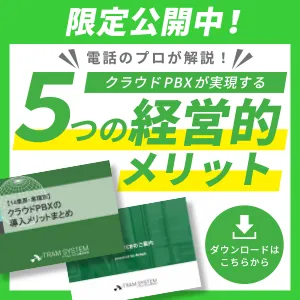PBXの機能|PBXの機能と汎用性を解説|トラムシステム
コールセンターやコンタクトセンターを運営している、もしくはこれから立ち上げようと考えている方にとって、業務を効率的に進めるためにも、お客様の満足度を上げるためにも、お客様からの問い合わせを制御するPBXは最も関心の高い製品の一つと言えるでしょう。
一方でPBXは搭載されている機能が多岐にわたるため、PBXについて興味がある方からは、
「PBXって機能がたくさんあるけど、どういったことができるの?」
「最近のPBXは他システムと連携するケースが多いって聞くけど、どんな連携ができるの?」
「クラウド化って話をよく聞くけど何がいいの?」
といったお話をよく聞きます。
そこでこの記事では、PBXの機能について詳しく知りたい方、機能比較している方向けに、PBXの主な機能とPBXで連携できるサービス、またPBXをクラウド化することで強化される機能について詳しく解説していきます。この記事を読むことで、PBXが提供している機能について詳しく理解できるため、今後のPBX検討の役に立つことでしょう。

目次
PBXの主な機能
まずはPBXで提供されている機能を見ていきましょう。
着信制御
PBXではお客様から問い合わせの電話を受ける際、契約している電話回線ごとに割り振られる電話番号で着信するのではなく、契約している電話番号を親番号として、親番号に紐付いている電話番号(子番号)ごとに着信させる機能を提供しています。
電話回線の契約数が月額費用として発生するため、例えばオペレーターの数だけ電話回線を契約すると高額な月額費用が必要になりますが、子番号で制御することで月額費用を押さえられます。この機能はダイヤルイン機能と呼ばれています。
発信制御
外線への発信を制御する方法として、LCR(Least Cost Routing)とACR(Automatic Carrier Routing)があります。
LCRとは、プッシュされた電話番号を検知すると、相手先の電話番号に応じて一番安いプロバイダーを自動的に選択して発信する機能です。自動的に接続されるため、利用者は待ち時間や特別な操作なく通話料を押さえた電話発信ができます。
ACRとは、あらかじめ決められたプロバイダーに自動的に接続される機能です。通話料の削減という機能についてLCRに見劣りしますが、LCRを搭載したPBXの購入費用は高額になるため、初期費用を押さえつつ、通話料もある程度押さえたい場合に利用されます。
代表番号着信機能
お客様から代表番号に着信があった際にあらかじめ登録されている電話機に接続する機能で、優先順位付けをして優先順位が高い接続先からつないでいく方法もあれば、電話番号順につないでいく方法もあります。
転送機能
担当者が不在、もしくは通話中の際に他の電話機に転送する機能で、不在転送や話中転送、圏外転送など状況に応じて適切な担当者につながるような制御しています。
パーク保留機能
通話中にパーク保留機能を使用すると、他の電話機で外線に応答できる機能です。
例えば、お問い合わせを受けた担当者が受け答えできないような詳しい質問や、お客様からの問い合わせ内容が担当する商材、サービスと異なっていた場合など、他の担当者に対応してもらう必要が出てきます。そういったケースでパーク保留機能を使うと外線は一度保留とされ、その間に担当者は該当する担当者に情報共有をして対応を依頼することになります。依頼を受けた担当者は自分の電話機で再開することで、そのままお問い合わせに対して継続して応対できます。
ここまで解説してきたPBXですが、従来のビジネスフォン(主装置)とは何が違うのでしょうか。
ビジネスフォンとの違いとしては、
・スマートフォンなどの携帯端末の内線化
スマートフォンからの会社への通話を内線化させることで、通話料をカットできます
・別拠点同士の内線化
離れた拠点(オフィス)同士を内線接続させることで、たとえ海外との電話であっても通話料をカットできます
・CTI機能
電話でお客様応対をする際に他システムのデータを連携してお客様情報や対応履歴などを表示させる機能であり、主にコールセンターやコンタクトセンターで重宝される機能
などが挙げられます。
社員間のコミュニケーションをすべて内線化させることで通話料をカットできるため、月々必要になる月額費用を押さえられるほか、事業計画を考える際にも必要なコストを予測しやすいメリットもあります。
PBXで連携できるサービス
PBXの主な機能を解説したところで、PBXで連携できるサービスを紹介します。特にコールセンターやコンタクトセンターといった大規模な電話システムを必要とするような業務では、電話をするだけの機能だけではなく、お客様の満足度を向上させるために、他システムとの連携が必要になってきます。
・CTI機能
CTI(Computer Telephony Integration)は、電話とコンピューターを統合させるシステムと意味するもので、お客様から電話がかかっていた際に、電話の着信を受けるのと同時にそのお客様の情報をオペレーターのパソコンに表示させる機能です。
CTI機能を利用するメリットは大きく2つあります。
1つはお客様情報を即座に確認できる点です。もちろん、過去のお客様とのやり取りも閲覧することもできるため、お客様の情報をあれこれ色々なシステムで確認しなくても状況を把握できます。お客様を待たせることや、過去に確認した質問を再度行う必要もなくなることから、お客様の満足度向上や業務効率を上げるためには不可欠になっています。
もう1つは、お客様との通話内容を録音できる点です。お客様との通話をいつでも再生、削除、記録できるため、後にお客様からクレームがあった時などのトラブルシューティングで活用できます。また、熟練のオペレーターの応対状況を記録して新人のオペレーターに伝えることで、新人のスキルや、応対品質を向上させられるため、コールセンター全体の対応品質向上に繋がります。
CTI機能では、主に3つの機能が提供されています。
ポップアップ機能
かかってきたお客様の電話番号からお客様情報を検索して、使用しているパソコン上に表示させる機能です。また、通話中に検索して必要な情報を表示させることも可能です。
CRM連携機能
顧客情報を管理しているCRMシステムとの連携をさせる機能で、お客様の情報を確認しながら応対できるようになります。お客様との通話前に過去の取引状況、潜在顧客なのか重要顧客なのかなど、オペレーターが対応に必要となる情報を供給できます。そのため、より細かいお客様サポートができたり、新しい付加価値提案できたりと、コールセンターでは必要不可欠な機能の一つと言えます。
通話録音機能
お客様との応対内容を記録して、いつでも再生や削除ができる機能です。お客様から問い合わせがあった際でも確認できるため、聞き漏らしがあった場合や過去の対応状況を再確認する際に役に立ちます。
・CRM機能
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客管理システムと呼ばれ、お客様との過去の対応履歴や取引情報、担当者情報などが管理されているシステムのことです。CRMと連携させることで、電話応対する前や応対中にこういった情報を確認できるようになります。
CRM機能を利用するメリットは大きく3つあります。
様々なコンタクトポイントからの情報をまとめて一括管理できる
電話やメール以外にも、最近はLINEやチャット、SNSなど様々なチャネルを利用する機会が増えてきました。必然的に企業と利用者のコンタクトポイントもこれらのチャネルになってくるわけですが、それぞれ別々のシステムで管理すると煩雑で使いにくいものになるため、様々なコンタクトポイントからの問い合わせや対応履歴を一元的に管理することで効率的な企業活動ができるようになります。
蓄積した顧客情報を基にデータ分析ができる
これまで対応してきた顧客情報をデータ分析することで、お客様の問い合わせ内容の傾向、回答内容によるその後のフォローアップの必要性、トラブルが発生する時の条件など、コールセンター全体の改善や会社そのものの経営方針策定まで幅広い分析が可能になります。
顧客情報をセグメント化して条件抽出できる
例えば、メール配信ツールでお客様宛に新しい商品を紹介して購買促進させる際、いたずらにすべてのお客様にメール配信をしてしまうと、非効率的な上に、メルマガ配信拒否による次回以降の施策実行が困難な状況に追い込まれてしまいます。そのため、需要がありそうなお客様に限定する必要が出てくるわけですが、その時に出てくるのがセグメント化(ターゲット化)が必要になります。
顧客情報をセグメント化させることで該当するお客様を限定できるため、その情報を使ったマーケティング施策やフォローアップメール、アンケート依頼など様々な業務に活用できます。
PBXをクラウド化
これまで解説してきたPBXですが、最近は従来のオンプレミス型ではなくクラウド型で検討されることが増えてきています。ここでは、クラウド型を利用することで強化される主な機能を整理していきます。
外出先からでも代表電話で電話ができる
例えば、PBXをクラウド型にすることで、
・外出先から代表電話を使ってお客様に電話をしたい
・在宅ワーカーが代表電話を使ってお客様対応をしたい
・営業業務を外注している企業に代表電話を使ってアウトバウンドコールをさせたい
などの用途で利用ができるようになります。
もちろん、携帯端末(スマートフォン)などに対応しているため、最近流行りのBYOD(Bring your own device)と呼ばれる社員のプライベート用携帯端末でも利用ができます。また、最近は働き方改革と日本の労働人口の減少という2つの問題から、在宅ワークも盛んになってきています。
コールセンターに限れば、出産のため退社を余儀なくされていた熟練のオペレーターを再雇用できれば、オペレーターを新人から鍛え上げるための時間とコストも不要になり、いつ採用できるかわからないオペレーターの確保も不要になることから、外出先や自宅から代表電話を使って仕事ができるのは価値が高いと考えられています。
社員間のコミュニケーションに内線が利用できる
もう一つのポイントは社員間のコミュニケーションに内線が利用でき、その結果大幅な通信料の削減が期待されます。従来のオンプレミス型の場合であれば同じフロアのコミュニケーションまでは内線が使えますが、例えば遠く離れた拠点との通信には外線を使用する必要があるため、通信料が発生してしまいます。
しかし、クラウド型を利用できれば、例えば海外の拠点との通話もすべて内線で対応できるため、通信料が発生しないため、通信料を気にしないで円滑なコミュニケーションができる機会を設けられます。
まとめ
PBXも従来の主装置から機能強化されて使いやすくなってきていますが、最近はさらにオンプレミス型からクラウド型へと使い勝手の向上と機能の拡張、大幅な初期費用削減といったことが実現され、これまで解決できなかった課題や、労働人口の減少と人手不足により採用が困難になって来ている状況にもある程度対応できるようになってきています。
PBXを導入することで実現したいことをまとめていきながら、クラウド型で新たにできることを考慮に入れつつ、自社にあったPBXを選んでみてはいかがでしょうか。
おすすめクラウドPBX
おすすめクラウドPBXとして、トラムシステム株式会社が提供するTramPBX Cloudのサービスがあります。
TramPBX Cloudとは
TramPBX Cloudとは、ビジネス用電話機(PBX/ビジネスフォン)をクラウドサービスにした、クラウドPBXになります。内線電話、外線電話、パーク保留、転送、留守電が利用可能です。
インスタントメッセージ、チャット、電話会議、Web会議、在籍確認などの通信サービスを統合したユニファイド・コミュニケーション機能も実装しています。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。