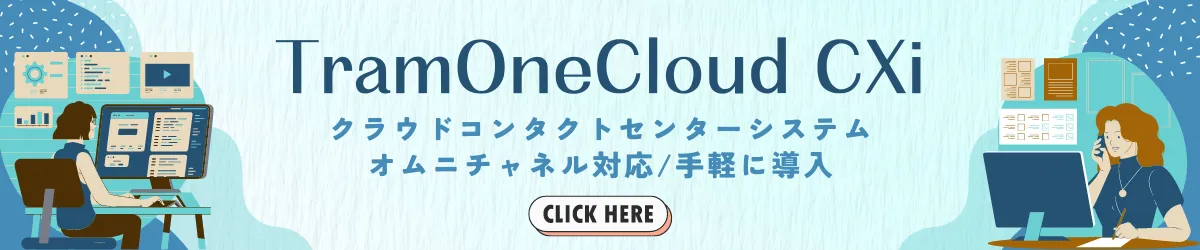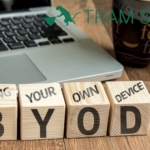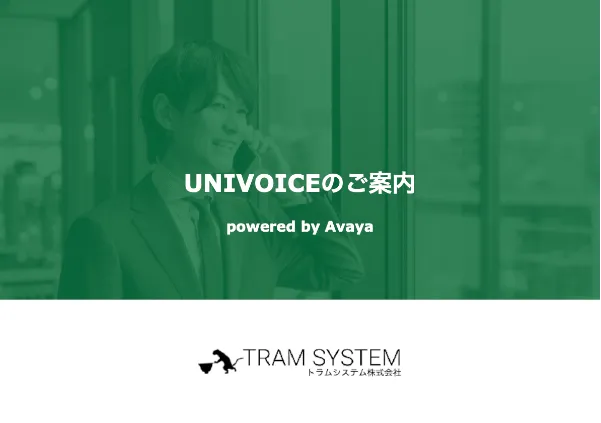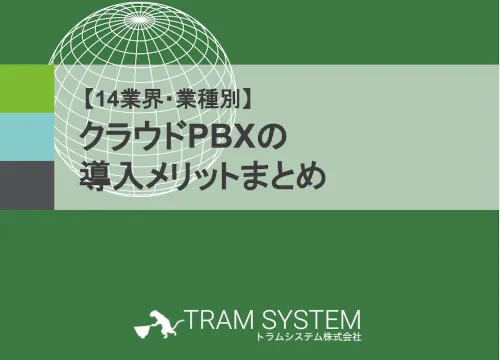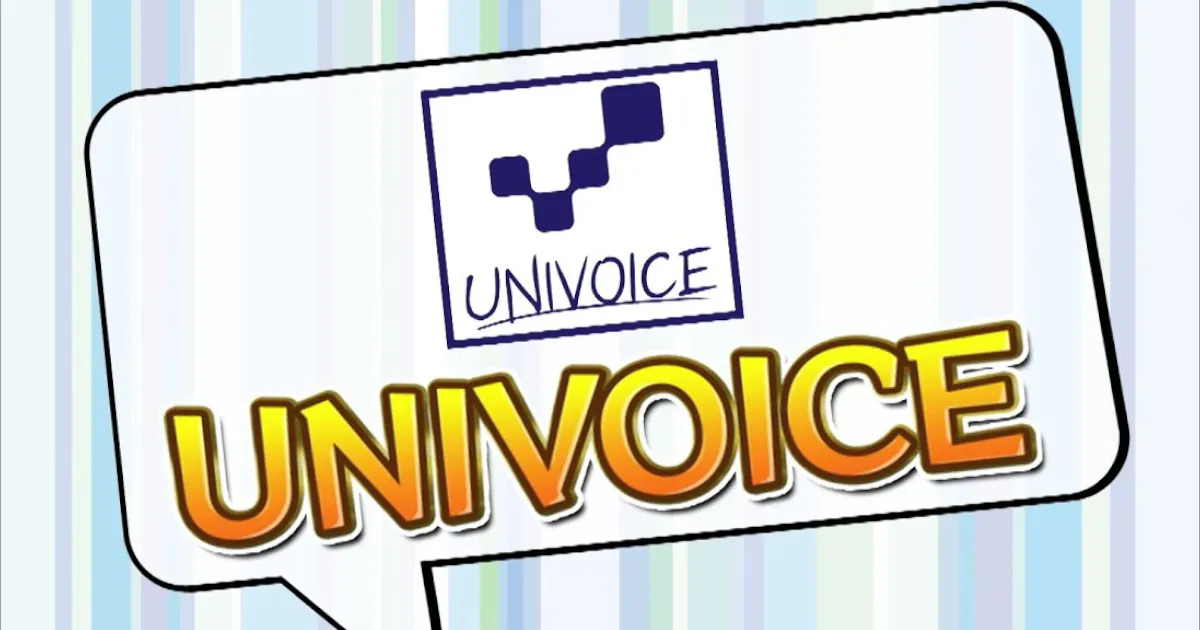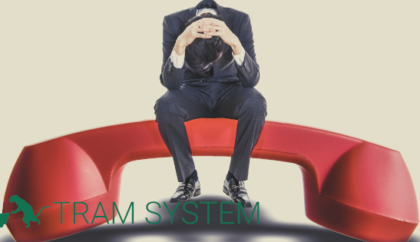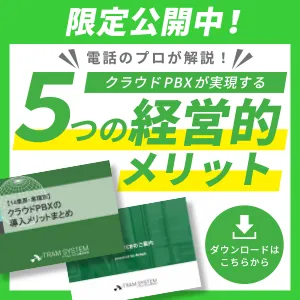BYOD導入事例4選!メリット・デメリットや危険な勝手BYODも解説|トラムシステム
働き方改革やテレワークを推進するとして注目されているのが、従業員が保有するスマートフォンなどの携帯端末を業務利用するBYODです。実際に導入した企業では、コスト削減や生産性向上などの効果が出ています。
この記事では、BYODのメリットやデメリット、導入事例について解説します。

目次
個人スマホを業務で利用する「BYOD」とは
BYOD(Bring Your Own Device)は、従業員が個人で保有する携帯端末を業務利用することです。スマートフォンだけではなく、パソコンやタブレットもBYODに含まれます。厳密にいえば、USBフラッシュメモリ、SDカード、HDDといったメディア機器もBYODの対象です。
BYODが普及する以前、会社は業務用端末を購入して従業員に支給していました。しかし、規模によっては数千人に及ぶ従業員全員に端末を支給するのは、コスト面で大きな負担です。
BYODは端末にアプリをインストールするだけで業務利用を実現するため、コストパフォーマンスに優れる手法として流行しています。
BYODが普及している背景
BYODは、社会状況の変化に応じて普及が進んでいます。
背景の1つとして挙げられるのが、働き方改革の推進です。テレワーク、在宅勤務、フリーアドレス、フレックスタイムといった時間や場所に囚われない働き方が求められるようになり、オフィスにほとんど出社しない従業員も増加しました。
そのような環境に対応するため、従業員の個人用端末があればコミュニケーションが実現するBYODが注目されています。使い慣れたデバイスを利用することで、ストレスのない効率的な業務環境も実現可能です。
また、ノートパソコンの軽量化やクラウドサービスの発展といった技術進化もBYOD普及を後押ししています。特に、小型ながらもパソコンと同等の性能を持つスマートフォンの普及が大きな影響を与えました。電話、メール、チャット、情報検索を1台でこなせるため、BYODのプラットフォームとして最適です。
BYODの導入事例4選
多くの会社や自治体がBYODの導入によって効率化や問題解決を実現しています。事例と同じような状況に陥っている企業は、BYODの導入を検討しましょう。
コニカミノルタ
電気機器メーカーのコニカミノルタは8年の歳月をかけ、2011年にスマートフォンを利用したBYODを導入しました。世界53ヵ国に拠点があり社員の出張も多いという風土のため、あらゆる場所でメール閲覧やスケジュール確認を行う必要があったからです。MDMツール導入を始めとするセキュリティ対策も合わせて実行しました。
その結果、2009年の在宅勤務制度導入から進行していた実質的なBYOD化(個人用端末を利用した業務)に対応しつつ、より高セキュリティな体制への移行を成功させています。業務も効率化され、社内でテーマとした「いつでも・どこでも・どんなデバイスでもコミュニケーションをとろう!」を実現しました。
大分県庁
生産性向上を目的とするICT活用を積極的に行ってきた大分県庁では、リモートワークの導入に伴い、BYODの導入を決定しました。
MDMを利用したセキュリティの強化を行いつつリモートワークの希望者を募ったところ、想定以上の希望者が集まるという結果を生んでいます。働き方の多様化や効率化は職員の間でも要望が高まっており、BYODの導入がそれを後押ししました。
インテル
半導体素子メーカーのインテルは、2010年からBYODの導入を開始しました。スマートフォン、タブレット、パソコンに至るまで、BYODの対象として接続を許可しています。
インテルがBYODを導入した最大の理由は、社員の生産性向上です。
「自分が扱いやすい最高のデバイスを利用する」という方針の下、各社員が利用するデバイスを自由に選択できるようにしました。それによって作業効率が向上するだけでなく、会議の合間や移動中といったスキマ時間に業務を行えるようになり、1日当たり57分の業務時間拡大を実現しています。
デンソー
自動車部品の世界シェアトップのデンソーは、iPhoneとiPadを利用したBYODを導入しました。希望者が利用するデバイスという位置づけとなっており、テレワーク時のコミュニケーション手段などに採用されています。
BYODの導入により、2014年の働き方改革に合わせて始まったテレワークを本格的に利用できるようになり、残業時間削減や働き方の多様化を加速化させることに成功。オフィスのペーパーレス化やフリーアドレス化も進み、業務全体の効率化を実現しました。
BYODのメリット・デメリット
すでに多くの企業で導入されているBYODですが、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
従業員側のメリット
従業員がBYODを利用する際のメリットは、以下の通りです。
・時間を有効活用できる
私物の端末を利用することで、移動中やスキマ時間を利用したリモートワークが可能となります。
・好みの端末を使える
自分好みの使いやすい私物の端末を業務利用できるめ、モチベーションや生産性向上が可能です。
・端末を統一できる
複数の端末を使い分ける必要がなくなり、管理にかかる手間やストレスを軽減できます。
従業員側のデメリット
逆にデメリットとして挙げられるのが、以下の3つです。
・端末の管理責任が発生する
紛失時のリスクが倍増するため、常日頃から慎重に管理しなければなりません。
・通話費用の自己負担
費用申請に関するルールが定められていない場合、業務で発生する通信費用を自己負担しなければなりません。
・プライベートの侵害
紛失リスク対策としてMDM(モバイルデバイス管理)を行う会社も増加していますが、端末の監視を強化するほど、従業員のプライベートは失われていきます。
会社側のメリット
会社側から見たBYODのメリットは、以下の通りです。
・生産性向上
従業員が使い慣れた個人用端末を利用させることで、業務の生産性向上が見込めます。
・コスト削減
新規に業務用端末を導入する必要がないため、初期費用や維持費用を大幅にカットできます。
・従業員満足度の向上
従業員が使い慣れた端末をそのまま業務利用できるため、従業員満足度の向上が見込めます。
・ダイバーシティ(多様性)に対応
育児、介護、療養など、オフィスへの出社が難しい社員でも会社外での業務を可能とします。
会社側のデメリット
逆に、以下のようなデメリットも存在します。
・情報漏洩のリスクがある
私物の端末を利用する以上、データの不正取得や端末そのものへの攻撃といったセキュリティ面でのリスクがつきまといます。リモートでの端末ロックやワイプによる状況確認が必要です。
・労働の管理が難しい
24時間365日労働が可能となるため、従業員の時間外労働や過重労働が発生しやすい環境となります。
・制度が高度化しやすい
BYODを安全に利用するための制度規定が複雑化、高度化しがちです。事前の周知を怠った場合、混乱を招きます。
BYODのメリットやデメリットについては次の記事でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
BYODを導入しないリスクも
さまざまなメリットをもたらすBYODですが、セキュリティリスクを問題として導入しない会社も多数存在します。しかし、それによって情報漏洩のリスクが完全に無くなるわけではありません。BYOD未導入の会社で「勝手BYOD」や「シャドーIT」と呼ばれる新たなリスクが発生しています。
勝手BYODとは
勝手BYODとは、会社から許可を得ていない個人用スマートフォンやサービスを業務利用する行為です。10~20代社員はスマートフォンの利用に慣れ親しんでいるため、セキュリティリスクに関する教育を実行しない場合、悪意がなくても勝手BYODの状態に陥ってしまうケースが報告されています。
例えば、個人用のクラウドストレージに業務用ファイルを保存することも、勝手BYODとして多く報告されている現象です。個人用のサービスはセキュリティが万全でないケースが多く、データの紛失や流出が発生しやすい危険な行為と言えます。
シャドーITとは
シャドーITとは、Google ドライブ、OneDriveといったITサービスを、個人用アカウントで無許可のまま利用することです。例えば「若手社員が勝手にLINEでグループを作り業務連絡用とする」という行為は、シャドーITに該当します。
シャドーITが横行している会社では、それを禁止しようとしても一部社員から「効率的なのになぜ禁止するのか」と反発される可能性があります。他社で発生した情報漏洩事件やトラブルを紹介し、シャドーITがどれだけの危険をはらんでいるのか、きちんと説明しなければなりません。
勝手BYOD・シャドーITへの対策
勝手BYODやシャドーITには、以下のような対策を施しましょう。
・セキュリティ教育
勝手BYODやシャドーITの危険性を認知させ、従業員が主体的に抑止する仕組みを構築します。
・許容
定められたルールを守ることを条件に、ITツールや電子機器の利用を一部許容します。
・監視
社内外のクラウドサービス利用を監視するCASB(Cloud Access Security Broker)などのツールを導入し、機密情報の防御を行います。
・禁止
可能な範囲で、個人の所有物やウェブサービスを利用させない仕組みを構築します。
BYODのセキュリティ対策については、次の記事でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください
まとめ
BYODはセキュリティ面でのリスクはありつつ、コスト削減やコミュニケーション活性化などのメリットのために多くの会社で導入が進んでいます。導入しない会社であっても、勝手BYODやシャドーITへの対策は求められます。「便利だから」と勢いで進めるのではなく、メリットやデメリットを把握した上で自社の環境にマッチする形で導入を進めましょう。

WRITER
トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人
広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。